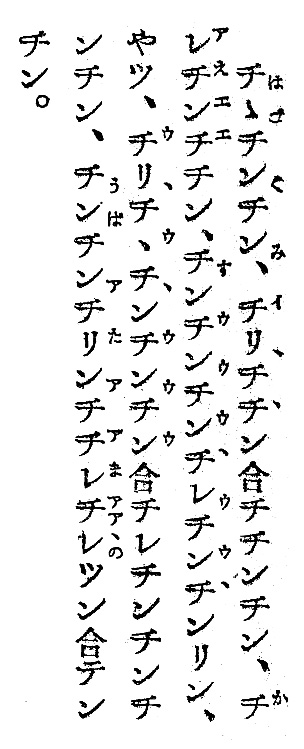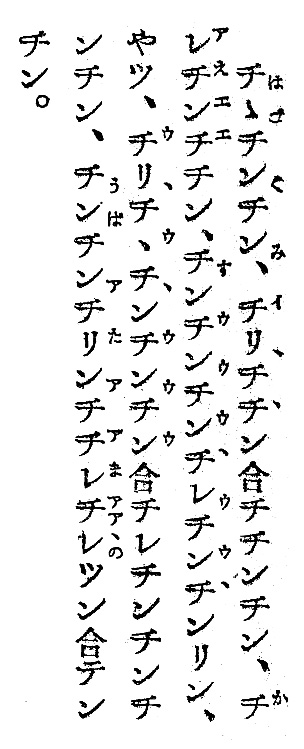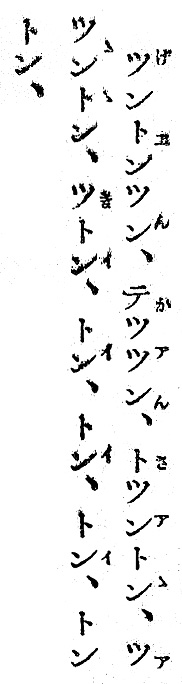FILE 118-1
【茶谷半次郎 鶴澤叶聞書】
(2016.01.05)
提供者:ね太郎
文藝春秋 10巻 11巻 (1932-1933)連載
文藝春秋掲載分以降は『文樂聞書』によった。(p275 文藏さんの三味線と「教興寺」以降。) また、文藝春秋連載部分については、単行本により適宜【 】内に補った
話者は四代目鶴澤叶、現今文樂座三味線筆頭(ふでがしら)。--故人三代目鶴澤淸六の門人。はじめ二代目鶴澤鶴五郎を名乘り、次に四代目鶴澤鶴太郎となり、大正二年一月先師の前名を繼いで四代目鶴澤叶となる。本名奥田德松。
筆者は師に就いて淨るりを習つてをります。勿論下手の横ずき、糠味噌を腐らして稽古宿に迷惑をかけること一方ではありません。以下は稽古のあひ間に、聯絡もなく師の語る藝談や、懷舊談を試みに、書止めてみたものであります。弧註は筆者記。
さうでした。ほんとうに偶然にも團平さんの亡くなられた日に私は稻荷座を覗きにいつたのでした。明治三十一年の四月一日であります。その頃淸六師匠(當時三代目鶴澤叶)の住居が、稻荷の西門の北の方にあつたので、稻荷座はすぐ近所でしたが、座へ出這入りしてゐる若い不良分子にかぶれることを恐れて師匠がやかましく云はれるので、滅多にいつたことはありませんでした。それで團平さんが偉いお師匠さんだと聞いて、かねがね聽きたいと思ひながらそれまで聽く折がありませんでした。時々稻荷座の廊下で、お弟子さんがお供して、手水にゆかれるのを遠くから見たことはありますが、舞臺の團平さんを見るのはその日がはじめてゞした。
その日私のいつた時は、恰度三代目大隅太夫さんの「志渡寺」を團平さんが彈いてゐられるところでした。小屋へはいつてゆくと、いきなり團平さんの三味線の大きな「たゝき」の絃の音がしましたのを、餘り大きな音なので何の音かと思ひました。すぐには三味線の音だとは思へませんでした。今思へば、「まさしく金比羅大權現--」の、一二三「すりあげ」の合の手のところであつたのです。私の師匠もよく彈かれたので、つねづね敬服してをりましたが、はじめて聽いた團平さんの三味線が、とても段ちがひなのに吃驚しました。しばらくすると小屋のなかゞ俄に騷々しくなつてきましたので、私は何のことゝもわからずに、そのまゝ小屋を出て仕舞ひました。その時團平さんが急に發病されたのであつたのをあとで知りました。これが聽きはじめの聽きをさめでしたが、一度でも名人の三味線を聽くことが出來たのを今に倖せに思つてをります。
「志渡寺」の「--はやせぐりくる斷末魔」といふところの合の手の、くり返しの二へん目が曖昧になつて、前へがつくりとなられたのだといふことです。奇異な因緣と思ひます。新左衞門さんと道八さん(當時友松)とが團平さんをかいて、團平さんの部屋が二階だつたので、五代目彌太夫さんの部屋へ入れたのでした。舞臺は豐澤龍助さんが着物のまゝで替りを勤めました。團平さんの病氣は腦溢血で、病院へ戸板で運ぶ途中で亡くなられたといふことです。【行年七十二歳でお有りなされました。】
團平さんは非常に力をこめて三味線を彈かれるので、しばらく彈いてゐられるとツボのところに凹みができたさうです。それでまたしても棹を削つてなほさねばならなかつたさうです。稽古三味線なんかとてもひどい溝ができたさうです。團平さんの左の手の力は非常なものであつたのです。
淸六師匠(當時叶)は文樂座に勤めてゐましたが、團平さんのところへ稽古に通つてゐられました。團平さんはいつでも、師匠がゆかれた時に、もし連中さん(素人の旦那衆)がさきにきてゐられるやうな場合には、「これで御飯を頂かねばならん者ですから--」と云つて、連中さんを後へ廻はして師匠の稽古をさきにせられたさうです。玄人には皆さうだつたさうです。さて稽古にかゝられたとなると、團平さんの氣のすむまでは、あとがつかへてゐてもお構ひなしに、午になつても御飯も食べずに稽古をせられるので、これには師匠の方がお腹(なか)が空いて時々弱られたさうです。稽古がすんで表へ出ると、そこいらで燒芋でも買つて食べようかと思ふほど、ペコペコになることがたびたびだつたさうです。「淸水町さんは偉いお人や」と始終に師匠は感腹して話してゐられました。(當時團平は島ノ内の淸水町、心齋橋筋東入る處に住居)
ある朝、師匠が團平さんのお宅へゆくと、二階で三味線の音がしてゐて、それが非常に上手な三味線なので、「誰やら、うまいこと彈きやはるなア。」と思うて感心して聽いてゐると、やがて二階から降りてこられたのが松葉屋の大師匠(五代目豐澤廣助)だつたので、吃驚して「お早やう厶います」と挨拶をしたと話してゐられました。私は文樂にゐて、團平さんは知りませんし、松葉屋の大師匠より偉い三味線彈きはないと思つてゐましたから、それを聞いて團平さんはどの位偉いのかと思ひました。
松葉屋の大師匠は見識の高いお人でしたが、藝の上では、分らないものがあれば團平さんの所へも研究にゆかれたのでありました。團平さんは名人でありますが、松葉屋さんもあれほどの大師匠であるだけに、そこが偉いところと思ひます。
團平さんの亡くなられたあとで、師匠(當時鶴澤叶)は文樂を出て稻荷座で三代目竹本大隅太夫の三味線を彈くことになりましたが、大隅さんから、「此處のところは團平さんはかう彈かれたから、かう彈いて呉れ。」とよく注文が出たさうですが、それがどうしてもそのとほりには彈けなかつたさうです。そんなことがあるたびに師匠は、團平さんに及び難いことを喞つてゐられました。
しかし師匠はこの稻荷座時代にウンと技倆を磨かれたのであります。後に大隅さんの文樂座入りに隨いて文樂へ復歸されましたが、その時の大隅さんの土産が「壺坂」でありました。
團平さんの節付せられた作の數は皆でどの位あるのか私は知りませんが、隨分と澤山ありますやうです。「三十三所花の山」の「壺坂」は有名でありますが、そのほか「良辨杉の段」「櫻の宮物狂ひの段」それから「彌陀本願三信記」の「日野左衞門屋敷の段」「嫁おどしの段」「日蓮記」の「法論石の段」「鳴響安宅新關」--こゝらの作はわりに彈かして貰ふことが多いのですが、節付のつけかたを味ひながら彈いてみますと、どうしてこんな手がついたものだらうと感心する處が澤山にあります。まア一ぺんこれを聽いてみなされ。
(かう云つて話者は、筆者に聽かせるべく三味線をとりあげて、「彌陀本願三信記」の「嫁おどしの段」をしづかに彈き出す……。
〽〽ところも名にし吉崎に、茨しげれる桓原の、木立おぐらき村はづれ、嶮岨坂道藪かげの、沼のかはづの聲々に、、遠寺の鐘ももの凄く、心の闇のくらまぎれ、息もすたすた鬼女の老婆、--(筆者は闇の沼に鳴くギアツ、ギアツ、といふ蛙の聲、ボーンと陰にひゞく遠寺の鐘を耳に聽きました。心の闇のくらまぎれ以下は、鬼氣迫る陰慘の調でありました。)
蛙の聲をきかすところは「ハヅミぶし」といふ手でありますが、それをそこへ持つてゆくと蛙の聲になつてゐます。團平さんの節付は、手の順や、運びに少しも無理がなくて、それでゐて耳になれぬ手が付いてゐるのです。
文樂座の昨年(昭和六年)の四月興行に「日蓮記」が出ました時「法論石の段」を私が彈きましたが、あれなど「虚空にのぼつてとゞまりしは、あやしかりけるしだいなれ」といふ三重の所で、本當に石が虚空でとまるやうに手がついてをります。こんな話をしますといくらでもあります。ともかくも非凡といふほかはありません。私なども時々節付を致しますがとても眞似も出來ません。
話はかはりますが、いつか稻荷座で「鳴響安宅新關」を上演した時、市川宗家から「勸進帳」の版權侵害の訴へが出ましたが、團平さんが法廷で、それが近松巢林子の原作であることを指摘して立派に云ひ開きをされたので事なくすんだと聞いてをります。文樂座ではついこの間も「勸進帳」を上演致しました。
團平さんは旅興行の時など、徹宵盃をはなさず、弟子達に藝談をされることがあつたさうです。團平さんは大して飲ける口でなくて、二合の酒が二時間も三時間もあるといふ嘗めるやうな飲み方なので、そんな時には、そのチビリチビリが隨分と長いのに皆惱まされるのださうですが、團平さんの貴い藝道の金言を聽くのに、それは大切な機會であつたといふことです。
私はさきにも申しましたやうに、團平さんに直接お目にかゝつたことはありませんでしたが、後に三代目團平さんに敎へていたゞいたことがありますので、いろいろ團平さんのお話は伺ひました。團平さんは斯道の神様といふべきお方と思つてをります。
【 團平さんの略歷
團平さんは三世豐澤廣助さんの門人で、はじめ豐澤力松と名乘り、天保十三年正月豐澤丑之助となり、弘化元年二世豐澤團平となられたのであります。普通には團平さんを初代と申し上げますが、名跡から申せば二代目であります。文政十一年播州加古川にお生れになりました。本名、加古仁兵衞さん。通名を淸水町さんと申し上げます。】
私の十二歳の時でした。その頃中の島の常安橋の北詰に長州屋敷の跡が殘つてゐて、そのなかに席があつて、そこでよく素人の淨るりの會がありました。露路のやうになつた突當りが席で、會のあるときは露路の兩側に提灯をつりならべて景氣をつけてゐました。ある時やはりそこに會があつて、鶴澤森助さんが誰かの三味線を彈きにゆかれるのにつれられて聽きにゆきました。
森助さんは當時は退いてゐられましたが、稻荷座の方のお人で、後に松谷と名乘られました。私は十歳の時から森助さんのところへ稽古に通うてをりました。
忘れもしませんが、その會で先代の貴鳳さん(當時の大阪の素義界の重鎭)の先代萩の御殿を、淸六師匠が彈いてゐられました。これが始めての師匠との出會ひであつたのでした。
師匠はその時はまだ三代目鶴澤鶴太郎と云ひました。その後三代目鶴澤叶になられ、それから三代目鶴澤淸六を繼がれたのであります。
私は子供心に師匠の三味線を聽いて、「こんなにうまい人があるのか」と本當に吃驚しました。そして同じ修業をするならこんな師匠に習ひたいと思ひました。
その晩、家へ歸つて父に「あの人に習ふのでなければ、もう稽古はやめる」と云つて駄々をこねました。森助さんとは盃のとりかはしもせず、弟子といふのではありませんでしたが、森助さんは稻荷座の派、師匠は文樂座の派であつたりしたところから、森助さんが私を手離したがられないので、これには父もちよつと困られたやうですが結局私の眞劒な願ひが容れられて、淸六師匠が私の姉の豐竹小時の師匠六代目豐竹時太夫さんの合三味線であつた緣故から時太夫さんの肝入で正式に淸六--當時鶴太郎師匠に弟子入りすることになりました。明治二十三年四月の事であります。
私の師匠のお師匠さんは、はじめ初代鶴澤鶴五郎と名乘り、それから二代目鶴澤鶴太郎になられたお人ですが、生家が北新地の蜆橋のつき當りにあつた豆腐屋さんだつたので、豆腐屋の鶴太郎と呼ばれ、また色の黑いお人だつたので黑鶴さんといふ緯名でとほつてゐたお人でした。
中々の硬骨漢で、住友の廣瀬さんが大變ひいきにしてゐられましたが、はじめて廣瀬さんから稽古にきて呉れといふ話があつた時、「旦那で稽古にゆくのやつたらいやゝ、師匠と弟子で稽古するのやつたらいく--」と云はれたさうですが、廣瀬さんもそれで結構だからといふので稽古にゆかれることになりました。それで稽古の時はいつも鶴太郎さんが上座にすわつて、きびしい稽古をせられたさうです。稽古がすむと、いつもの間柄に戾つて下座へまはつて、「しかし暑おましたなア--」といつた工合だつたさうです。
ある時廣瀬さんが鶴太郎さんに、「うちへ抱へてあげるから文樂を退いたらどうか。」と云はれたさうですが、鶴太郎さんは「まことに有難いお言葉ですがうちの福太郎(淸六の當時の名)を一人前に仕立てゝやるまでは文樂を退くわけにゆきませんので--」と云つてことわられたさうです。
その後師匠(淸六)が病氣になつたのを、日夜介抱してゐられるうちに、自分も同じ病氣になられて、師匠はなほりましたが、鶴太郎さんはとうとうそれで亡くなられました。師匠にとつて鶴太郎さんは、藝と命の恩人であつたのであります。本名を田中卯三郎さんと申されます。亡くなられた時鶴太郎さんは二十九歳でした。廣瀬さんは晩年まで、黑鶴さんの義俠を讃めてゐられました。
黑鶴さんが亡くなられたので、師匠は三代目鶴太郎を繼いで後目を相續され、黑鶴さんのお母さんに養母として仕へられたのでありますが、私が師匠に入門したのはその時代であります。
その頃は御靈の文樂座は、朝の七時にはじまつて、夕方の七時に閉場(はね)ました。三番叟がすむとすぐ大序ですから、それに遲れぬやうに私は大序を彈きに出勤しなければなりません。それがすんだらすぐ歸らないと、師匠の家へ歸るのが八時より遲れると「何をしてゐたのか。」とお年寄りに叱られました。それから雑用をして、師匠の出番の時間がくると、師匠のお供をしてまた文樂へまゐります。晩には師匠の家へ見える連中さんに師匠が稽古せられるのを、次の間で聽いて稽古本に三味線の朱を入れるのです。それが私たちの稽古であつたのでした。ところが生憎く、師匠は寝坊をせられるからいいのですが、こつちは朝早くから一日中、いそがしくしてゐるので、やつと落つくその時刻になると、眠たくて眠たくて弱りました。叱られると思ふので氣を張つてゐるのですが、師匠の稽古をじつと聽いてゐるうちに、ツイいつの間にかふらふら居眠りを始めるのです。さうするとお年寄りが横から、火箸のさきを、チョイと手や腕にあてて、「これツ。」とたしなめられるので、ハツとしてまたお稽古を聽く--それをまたしてもくり返してをりました。
しかし厳格なお方ではありましたが、情合のあるお方でした。「藝は苦しんで稽古するので、おぼえるので、らくをして稽古した藝は身につかぬ。」と云つていつも諭してくれられました。私には陰になり日なたになつて目をかけて戴きました。私が四代目鶴太郎を繼ぐことができましたのは、當時このお方の庇護にあづかつたお蔭でありました。今東京にゐる鶴澤紋左衞門さんはその頃の相弟子で、卯三郎といひました。(つゞく)
この間亡くなられた三代目の越路さんは艶聞の多いお方でした。實際、舞臺の前であの二の音の冴えた、意氣な聲で、惹き入れられるやうな巧い淨るりを聽いてゐたら女(をなご)さんが惚れるのは無理はないと思ひます。私どもでも越路さんの出番の時に、何か用意があつて舞臺裏までゆくとつい聽きとれて立ちどまつてしまふといふやうなわけで、越路さんの出番の時は舞臺裏の聽き手が多勢ありました。
こんな話を聞いてをります。越路さんがまださの太夫時代に土居道夫さんのところへお稽古にいつてゐられましたが、或る日、越路さんは前夜情人のところでひどく睡眠不足して眠たいのを我慢してお稽古にゆかれたらしいのです。その時は土居さんは「太功記」の妙心寺を習つてゐられたのでした。ところが稽古がはじまると、越路さんは「信長記」の金閣寺を語り出すのです。面喰つた土居さんがそつと顔をあげて見ると、越路さんの眼があいてない。さてはと思はれたが土居さんもわざと素知らぬ顔で聽いてゐられると、半睡半醒の越路さんは、眼をあかないまゝで妙心寺をしまひまで一絲亂れず語りをはりました。まだ氣のつかぬ越路さんが「もう一ぺんやりまよか」と云ふのを、「いやもうえゝ、いんで早よう寝。」と云つて歸へされましたが、土居さんは少からず越路さんの藝のたしかさに感じ入つて、早速越路さんのお師匠さんの攝津大掾さん(當時二代越路)に、「あんたの弟子に偉い奴がゐる。あ【さ】の太夫はあんたの後繼になれる」云つて、この話をして讃められたさうです。
大掾さんが「太夫ともあらうものが、語りものを間違へるといふことがあるものか。」と、呼びよせて叱ると云はれるのを、土居さんはとめられたといふことです。
私が故人南部太夫さんを彈いてゐる時のこと--當時私は四代目鶴澤鶴太郎と申しました。ある日南部さんと二人で、次興行の出し物を聽いて貰ひに攝津大掾さんのお宅へまゐりました。いつも南部さんと二人で稽古をしておいて、大掾さんに聽いて貰ひにゆくのです。大掾さんは餘り朝のお早い方ではないのでその日も午前九時頃にゆきましたところが、お家さんのお高さんが出てこられて、「お師匠さんは今お稽古中やから、まアあがつてそこで待つてゐなされ」と仰つしやるので、「どなたのお稽古ですか。土居の旦那はんですか、田中(太七郎)の旦那はんですか」と私がたづねましたら、「いゝや、さうやない。お師匠さんは今勉强中や」と仰つしやるのです。不思議に思ひましたので、私はひとりで、そつとお師匠さんのお部屋を覗いて見ましたら、大掾さんはおひとりで、その時文樂に出てゐる大掾さんの語り物「本朝二十四孝」四段目をおさらへしてゐられました。そしていろ/\と工夫をお考へ中のやうな御様子でした。思ひがけぬことでしたので私は吃驚してお家さんに、「お師匠さんの二十四孝の四段目は評判の二枚札の語り物やおまへんか、それを毎日々々おさらへとはこれは驚き入りました。」と申しましたら、お家さんは「太夫はもとより三味線彈きも同じこと、文樂座へ出てゐても、舞臺だけで本を見るやうな太夫に藝道の出來るものはゐません。三味線彈きも芝居へゆくまでに、内でさらへてさらへて鍛錬練してこそ人の耳を惹きつけることが出來るのや、お前さんがたのやうに芝居だけで本を見るやうな心がけでは中々名人にはなれぬ。--」と諄々と二人に諭してくれられました。
お師匠さんの淨るりは一度聽いたらまた聽きたくなる--なるほどそれも尤なことと思ひました。名人の藝にはこれほどの隱れた苦心があつたのだと覺りました。(御靈文樂座では立見は札一枚、大掾さんの場は二枚札、つまり倍額でありました。)
ある時また南部さんと二人で、「刈萱」の高野山の段を聽いて貰ひに大掾さんのお宅へ參つたことがありました。
高野山のまくらのところ、
〽おりつ、のぼりつ、[合]チリガンチーン、ゆく先を、--
こゝは「アミド」といふ節でありますが、この合の手のチリガンチーンのチーンは、三上の次の「小ワリ」といふところから一番下へすり下げるのです。そのすり下がるところで、私が彈くと、チーンのンへ下るあひだのすり下りに音が消えてゐます。ところが大掾さんが彈かれると、そのすり下りに音がきこえるのです。大掾さんは何十年の間太夫修業ばかりで三味線を彈かれないのに、偉いものやなアとつくづく感心致しました。今にそこのところを彈くたびに、「こゝであつたな。」とその時のことを思ひ出します。
攝津大掾さんは、若年の頃は三味線を修業してゐられたのであります。二十二歳の時(安政五年)五代目竹本春太夫さんの弟子となられて竹本南部太夫と申されるまでは、その時春太夫さんを彈いてゐらた名人三代目野澤吉兵衞さんの門人でありました。その前には三代目鶴澤淸七さんに入門してゐられたこともあります。その時分から三味線修業のかたはら淨るりの稽古もしてゐられて、天性美音でありましたので、三味線よりも却つて淨るりの方が一枚上のやうに云はれなされたといふことであります。
春太夫さんに大掾さんを引合せたのは吉兵衞さんで、それは吉兵衞さんが別に一座を組織して地方興行にゆかれるのに、大掾さんの淨るりの語り口の非凡なのに眼をつけられて、太夫に仕立てゝ一座の花形にしたいと思はれて春太夫さんに賴みこまれたのであります。大掾さんはそれまで龜次郎さんと申されました。
大掾さんは幼名を吉太郎と申され、生家は大阪順慶町三丁目塗物問屋、姓は森と申されましたが、わけあつて父の家をつがれませんでした。養家の姓は二見、名を龜次郎と改められました。【後には金助と申されました。】養父は大工の棟梁さんでありましたが、素人淨るりの大天狗であつたといふことであります。これが大掾さんが淨るり界に足をふみ入れられる機緣となつて、十一歳の時から三味線の稽古をせられました。最初の師匠は竹澤龍之助といふ人、それから鶴澤淸七さんに就かれたのであります。
大掾さんは吉兵衞さんにつれられて近畿、中國、四國と凡そ二年ほど巡業せられましたが、その間吉兵衞さんの懇篤な薫陶を享けられて見臺の功を積まれたのであります。それからまた萬延元年--大掾さんの二十五歳の時--に江戸興行にゆかれました。この江戸興行で御苦勞なされたお話は私も直き/\大掾さんから承つてをります。
その時の一行は野澤吉兵衞さん、竹本其太夫さん、野澤勝鳳さんなどで、大掾さんの南部太夫を眞打にして、吉兵衞さんが自身でその三味線を彈かれることになつてをりました。大掾さんが、「それでは名譽ではありますが、提灯と釣鐘で、今度は田舎とちがひまして江戸のことゆゑ、私には荷が勝ちすぎます」と云はれましたが、吉兵衞さんは、「釋尊も難行苦行して、はじめて佛になられたのであるから、天下の名人にならうと思ふには、それぐらゐの修業は何でもない。」と申されて、大掾さんの辭退を聞入れられませんので、大掾さんも決心を固めて江戸へ上られたのでありました。
初代竹本越路太夫は野澤吉兵衞さんの實父で、恰度その年は十三囘忌にあたつてゐたのと、越路太夫といふ名が江戸にお馴染のある名であつたので、新下りの南部太夫に人氣をつけたいのとで、吉兵衞さんは江戸から手紙をもつて春太夫さんの許しを得られて、大掾さんに二代目竹本越路太夫を繼がせられたのであります。大掾さんは、六代目春太夫になられるまで、實に四十餘年この名を名乘つておいでになりました。
その時の江戸興行は、文樂座とちがひまして、素淨るりで寄席を勤められるのでありました。そして出し物は毎晩替りなので骨の折れることは一とほりではありません。それにその頃は、當今と違つて淨るりを聽く人が澤山ありまして、見物の耳が肥えてゐて仲々氣が張つたさうです。大掾さんの一番困られたのは、毎晩寄席で翌晩の語り物を宵觸れする時に、吉兵衞さんは大掾さんのかいもく知らぬ語り物を、少しも大掾さんに相談せずに觸れさしてしまはれるのです。そんな時は寄席をしまうて歸つてから、翌晩の語り物を吉兵衞さんが大掾さんに稽古せられるのです。吉兵衞さんは稽古をすましてそこ/\にやすんでしまはれる。が大掾さんは、どうでもかうでも朝までに會得しておかなければ翌晩の間に合ひません。そのために徹夜は殆ど毎晩であつたさうです。さすがの大掾さんもこれには弱られました。「今日かぎりやめてしまはうか、いつそ死んでしまはうか、といく度考へたか知れぬ。」と、後年その時のことを大掾さんは仰つておいででした。
ある時大掾さんが弱り果てゝおいでになると、吉兵衞さんが、「それほど大儀であるなら是非ないことであるから、やめたがよい。今晩高座で、今晩の出し物は私は存じませぬとお客にあやまつたらどうだ。」と云はれました。そんなことが出來るわけのものではありませんし、大掾さんはつらいのをこらへて稽古をはげまれたといふことであります。
大掾さんは、まことに穏やかな、品位のあるそして温い感じのお方でした。お師匠さんの前へ參りますと、何となく嬉しい氣持がいたしました。さういふ方でしたから敵といふものは一人もありませんでした。
竹本南部太夫から、二世竹本越路太夫になられ、【萬延元年】それから六代目竹本春太夫になられて【明治三十六年一月】竹本攝津大掾になられたのでありますが、【明治三十六年五月小松宮家より拜領】二世越路太夫を四十何年も長く名乘つておいでになつたのも、三代目野澤吉兵衞さんの師恩に報ずるお心であつたやうに承つてをります。
【大正二年四月に引退なさいました。御靈文樂座の引退興行の語り物は「楠昔噺」三味線は六代豐澤廣助さん(後に名庭絃阿彌)でありました。大正六年十月九日午後四時半、東須磨の別宅でお亡くなりになりました。行年八十八歳。法名春暁院殿越峰翁居士。墓所は天滿の寺町寶珠院と、別に一基高野山にあります。】
大掾さんのやうな愼みのあるお方にも、一度こんな失敗がありました。鰻は音聲の大敵で、芝居出勤中は太夫は嗜まないゐであります。それをどうしたものか、或る日灘萬の女將お德さんがうつかりお師匠さんに鰻をすゝめて食べさしたのです。さアそれが覿面に崇つて、その晩大掾さんは舞臺に出演中、途中で聲がとまつて出なくなりまして、南部さんが替りを勤められるといふ始末です。きまりがわるかつたと見えて大掾さんもお宅へ歸つても默つてゐられましたが、あとでお家さんの耳にはひつて矢釜しく詮議せられるので、大掾さんもたうとう事の次第を白狀せられたのでした。
大掾さんが東須磨の別荘においでの頃、大掾さんの斡旋で、神戸の川崎さんの御母堂の喜の祝に、叶太夫さんと一つしよに呼ばれて參つたことがありました。その時「堀川」の猿廻しを二人で勤めました。大掾さんのお家さんのお高さんも聽いてゐられましたが、あとで私に、「あんたはえらいものを知つてゐる。今あんたの彈いたのは三代目の吉兵衞さんの手や。この頃は皆が淸水町(團平)の手ばかり彈いて、野澤の手を彈くものがない。」と云はれました。それは與次郎が猿を廻すときの、二上りの彈き出しの手--お猿はめでたや、めでたやなア、の合の手であります。淸水町の手のほかに松葉屋さんの手もあります。これは今の友治郎さんが彈かれます。私は五代目の吉兵衞さんから野澤の手を敎へていただいたのであります。私はお家さんの見識に驚きました。
お家さんは大掾さんと永年御一しよに苦勞をなされただけに、藝道のこともよく御存知であつたのでした。
お家さんは大掾さんが御勉强のために徹夜なさつたりする時は、御自分も針仕事などなさつて起きておいでになつたといふことであります。
その頃の見物の方は、ことに女(をなご)さんたちは、「大掾はんの淨るりは情があるけれど、大隅さんの淨るりはすげない。」とよく申されました。實際、大掾さんは天性美音でありましたし、技巧の妙をつくすとでも申しませうか、さう云つた語り口でありました。三代大隅さんは今の言葉で申しましたら、テンポの早い語り口でした。しかし、さすがに名人團平さんに鍛へぬかれて、「凝り固まり」と云はれるお方だけに、きまりきまりの實にきつちりした語り口で、聲も美聲とはいへませんでしたが、その早い語り口に何とも云へぬ情がありました。
私どもは節を覺えるために舞臺裏で聽いて朱を入れるのですが、大隅さんの淨るりは、きまりがきつちりしてゐるので、十日ほど聽いてゐるとほぼ覺えられました。ところが大掾さんの淨るりは、ものゝ二十日も聽いて少し覺えられたやうに思つて、その翌晩聽いて見ると、たしかにかうだつたがと思ふところが、また違ふ。朱を入れ替へておいて、次に聽くと、またどうも違ふやうに思はれる。ながく聽いてゐるとわからなくなるのでした。色々と工夫もされたのでありますが、天分の豐かなお方であつたのだと存じます。
文樂座へ大隅さんが淸六師匠を連れて這入られた時でした。「壺坂」の段切のツレを私(當時鶴太郎)が彈きましたが、或る日大隅さんが私に、「奥田、お前は三味線を彈いてゐるのか、かいもく音がしてへんやないか、田中(師匠)の三味線はカンを彈いてるやうなもんや、俺はお前の三味線で語つてゐるのやぜ。」とお叱言を云はれました。大隅さんは磊落な、氣性のさつぱりしたお方で、かまはずものを云はれるお方でした。
私も口惜しかつたので、その晩から「なに糞ツ」と意氣込んで力一ぱい彈くのですが、なにしろ師匠の絲の音が大きいので、私の三味線がみな消されてしまつて、自分にもかいもく自分の絃の音が聞えませんでした。
これは私が叶になつてからの話ですが、六代目廣助さん後に名庭絃阿彌に「日向島」を稽古していただいて、前彈きで虐められたことがありました。虐められたと申すと語弊がありますが、その時は全くそんな氣がいたしました。「日向島」の前彈きは、
チンチントツツン、トツツン、トツツン、トツツン、トツツン、ツンツンツンツン、ツツン、ボトテン、
ウタヒ、松門獨りとぢて年月をおくり、みづから淸光を見ざれども--
となる、たつたこれだけの手なのです。
廣助さんのお宅へは毎朝六時頃にお伺ひしないといけないのでした。八時頃まで待つて、やうやくお稽古にかゝります。
はツ、チンチントツツン、トツツン
と私が彈きます。廣助さんは聽いてゐられて、「いかん。」と云はれるだけで、何もほかのことは云はれません。仕方がないからそのまゝ歸ります。翌る日もまた「いかん。」と云はれて歸るのです。その翌る日も、翌る日も同じことなのです。毎朝早く起きてゆくのは辛らかつたのですが、これが修業と思うて心をとりなほしてゆきました。
恰度十四日目でした。いくら何でも私は腹が立つてきました。「お師匠はんもあんまり意地がわるい。いかんならいかんで、どこがいかんと云ふてくれはつてもよささうなもんや。今日もいかんと云やはつたら、この撥でお師匠はんを撲つてやろ。」と決心して出かけました。稽古にかゝつても「どうでもえゝわい」といふ氣持でしたから掛聲もせずに、
チンチントツツン、トツツン--
と素つ氣なく彈いてのけました。ところが意外にも廣助さんは「出來た。出來た。それでえゝのやがな。」と云はれるのです。そして「この間うちのは景が彈けてなかつた。」とはじめて云はれました。
なるほど、花やかに、はツ、チンチントツツンではいけないのでした。盲目の景淸が海邊にたゝずんでゐる侘しい景が現はれなければいけないのでした。不平滿々の氣分が、はからず「日向島」の前彈きを及第させてくれたのであります。(續く)
淨るりの三味線は、兒島屋文藏さん(初代鶴澤文藏)の時代までは唄の三味線と同じやうに、胴の皮の切り口をほそく切つてゐたのを、今日のやうに山形に廣く切るやうになつたのは文藏さんの好みであると申します。
何でも芝居の役前に三味線の皮を張り替へさしたのが時間が間に合はぬので、急いで山形に廣く切らせたのが始まりだと聞いてをります。今日でも文藏張りと申してをります。
このお人は後に二世鶴澤友治郎になられましたが、名人の聞え高いお人であります。寶曆から、天明頃までの番附に載つてをります。「妹脊山婦庭訓」「おはつ德兵衞、敎興寺の段」は文藏さんの手附けであります。ほかにも手附けなされたものは澤山にございます。
三味線はむねにはひきて手にひくな
ひけよひくなよこゝろすなほに
これは文藏さんの有名な歌であります。
三味線の朱章を初めて工夫されたのは初代鶴澤淸七さんと申すお人で、幼名を淸治郎、天明四年に淸七に改名されました。通名を松屋淸七さんと申されます。初代鶴澤文藏さんの門人で、文化八九年頃まで勤めてゐられます。後に三世鶴澤友治郎になられました。
明治四十三年の九月のこと、文樂座で「關取千兩幟」が出まして、櫓太鼓の三味線を淸六師匠、ツレを私(當時鶴太郎)が勤めた時の話であります。
その時の太夫さんは掛合で、猪名川が七五三太夫さん、鐵ケ嶽が津太夫さん、おとわが古靱太夫さん、北野屋が常子太夫さん(今の文字太夫)、大阪屋が越見太夫さん(今の町太夫)でした。櫓太鼓の三味線のツレも番附では私(鶴太郎)と、野澤吉松さんと、鶴澤大三郎さん(後に鶴澤才治)と三人で三日目替りに勤めることになつてありました。
大三郎さんは太鼓の三味線が上手で、殊に曲彈きが得意であつたのですが、この年は大變にコレラの流行つた年で、運わるく大三郎さんは交通遮斷を喰つて、初日から三日勤めたきり、芝居へ出勤できなくなつて仕舞ひました。吉松さんは、とても太鼓はかなはんというて途中で逃げてしまつたので、ツレはたうとう私ひとりになりました。
この太鼓の三味線は、鶴澤兵吉さんといふお人が櫓太鼓の名人だつたので、淸六師匠も私もこのお人に習つたのでありますが、師匠には本手の三味線を、私にはカン太鼓を入れる曲彈きを敎へてくれられました。--鶴澤兵吉さんは竹本山城掾を彈いてゐられたお人です。
さて毎晩師匠と二人で太鼓の三味線を勤めるのでしたが、師匠は三味線で太鼓を彈かれてさきへ這入つて仕舞はれる、あとへ私が殘つて曲彈きを勤めるのでした。師匠の三味線はまことに鮮やかなもので、曲彈きをせずに見事に太鼓を聽かされました。毎晩見物から「淸六さん、淸六さん。」と聲がかゝるといふ大當りでした。
ところが、私をひいきにして下さる永藤呂篤さんといふお方--今もつて御ひいきにして戴いてをりますが、このお方が聽きに見えて、私に「鶴太郎はん、ありやアいかん。淸六さんの上手な三味線のあとへ、あんたが殘つたんでは、あんたの三味線が聽かれへん。大體、顔の上の者があとへ殘るのが本當や。淸六さんに賴んで、あんたさきにやらしてもらひなはれ。」と云はれるのです。早速師匠にこの話をして賴んでみましたが、「そんなわけにゆかん。」と云はれるので、その通り呂篤さんに話しましたら、呂篤さんは「そんなら師匠と同じ手のところをぬいて貰ひなはれ。」と云はれました。師匠も私も同じ手を彈くのは、打込みと打出しの手で、それを師匠にぬいて貰へば見物に比較されるところがなくなるからでありました。それでまた師匠にそれを賴んだのですが、師匠は「きまりの手やから、ぬくわけにはゆかん」と云はれて、どうしでも應じて呉れられません。
呂篤さんは「あんたとこの師匠はわからん人や。それではまるで弟子に恥かゝしてゐるやうなもんや。」といつて憤慨されます。私もさう云はれると、だんだん師匠を恨めしく思ふ氣持が嵩じてくるのでした。呂篤さんは私のひいきに毎日聽きにこられます。お目にかゝるとその話が出ます。堪まりかねて或晩師匠に、「皆が聽いてゐられへんと云やはりますので、どないかして貰へまへんやろか。」ともう一度賴んでみました。ところが相變らず師匠は「でけん。」と云つて刎ねつけられました。「どないしても、でけまへんか。」「でけんものはでけんツ。」私も思はずカツとなつて、「そんならもうよろしおます。私はもうやめます。」さういつて弟子に三味線箱を持たせて部屋を出ました。
私の歸りかける姿を見て勘定場の淸水さんが走つてこられて、「あんた、そんなことして明日からどないするつもりや。」と云はれるので、「もう一生、三味線彈きはやめる決心です。」と申しましたら、「そんなこと云はんと、まア私にあづけとくなはれ、私がよいやうに計らひますさかい。」と云はれます。居合せた野澤文平さんも「淸六さんもあんまり殺生や」と云つて私に同情してくれます。そこへ時太夫さん(七代目)も出てきてなだめてくれられるので、ともかく淸水さんに預けることにしました。その時の次狂言が「近江源氏先陣館」でして、和田兵衞上使の段を時太夫さんが勤められて、私が彈いてをりました。「千兩幟」は切狂言でありました。
その晩「太鼓」の舞臺へ、師匠と私と無言で並びました。私は「何ぢやい。もう師匠でも弟子でもないのや。」といふ氣持でした。師匠はいつものとほり彈きをはつてから、何と思はれてか「おい、はいつてもえゝか。」と小聲で私にたづねられました。私はまだ氣が立つてゐるので、向ツ腹で「はいりなはれツ。」と云つて、もうなんにもこはいものはないといふ意氣込みで曲彈きを勤めました。
すんでから呂篤さんにその話をしましたら「さやうか、しかし今日はよう出來た。あの位彈けたら聽いてゐられる。」と云はれました。家へ歸つて寝床へ這入る時分には、宵の興奮もだんだん靜まつてきて、色々と考へられてまゐります。今夜舞臺で「はいつてもえゝか。」といはれた、いつにない師匠の言葉も思ひ出されてきます。師匠は私の藝を恥ぢしめて、鞭撻してくれられたのだと思ふと、「えらいことを師匠に云ふた。」と心から後悔されてきました。
翌る日師匠の前へ手をつかへて、「きのふは無茶云ひましてすみまへなんだ。どうぞ勘忍しとくなはれ。」と云つて謝まりましたら、師匠は「わしは何とも思うてへん。」と云うてくれられました。私は涙が出て出てとまりませんでした。
後々まで師匠は「あの時おまへはこはかつたなア。」とよく云はれました。その時仲へはいつて下さつた淸水さんといふお人は、仲々藝道のことのよくわかるお人でしたが、惜しいことにはこの時のコレラで亡くなられました。
同じ興行の時でした。師匠と喧嘩する前、さきに申したやうに師匠がいつも大當りで這入られるあとを勤めるのですから、何でも私も人氣を取らうと思つて、曲彈きをするのに、大根で彈いたり、御幣で彈いたり、みかんで彈いたりしてみました。彈いてからそれを見物席へ投げるのです。
そんなことをしてゐましたら、たうとう大掾さんに呼びつけられて、「文樂座は寄席ではない、檜舞臺ですぞ。そんなことをしてくれると、わしの顔にかゝはるからやめてくれ。」と云つて叱られました。
明治三十七年の一月、文樂座の中狂言に「白石噺」の新吉原揚屋の段が出まして、攝津大掾さんが勤められることになつてゐましたが、大掾さんが御病氣のため、三代目越路太夫さんが替りを勤められました。三味線は五代目野澤吉兵衞さんでした。ある日大隅さんが床内へこられて、越路さんの宗六のいけんを聽かれて「あゝまだ弟子は弟子だけや、語れんなア」と云はれたのを、常子太夫さん(今の文字太夫)が聞いて、師匠のことですからひどく憤慨して、すぐに越路さんのお宅へかけつけて右の話をされましたら、越路さんは「大隅さんがさう云はれたか、わしはまだ語れん。」と言はれたさうであります。
いつの頃でしたか、誰を彈いてゐましたか記憶いたしませんが、私らの方が口、越路さんの方が奥を、次興行に受持つことになつてゐました。初日が近づいたある日、越路さんに逢ひましたので、私が「貴田さん(越路太夫の本名)あなたの方はもうお稽古がすみましたか。」とおたづねしたら、「まだや。お前さんとこはもうすんだんか。わしの方はお前とこの太夫のやうに、テンと彈いてテンで出るのと違ふのやさかいなア。」と云はれました。これは越路さんの云はれるとほりで、三味線がテンと彈いても、音はテンから出ぬのが淨るりを語る祕訣であります。
五代目野澤吉兵衞さん--このお方は私には忘れられぬお方であります。鶴太郎時代から私を隨分可愛がつて下さいました。
四代目吉兵衞さんの門人で、攝津大掾さんの三味線を、越路時代、春太夫時代から、大椽さんになられてからもまだしばらく彈いておいでになりました。本名を鈴木繁造さんと申し上げます。
まことに淡白な、面白いお方でした。
北の新地の平鹿樓の御主人--俳名を紅雀さんと申される方が御ひいきで、吉兵衞さんがお稽古にいつてゐられました。今の平鹿の御主人は紅雀さんの弟さんで、俳名を柳平さんと云はれます。私も以前から紅雀さんに御ひいきになつて合三味線にしていたゞいてをりました。紅雀さんは、お駒才三の城木屋が十八番で、よく出ましたが、私には、さわりの投げぶしのところの模様がどうもうまく彈けないのでした。その頃私は三段目ものが好きで、世話ものは不得手でした。吉兵衞さんにいつも「お前のは、かたくなり過ぎて色氣のないのがいかんのや、娘のこゝろで彈かないかん。」と云はれてをりました。
ある時、堀江の橘通りの太神宮さんの敎會所でお素人さんの淨るり大會がありまして、私が紅雀さんの、やつぱり「城木屋」を彈くことになつてありました。吉兵衞さんは「今夜はわしが聽いててやる。」と云はれて、その晩お見えになりました。
床へ上つて見ましたら吉兵衞さんは見物席のまん前に坐つておいでになりましたが、いよ/\例の「投げぶし」のところへきますと、吉兵衞さんは突然大聲で「ちがふ、ちがふ、そりやいかん。」と云はれるので、私はすつかりどぎまぎしてしまひました。それでもどうにか、しまひまで彈いて樂屋へ歸つてから、「お師匠はん、あれは殺生だつせ。」と苦笑しながら云ひましたら、吉兵衞さんは「えらいわるかつた。云ふつもりやなかつたんやが、思はず出たんや。」と仰つてゞした。
そして「娘の心といふものがわからないかん。お前は一ぺん素人の娘さんと情事をしてこんとあかん」と云はれるのです。
その時の話だつたか、それから後の話だつたか、吉兵衞さんは私に、「お前に世話物の三味線が彈けるやうにしてやるさかい、わしの云ふとほりするか。」と云はれるので、どんなことをするのかおたづねしますと、「新町の黑あんどへいつて、これこれのものを買ふといで--」と云はれるのです。(黑あんどは閨房の藥や用具を賣る店)若い私がきまりわるがるのが吉兵衞さんには面白いらしいのです。私が「お師匠はん、それだけは堪忍しとくなはれ、ほかのことやつたら何んでもしますさかい。」と云つても、「それをせんのやつたら、もう敎へたれへん。」と云はれるのです。仕方がないので思ひ切つて俥に乘つて、云はれた品を買ひに出かけました。黑あんどの前で俥をおりて、ソツとあとさきを見まはしますと、吉兵衞さんも俥で私のあとを尾けてこられたと見えて、新町橋の上から様子を窺つてゐられるのです。やつとの思ひで買物をすまして出てきますと、「えらい、えらい、その位の勇氣がないと修業はでけへん。」と云はれて大變に御機嫌がよいのでした。
その時分のことでした。私の連中さんの順會がお素人の家で催されました。場所は北區の伊勢町を老松町北へはいつた、紺染物をなさるお宅でした。
「もたれ」は相生さん--後に藍玉さんと申されて、六七年前神戸で亡くなられました。その時の出しものは「四谷怪談」の伊右衞門住家でありました。「どつさり」は紅雀さんで、出し物は「お夏淸十郎」湊町の段、三味線は吉兵衞さんでした。「もたれ」までは私が彈きました。(どつさりは一番最後の出演、もたれはその一つ前)
何しろ素人家のことでありますし、そこへ床を高くこしらへたものですから、天井が低くつて、三味線の音がこもらないので彈き憎くゝて困りました。「もたれ」をすまして樂屋へはいつて私は吉兵衞さんに「天井が低うて、かいもく三味線がこもりまへん。」とこぼしてをりました。
すぐに床へ上られた吉兵衞さんは、湊町の前彈きを彈かれながら、樂屋の私の方を向いて、「おい、何を云ふてんね。よう鳴るやないか。お前の手が鳴れへんねやがな。」と大きな聲で仰つしやるのです。實際ビン/\と、とてもいゝ音がしてゐるのです。これを聞いて見物の方々は「えらい違ひやなア。」と云つてゐられます。私はすつかり赤面してしまひました。
文樂座へ出勤されても、よく出番の前に風呂へ這入つてゐられるので、皆が「お師匠はん、濡れだつか」と云つて、冷かすと、「何を云ふてんね。私の爪は堅すぎるので、少しやはらかうせんと三味線が鳴り過ぎて困るのや」と云はれました。實際にお師匠さんの三味線はよく鳴りました。針金のやうにキン/\いふ音がしました。
明治四十四年二月二十一日、七十七歳の高齢でお亡くなりになりました。通名を「江戸堀」さんと申しました。吉兵衞さんのことでは思ひ出すことが多いのであります。私には懷かしいお方でございます。
七八つの頃から三味線をいぢりました。父は奥田幸七、伊豫幸といつてその頃は北堀江の御池橋のほとりで骨董屋を營んでをりました。素人でしたが淨るりが好きで、三味線も彈きました。俳號を幸壽と云ひました。そんなわけで私も幼い時分から三味線に親しんでゐたので、見やう見眞似に三味線をいぢることを好むやうになりました。手ほどきは父から享けましたが、太十の夕顔棚だつたと覺えてゐます。
十歳の時父にせがんで御近所だつたので鶴澤森助さんのところへ三味線のお稽古にゆくことになりました。父もその頃は家が逼塞してゐたので、子供に自分の好む藝を仕込んで、藝で身を立てさせようと考へられたのであらうと思ひます。姉も六代目豐竹時太夫さんに弟子入して、當時豐竹小時と申してをりました。
十二藏の時、三代目鶴澤鶴太郎師匠(後三代目鶴澤淸六)に入門いたしました。
師匠に入門した明治二十三年の五月、「五天竺」の怪石の段(大序)で、はじめて出語りの三味線を勤めました。掛合で太夫さんは竹本品尾太夫さん、同津子太夫さん、同つばめ太夫さん(今の古靱太夫)、同氏戸太夫さん、同鶴尾太夫さん(先代南部太夫)、豐竹綾戸太夫さんでありました。これが私の初舞臺で、その時文樂座の座元植村さんの未亡人が大變ほめて下さつて、「しつかり勉强しなはれや」と仰つて三味線の絲の箱にはいつたのを呉れられました。嬉しかつたことを忘れません。
七代目竹本時太夫さんは四年ほど、故人竹本南部太夫さんは鶴尾太夫時代から四五年、故人九代目竹本染太夫さんは一年餘り彈きました。それからこの頃新文樂座建設の運動に奔走してゐられる竹本叶太夫さんは、文樂を出られるまで十三年彈きました。
合三味線はそれぐらゐですが、そのほかに彈きましたのは故人では竹本氏太夫さん、豐竹綾太夫さん、竹本むら太夫さん、竹本七五三太夫さん、竹本路太夫さん、六代目竹本彌太夫さん、替りでは三代目越路さんのさの太夫時代、現存の人では今の津太夫さんは文太夫時代から、古靱さんのつばめ太夫時代、駒太夫さんの富太夫時代、今病氣してゐられる源太夫さんなどです。只今は獨身であります。
それはこはいもので、三味線を彈く人の氣分をすぐ表はします。氣分の沈んでゐる時は明るい調子になりません。色氣など出ません。ふところ具合がわるくて、晦日が苦になつてゐるやうな時は絃の音が冴えません。絃の音をきいて、「あの人、この頃だいぶんセクチイ(つまつてゐる)な。」などと感じさせられることはよくあります。
身持ちも愼しまないと、すぐに三味線に影響します。文樂で廣助さん(六代目)に若手の三味線彈きの連中が稽古をして貰つてゐた頃、「お前ら、かいもく三味線が鳴つてへんやないか。」と、よく皆の不身持を叱られました。
これは太夫さんも同じで、合三味線の太夫さんが前晩に女に會ふてきたりした時は、一しよに舞臺を勤めてゐる三味線彈きにはよくわかります。(終)
▽前号「天才三代越路さん」の下段五行目、妙心寺とあるは金閣寺の誤り。つまり越路さんは妙心寺を語るべきを、しまひまで金閣寺を語つて氣がつかなかつたのであります。
▽それから長らく獨身であつた鶴澤叶は、文樂座のこの三月興行から、島太夫改め三代目竹本呂太夫の合三味線となりました。
私が師匠淸六に弟子入して、はじめて文樂座へ這入つた頃は、人形の方では初代吉田玉造さんと初代桐竹紋十郎さんのお二人が大將株で、幕内では大した御勢力でした。實際に申しましてもこのお二人は、人形遣ひの名人として近世の双璧でありました。そのほか吉田玉治さん、吉田玉助さん、吉田金之助さん、吉田玉五郎さん、吉田龜松さんなどが人氣がありました。
玉造さんのお宅は島の内の御池橋東詰を東へ這入つた北側で、その西隣に「きみづや」といふ莨入屋があつて、そこの主人が淨るり三味線を大變によく彈きまして、玉造さんもしじゆうに遊びに見えてゐました。私の父と「きみづや」さんとは連中友達だつたので父もよく遊びにいつてをりまして、父は玉造さんともお馴染になつてをりました。そんなわけで私は文樂で玉造さんには可愛がつて戴きました。
玉造さんは天保十年十一歳から舞臺に出られ、明治三十七年に七十七歳で亡くなられました。私は、明治二十三年私が御靈文樂座へ這入る以前のことは存じませんが、松島文樂座時代から、玉造さんが文樂座のために盡された功績は非常なものでありまして、攝津大掾さんに劣らぬ文樂座の殊勲者のお一人であつたのであります。本名を吉倉龜吉さんと申し上げます。
玉造さんは、荒事でも、女形でも、道化でも、勝賴、十次郎、櫻丸でも、何でも上手に遣はれました。また動物、殊に狐がお得意でした。まことにそれは入神の技でありました。
玉造さんの狐には、私には忘れられぬ印象が殘つてをります。
明治三十年の五月に「義經千本櫻」が出まして、「鮨屋」は二世越路太夫さん(攝津大掾)でした。私は「道行」で「豆くひ」を勤めてをりました。「豆くひ」と申すのは、ツレ三味線の一番ビリのことであります。
紋十郎さんが靜御前、玉造さんが忠信でした。御存じのとほり「道行」の、
〽谷のうぐひすなア、初音のつゞみ初音のつゞみ [合]しらべあやなす音につれて--
といふ文句のところ、この合には三味線が澤山あります。この間に狐が櫻の根元から出たり、小山の蔭から出たりするのでありますが、玉造さんのは、何處から出られるのか眼にとまりません。舞臺の下手でドロドロドロ--と太皷が鳴つたと思ふと、スツと狐が舞臺に現はれてゐます。「豆くひ」で毎日床に出てゐる私が、「何處から出やはつたんやろ」と思ふ位でした。いつも見物の方が、アツと云はれました。
狐は出てからは少しもヂツとしてゐません。あちこちに目くばりしては、ちよつと走り、またあちこちに目くばりして、さも嬉しさうに靜の皷の音を聽いてゐる姿や、首をひねつて、クルリと廻つてわがうしろを見る仕科や、舞臺のまん中で正面を向いて、くわツと口を開いて、耳を立てゝ眼を剝き、また當り前になつて舞臺の奥へ飛んでゆく仕科など、何とも云へませんでした。今でもハツキリ眼に殘つてをります。それに狐ばかりが眼について、玉造さんの姿はちつとも眼につきません。それは實際のことでありまして、今の御見物にお見せしたいと思ひます。全く偉いものでありました。
狐の出てゐる間、靜は舞臺の上手で、しじう見物にうしろを見せて皷を打つてをります。それがまた紋十郎さんの味噌でもあつたのですが、實によい形でした。紋十郎さんのことは後に申上げます。
それからまたドロドロドロで、櫻の根元へよると見せかけて忠信に早替りですが、その早いこと、肩衣の替るのも、いつ替つたのかわからない位です。
早替りは人形が替ると一しよに人形遣ひの肩衣が替るのですが、その時に人形のかたちが崩れてはいけないのです。これは玉造さんが仰つてゐられました。そして「三味線彈きも同じことや。三味線がよう彈かれても體が崩れては何もならん。」と云ふて聞かされました。
四段目川連法眼館の段でも、四段目の時は下手に舞臺をこしらえて、そこへ小川淺丸さんが皷を箱に入れて持つて出られ、まくらで皷を打つて左手へ置かれます。--その時皷はスリ替へておくのです。--そして
〽彼の洛陽に聞えたる、會稽城門の越の皷、斯くやと思ふ春風に、さそはれ來たる佐藤忠信--
で、狐がその皷を破つて出てくるのですが、狐がさきに首を出します。それが性根が這入つて生きてゐるので、ハツとそれに氣を奪られてゐる間に、皷の箱の中からスウとあの大きな體の玉造さんが出てこられます。それは早いもので、まことに綺麗でありました。話が前後いたしますが、「道行」の靜との踊りも、うまいものでした。
四段目は谷太夫改め九代目染太夫さんでありました。狐から早替りした忠信が、靜に皷でさんざんに打擲され、
〽さあ白狀、さあ白狀、さあさあさあと詰寄られ、一句一答詞なく、只ひれ伏して居たりしが、漸に頭をもたげ、初音の皷手に取上げ、さもうやうやしく押戴き押戴き、靜の前に直しおき、しづしづ立て廣庭へ、おりる姿もしほしほと、身すぼらしげに手をつかへ--
といふ條で、正面金襖の上の御殿で、狐のこゝろで兩足を揃へて、皷をさゝげて靜の前に直し、また兩足を揃へて、下の庭へ欄干をひよいひよいとおりるシヨンボリとした忠信の姿が、忠信のままで狐の歩るいてゐる姿になつてゐるのに感心致しました。深い印象を享けました。
こゝのところは三味線にも心があつて彈きにくいところです。
〽しづしづ立て、[合]チンチンチン、テツトン、廣庭へおりる。[合]チンチン、
この合の手が彈けませぬ。人間ならぬ狐のこゝろ、それがむつかしいのです。私も後に(大正二年二月)同じ九代目染太夫さんで四段目を彈きまして苦心いたしました。今もつて自分で滿足のゆくほどに彈けません。
玉造さんのお話にもどりますが、それから親つゞみとの別れのところ、
〽椽の下より延び上り、我親つゞみに打向ひ、かはす詞のしり聲も、涙ながらの暇乞、人間よりは睦まじく、--
この間の、皷に別れともない、切ない氣持を見せる仕科、
〽頭をうなだれ禮をなし、御大將を伏拜み伏拜み座を立つは立ちながら、皷の方をなつかしげに、見かへり見かへり行くとなく、消ゆるともなき春霞、--
で、せん方なく、しほしほと立ち去る忠信のいぢらしい姿は、見てゐるのがつらい位、いつでも私はポロポロ涙がこぼれるのでした。
四段目には前後何べんも早替りがありますが、前申しましたやうに出られるところが眼にとまりませんので、毎日見てをりますのに「今あすこから出やはる。今度はこゝから出やはる。」といふ見當が確かにつきませんでした。名人であつたと思ひます。
やはりまだ私弱年の頃、「本朝二十四孝」が出た時のことでありました。
「奥庭の段」で玉造さんは、さきに狐を遣ふて出られます。この場でも「千本櫻」と同じふり--あちこち見たり、くるりと廻つたり、正面で大きく口を開いて睨む仕科などがありますが、いつ見ても實によいのです。がそのあとで狐が戯れるやうなふりがあります。これは千本の狐とは違ひます。遣ひ方も違ふのであります。
それからトントントンと走つて床の間へゆき、人目がないかといふ風にあちこちに眼をくばつて、諏訪法性の兜の祭つてある床の間の下へ、スツと這入つてしまひます。そしてすぐ下手の庭先から八重垣姫を遣ふて、早替りで玉造さんが出て見えます。それがとても早いのでした。
その時のことでした。或る日玉造さんが、舞臺をおりて樂屋の風呂へゆかれて出てこられるのに出會ひまして、
「お師匠はん、あんたは狐がなんであない上手だんね。ほんまに生きてゐるやうや。」と申しましたら、
「何を云ふのぢや。子供が大人なぶりすな。」
と玉造さんはひどく立腹されました。生意氣な小僧だと思はれたのでありませう。私は生來コマシヤクレてをりまして、何でも突き止めてみませんと氣のすまぬ性分でしたので、「そやおまへんのや。そないおこらんといとくれやす。わてはお師匠はんはきつとほんまの狐がそばえてゐるのを見やはつたのんや思ひます。狐の走るとこを見たお人はゐやはりますやろけど、狐のそばえてゐるのを見た人は滅多におまへんやろ。お師匠はんは見やはつたんや思ひます。」
と申しますと、
「お前、えらいことを云ふなア。俺はこの年になるが、まだ俺に狐のことでそんなこと糺いた者はあらへん。感心や。お前は見込みがある。しつかり勉强しいや。」
といはれて、御機嫌をなほされました。そして「俺が狐で苦心した話を聞かしてやるから、俺の部屋へおいで」と仰しやるので、一しよに三階の玉造さんのお部屋へまゐりました。
玉造さんのお話。--
俺は、どうぞして狐がものに戯れてゐるところが見たいと思つて、伏見のお稻荷さんへ「何卒それを見せて下され。」と願を懸けた。尤も毎月毎月お參りしてをつたが、その驗がなくて六年目も空しく過ぎてしまつた。恰度七年目の暮であつた。寒い時であつた。一の峰のお宮のうしろの裏山で、今と違つて實に淋しい處であつたが、朝早くフト俺は狐を見た。眞白な狐であつた。ハツと思つて思はず手を合して拜んだ。拜みながら一心に見てゐると、狐はうしろを見たり、そばえたり、パツと飛んだり、いろいろの格好をした。そしてフイと見えなくなつて、それきり姿を見せなかつた。神様が見せて下されたのだ。有難いことだと思つて、それから一生懸命に勉强した。俺はそれから舞臺の絞も玉の紋にしたのだ。この話は誰にもするなよ。お前も一生懸命に勉强せい。
と仰しやいました。あんなに、まるで生きてゐるやうに狐を遣はれるまでには、玉造さんの苦心は一朝一夕のことではなかつたのであります。
古い話では、江戸猿若町の芝居で「石橋」の獅子を使つて大變な大當りだつたと申します。また松島文樂座で「松島八景」といふ所作事で七變化の早替りをして見物を驚かされたさうです。明治十三年の五月、やはり同座で「五天竺」の孫悟空を遣はれた時は、見物席の上を宙づりして、それが評判となつて七十日も大入がつゞいたといふことです。私が御靈文樂座へ初めて這入つた年にも「五天竺」が出まして、この宙づりで見物席の上を自由自在にクルクル廻つて見せられて、この時も大入でありました。
文樂座が松島から御靈へ移つた明治十七年九月の初興行の時には、「夜這星」の所作で、二階棧敷の三方の勾欄を宙づりでまるで飛鳥のやうに飛び廻られ、見物をヤンヤと云はされたと聞いてをります。
そのほか玉造さんの當り狂言は、お染久松七化、玉藻前の狐、二十四孝の狐火、伊賀越新關、千本櫻御殿、芦屋道滿、八犬傳、【桶】狹間合戰、七福神、四谷怪談、詠開秋七草、小倉色紙、大江山、などでありました。
玉造さんは、あれでなかなか性の惡い茶目氣分がありました。
明治二十三年の御靈文樂座の九月興行に「浦島太郎倭物語」が出まして、「法印祈りの段」で、浦島太郎を玉造さん、乙姫さまを紋十郎さんが遣はれました。太夫は竹本文太夫さん(今の津太夫)、三味線は鶴澤寛次【治】郎さんでした。
この時は舞臺の前の「かぶりつき」の處に三間眞角の水槽を取付けて本水が入れてありまして、--私十二歳の折の大ぶん古い話ですから、舞臺の順序には記憶違ひがあるかも知れませんが--何でも追つ手がかゝつて浦島が海へ飛込む體で、人形諸共、玉造さんはその本水のなかヘドブンと沈んで仕舞はれます。そしてすぐにまた浦島を遣ふて下手から舞臺へ出てこられます。人形も、肩衣も、玉造さんも少しも水に濡れてをりません。それが見せどころであつたのです。その時、水槽の中から龜が浮きあがつてきて、その龜が二つに割れて、その中から紋十郎さんが乙姫さんを遣ふてスと出られます。そんな段取だつたと覺えてゐます。
千秋樂の日でありました。いざ入水といふ時、玉造さんはツカツカと床のところへ走つてゆかれて、そこに並んでゐられた文太夫さんと寛治郎さんを捕まへて、お二人を一しよに水の中へ引張り込まうとなさるのです。驚いたのはお二人で、寛治郎さんは三味線を持つたまゝ床から飛びおりて、見物席のうしろまで逃げ出されましたが、お氣の毒に文太夫さんは玉造さんに捕まへられ、とうとう一しよに入水の憂目を見られました。
寛治郎さんは二人の入水を見届けてから、グルリと見物席を一廻りして床へ戾られて、素知らぬ顔をして控えてゐられます。玉造さんも、いつものとほりすぐまた無臺へ出てこられます、相變らず、着附けも體も少しも濡れてゐず、涼しい顔をしてゐられます。しばらくして文太夫さんも床へ出てこられましたが、文太夫さんは着附けも體もヅブ濡れのまゝでした。すぐあとを語らなければならないので、體を拭ふ暇もなくそんなりで出てこられたのでありました。見物は大喜びで拍手されます。文太夫さんは濡れ鼠のまゝで仕舞ひまでいつものとほりに勤められました。私も見てをりまして、子供心にその時の文太夫さんを「偉いなア。」と思ひました。見物にも大人氣でありました。
幕が閉つてから、文太夫さんが。
「お師匠はん。えらい目にあはしやはりましたぜ。水の中へ這入るのはよろしいけれど、あがる處がわかりまへんので往生しました。」
と云はれますと、玉造さんは。
「それは氣の毒やつたなア。アツハハハハ……」
と大笑ひをして面白がつてゐられるのでありました。文太夫さんは水の中でウロウロしてゐられたのですが、道具方が手を引張つて、やうやう見物に知れぬやうにあがられたのだといふことです。
この間も、その話を思ひ出して津太夫さんにいたしましたら、
「さうさう。あの時は往生した。あがる處はわかれへんし、それに幾日も替えてあれへんので水が臭ふて弱つた。しかし古い話やなア。」
と云つて苦笑してゐられました。
この時分、文樂座の總稽古の時に--總稽古といふのは人形、太夫、三味線一しよの稽古でありますが、稽古の最中に太夫や三味線彈きが、玉造さんから「そこは違ふ。」と駄目を出されることがたびたびありました。なかなか容赦がありませんでした。
これは有名なお話であります。玉造さんが、まだ稻荷座にゐられた頃でありました。「千本櫻」の「鮨屋」で、太夫は三代目竹本長門太夫さん、三味線は豐澤團平さんでありました。その時のことであります。
いがみの權太が、すし桶かゝえて引込むところ、
〽ヤこれわすれてはとひつさげて、あとをしたふて。[合]。
この合で、太夫、三味線、人形の三つの呼吸がピツタリ合ふて、玉造さんの腹帶がブツツリ切れたのであります。
長門さんの「あとをしたふて--ツ」とひつぱつて切る氣合。それを受けとつて彈き出す團平さんの氣合。
ヱーツ。テン、テン、テン、テンテンテンテンテン、テテテン、テテテン、テテテン、テンテンテンテツテツテツテツ--
人形の足どりもこの三味線に合はします。こゝのアウンの氣合に力が籠つて、玉造さんの腹帶が切れたのです。彈く人はもとより名人團平さんでありますが、玉造さんの意氣込みもそれほどはげしかつたのであると思ひます。これには「志渡寺」のお辻の水行のくだりであつたといふ異説がありますが、私は右のやうに聞いてをります。
今はなくなりましたが、その頃御靈さんの南門をちよつと南へいつた西側に道具屋さんがありました。玉造さんは暇があるとその店へいつてゐられました。
或る時、また例のコマシヤクレから私が、
「お師匠はんはそないに道具なぶりばつかりしてはりまんが、わかりまんのんか。つかみなはれしまへんか。」
と云ひますと。
「阿呆云ふな。俺は長年人形を遣ふてゐるので、何でも手の上へ載せて見れば、重みでわかる。」
と仰しやるのです。
私はそんなものかしらんと思ひましたが、こればつかりはいくら玉造さんでも少し當にならないやうな氣持も致しました。
あとで父にその話をしますと、父は、
「いやあの入なかなかよう見やはるぜ。わしも一ぺん掘り出されて、えらい損したことがある。」
と申されました。前にも申上げましたやうに、その頃父は骨董屋をしてをりました。
初代吉田玉助さんと申さるのが玉造さんの息子さんでありました。このお人もなかなか人形をよく遣はれましたが、惜しいことには若死されました。その玉助さんのお子さん、玉造さんのお孫さんにあたるお人は、今東京にゐられて富崎大檢校さんと申されると聞いてをります。
(つゞく)
攝津大掾さんがまだお若い時分、二代目越路太夫さんと申上げたはじめの頃のことで、その頃は堂島仲通りの尼ケ崎裏といふ十二三軒もある長屋にお住ひになつてゐられました。まだ連中をとつてお稽古をしておゐでになつたといふことです。
ある夜、更けてから大掾さんは、どうしてもそこの處がうまく語られないので、「中將姫」の雪責めの段の繼母岩根御前が、雪中に倒れてゐる中將姫の喉首を割れ竹で押へつけて折檻するところを、ひとりでしきりと御稽古しておゐでになりました。
「サア有やうに白狀しや。アヽイ。サアどうぢや。アヽイ。サア云はぬか。アヽ……プル……アヽ……プル……アヽイ。さあ白狀せい。アヽ……プル……アヽ、アヽ。アヽイ……
こゝの首を締められる悲鳴がうまく語れんので、そこをくり返しくり返し稽古してゐられました。
さうとは知らない長屋の人たちは、はじめのうちは近所に病人があるのだらう位に考へてゐましたが、いつまでたつても悲鳴がやまず、どうやら人の締め殺されゐやうな聲がするので、追々と長屋の人たちが起きてきて、しまひには長屋總出で「どこや、どこや。」と大騷ぎをはじめました。
それと悟つた大掾さんも、餘り騷ぎが大きくなつたのに恐縮されて、今更「私が中將姫の稽古をしてましたのや。」とも云はれず、皆の仲間入をして、一しよになつて「どこだつしやろなア。」と云つてとぼけてゐられました。そのうち誰かゞ、この裏には古い狸が住んでゐるといふことだから、狸の仕業かも知れぬと云ひ出したので、やうやく鳧がついたといふことです。
大掾さんの藝道に御熱心であつたお話はかずかず承つてをります、後年私も大掾さんの「中將姫」を聽きましたが、雪責めのくだりは中將姫の痛々しい苛責の有様をまるで目の前に見るやうに思ひました。「中將姫」は大掾さん十八番物の一つでありました。
大掾さんの語り物は澤山お有なされて、さすがに名人の淨るりだけあつてどの淨るりでも見物がワツといふところが六七箇所はかならずありました。そのうちでも私が聽かして戴いて特に感心致しましたのは、
二十四孝四段目、岸姫松三段目、戀女房子別れ、夕霧伊左衞門吉田屋、和田合戰三段目、中將姫雪責めの段、ひらかな盛衰記神崎揚屋の段、忠臣藏九段目、先代萩御殿、三勝半七酒屋、加賀見山長局、大功記十段目、梅川忠兵衞新口村、朝顔日記宿屋、阿波鳴戸八つ目、心中天網島こだつ、合邦辻下の巻、おしゆん傳兵衞堀川の段、妹背山四段目。
などでありましたが、わけても壇浦兜軍記の阿古屋、妹背山三段目の雛鳥、後室定高、忠臣藏七つ目のおかるなどは古今にすぐれた出來でありました。
大掾さんの淨るりのよかつたところを一々申上げてはきりがありませんが、例へば「吉田屋」のマクラのところ、はじめの方は長らく舞臺に出さなかつたのを、明治三十五年の文樂座の初春興行に大掾さんが出された時に、夕霧の出をつけるために、つけ加へられたマクラであります。三味線は五代目野澤吉兵衞さんでした。その全文を申上げますと、
〽戀風や、その扇屋の金山と、名は立のぼる夕ぎりや秋の末よりぶらぶらと、寝たり起きたり面やせて、藥も日數ふるゆきの、おもらぬ先のやうじようと、勤めも心のまゝなれど、ふかきよしみの吉田屋は、足元かるき道中や、のれんくゞるも力なく。[詞]けふはお目出たうござんす。アヽしんどやとこし打かけ、我身を横に投げ入れの、水仙淸き姿なり。[詞]--いろいろあつて--サ、サ、サヽヽ先づあちらへと座敷へこそは出しにける。
こゝまでは五行本にはありませぬ。それから本文のマクラになるのですが、
〽冬編笠の赤ばりて、紙子の火打ひざのさら、笠ふき凌ぐしのぶ草、忍ぶとすれど古への、花は嵐のおとがひに、けふの寒さをくひしばる……。
それから少し奥の文彌ぶしの、
〽昔はやりが迎ひに出る今はやうやう長刀の。
この間の間拍子のよろしいこと。何と云つたらよろしいか、絶世の妙技とも申すべきうま味がありました。それからまた奥の「ゆかりの月」といふ歌のところが實によろしうありました。
(話者はまた三味線をとりあげて彈きながら「ゆかりの月」を唄ふのでした。
〽可愛い男に逢坂の、關よりつらい世の習ひ、詞。思はぬ人にせきとめられて、今は野澤の一つ水。詞。すまぬ心のなかにもしばし、思はでうつす月の影。--
地唄風の、しかし粹な唄でありました。江戸唄にない境地で、それでゐて「もつちやり」しない、すつきりした調子です。上方の粹。さうしたものを感じながら筆者は聽きとれてゐました。)
これがあの大掾さんの美音でせう。全く惚れぼれいたしました。それからこの時の吉兵衞さんの三味線がまたよろしう御座いました。前にも申しましたが、吉兵衞さんの三味線は針金のやうによく鳴る、それはきれいな三味線でした。あのやうな「吉田屋」はほかに御座いません。それから「吉田屋」が流行るやうになりまして、文樂座でもよく出るやうになり、お素人衆もちよいちよい語られるやうになりました。しかし大掾さんの「吉田屋」は日本一、大掾さんかぎりの「吉田屋」でした。三代目越路さんでも音聲が違ひました。大掾さんに敎へて貰はれたのは越路さんのほかに故人竹本南部太夫さん、故人豐竹呂昇さんなどであります。呂昇さんのは私は聽いてをりますが、よくおぼえてゐられて大掾さんのとほりの節でした。今日では「吉田屋」を大掾さんの風で語るお人はないやうです。いつか豐竹呂之助さんのをきゝましたが、呂之助さんは呂昇さんからならつてゐられるやうでした。
大掾さんの「先代萩」を私が聽かして戴いた時は三味線は松葉屋さん(五代目豐澤廣助)でありましたが、マクラのあひだのよろしかつたことそれから少し奥の、
〽子は孝行に面痩せて、はごくみかへす烏羽玉の、涙をかくすうないがみ。--
この「はごくみかへす--」のあたりの間拍子は、松葉屋さんの三味線と大掾さんの美音とが調和して、惹き込まれるほどよかつたのを忘れません。こゝの三味線の手は松葉屋さんの工夫なされた手であります。私どもも滿足には彈けませんがこの手を彈かしていたゞいてをります。それからその奥の政岡のクドキの間の、
〽そなたの命は出羽奥州、五十四郡の一家中、所存の臍を固めさす。誠に國の礎ぞや。--
の「誠に國の礎ぞや。」の「ツキブシ」は誰でもが聲が足りなくて困るのですが、大掾さんは平氣なもので、そこは大掾さんのお得意のところでありました。見物は「はごくみかへす烏羽玉の」でワツと云ひ、「ツキブシ」でワツと云ひ、そのあとの、
〽七つ八つから金山へ、一年待てどもまだ見えぬ。合。
でまたワツと云ひます。そんな具合で大掾さんの淨るりは何べんでも聽きたくなるのでありました。
東京の杉山茂丸翁からお聞きした話ですが、明治三十六年の五月、文樂座に大掾さんの妹脊山四段目が出た時のことでした。この時は大隅太夫さんが文樂座へ入座されて始めての興行で、大隅さんは切狂言で「壼坂」を勤めてゐられました。杉山さんもわざわざ東京から見物に見えてをられました。
恰度大掾さんが舞臺を勤めてゐられた時、杉山さんの棧敷へ大隅太夫さんと南部太夫さんが行つてゐられました。大掾さんが、金輪五郎の鱶七がお三輪を殺すところ、
〽放しや放しやと身をもがく、たぶさつかんで氷の刄、わきばらぐつと差通せば、うんとのつけにたふれ伏す。刀を突捨あたりをうかゞひ目を配る。奥は豐かに音樂の、調子も秋のあはれなり。
こゝを語られるのを大隅さんが聽いて杉山さんに、
「兄貴のあすこのところは師匠(春太夫)のと違うとります。師匠のは、わきばらのところすぐ、ぐつとさしとほせばになるのだす。兄貴はわきばらと、ぐつとのあひだに間をのばしてます。あれは違ふてます。」
と云はれました。大隅さんは大掾さんの後輩でありましたが、大掾さんと同じ五代目竹本春太夫さんの門人であつたのであります。
杉山さんは「さやうか。」と云つてゐられましたが、傍らに聞いてゐた南部太夫さんが樂屋へ戾つて大掾さんにその話をされますと、大掾さんは、「大隅がそんなことを云うてゐるか、お前、大隅に芝居から歸りにわしの宅へ一寸寄るやうに云ふといておくれ。」
と仰しやいました。
御存じでありませうが、この場で金輪五郎がお三輪を殺すのは、本文にありますやうに、「彼(入鹿)が父たる蘇我の蝦夷、齡傾く頃までも一子なきをうれひ、時の博士に占はせ、白き女鹿の生血を取り、母に與へしその驗、すこやかなる男子出生、鹿の生血胎に入を以つて入鹿となづく。去るによつてきやつが心をとらかすには、爪黑の鹿の血汐と疑若の相ある女の生血、是を混じて此笛にそそぎかけて調ぶる時は、實に秋鹿の妻乞ふ如く、自然と鹿の性質あらはれ色音を感じて正體なし。其處を計つて寶劒を禍なく奪ひ返さん鎌足公の御計略。ものかげより窺ひ見るに疑若の相ある汝なれば、不便ながらも手に掛し」といふわけなので、これは手負ひになつてからのお三輪に、金輪五郎が云ひ聞かす言葉でありますが、仔細を聞いてお三輪は自分の命が戀人藤原淡海のためにも役に立つことを知つて、哀れにも喜んで死ぬのであります。疑若の相とは嫉妬の相をいふのであります。
大隅太夫さんが、南部太夫さんのことづけを聞いて、その夜大掾さんのお宅へ伺はれますと、大掾さんはかう仰しやるのです。
「お前さんの云ふとほり、あすこは師匠の語られたのとわしのは違うてゐます。師匠の型もわしはよくおぼえてゐますが、わしは心があつてあゝ語つてゐるので、間違うてゐるのではありません。こゝは金輪五郎はお三輪を殺しともないが、お天子様のために不便(ふびん)ながらも殺すといふところである故、わしは、わきばら--というてから口のうちで南無阿彌陀佛と稱へて、それからぐつとさしとほせばと語つてをるのです。
大掾さんのお話は大隅さんを心から敬服させました。大掾さんのお宅を辭して、大隅さんはすぐその足で、杉山さんの宿を訪ねられ、
「貴兄(あにき)は偉いものです。私も德をしました。」
と云つて、その話を杉山さんになさつたさうです。
私もこの時は「壺坂」のツレ彈きを勤めてをりましたが、この興行は大入で五月一日から七月十五日まで打續けました。
只今では時世が變つたとでも申すのでありませう。門人に稽古しますのに、「そこはさうでない。かうぢや。」と少しきびしく申しませうものなら、厭がつて明日から顔を見せぬといふ始末であります。
私が師匠淸六に敎へて貰ひました時分は、はじめ一度師匠が彈かれるのを聽かして貰ひ、次に師匠と一緒に彈きまして、すぐあと自分ひとりで彈くのであります。それでおしまひで、もう一度でも彈いたりしますと「お前はおぼえが惡いなア。」と云はれます。それではじめに聽かして貰ふ時は一心に聽いてゐなければなりませんでした。さうして翌日參りまして間違へると、すぐ拍子扇で頭をポカンと遣られました。師匠は至つて手が早かつたのです。それですから見臺の前へ据つたらもう一生懸命でありました。それに師匠もなかなかえらいところがありまして私の心をすぐ見ぬかれました。「こいつ、今日はこれから何處かへ行くな。」「今日はほかのことを考へてゐるな。」といつもさきに覺つてしまはれるのです。そんな時は容赦なくポカンを喰はせられます。見臺の前へすわつたら決して油斷はなりませんでした。拍子扇で叩かれるのは毎日のことで、撥で左手をしたゝかに打たれることもたびたびでありました。私の鶴五郎時代、師匠の鶴太郎時代から叶時代、こんなことがつゞきました。
三代目越路太夫さんが豐澤團七さんについて稽古なされてゐた時は、よく「いかん。」「いかん。」と云はれては撥で頭を打たれなされたといふことです。いつでありましたか、越路さんは頭にある疵痕を私に見せておゐでになりました。
このやうな稽古を今日の門人にいたしましたら事件になりませう。何事も時世で、いたし方はありませんが、藝道の修業は昔のやうな心意氣で致したいものだと常に私は思うてをります。つらい苦しいなかにまた云ふに云はれぬ嬉しいこともありました。
初代桐竹紋十郎さんは、近世女形遣ひの名人でお有りなされました。親御さんは桐竹門十郎さんと申されて、やはり立者(たてもの)であられたさうですが、門十郎さんと申されたので、紋十郎さんは初代であります。
私は紋十郎さんの舞臺を澤山に拜見してをりますが、そのなかで「あゝ美しい形やなナ。」と感心いたしまして今に目に殘つてゐる型が澤山に御座います。
紋十郎さんでよかつたのは、先代萩御殿の政岡、和田合戰の板額、壇浦兜軍記の阿古屋、朝顔日記の深雪、妹脊山のお三輪、同雛鳥、合邦辻の玉手、堀川のおしゆん、紙治のおさん、帶屋のお半、同おきぬ、酒屋のおその、野崎村のお光、二十四孝四段目の八重垣姫、鰻谷のおつま、ひらかな盛衰記の梅ケ枝、同おふで、千本櫻道行の靜御前、伊賀越八つ目のお谷、忠臣藏七つ目のお輕、同九つ目の戸無瀬、白石噺の宮城野、彦三毛谷村のおその、大功記十段目の操、加賀見山のお初、一ノ谷三段目の相模、吉田屋の夕ぎり、新口村の梅川、三十三間堂のお柳、などでありました。
このうちでも酒屋のおその、毛谷村のおその、お三輪、雛鳥、梅ケ枝、お筆、靜御前、玉手、政岡、板額、お光、操、お半は、とりわけよろしうありました。申上げたほかにもよろしかつたものは澤山にあります。
「千本櫻」の道行で、玉造さんの忠信と相舞のうちの、
〽なにがしは平家の侍惡七兵衞景淸と名乘かけ名乘かけ、なぎ立てなぎ立てなぎ立つれば、花にあらしのちりぢりぱつと、合テテテン、テンテンテンテンテンテン、ポトテン。
この合で、紋十郎さんの靜御前が扇を持つて、トントントントントンとあとへよるところのよろしかつたこと。まことに美しい形でありました。只今は團平さんの手を使ひまして、三味線は「はツ、ポトテン」だけになりましたが、その時分は前申したやうな手でありました。
「ひらかな盛衰記」のこし元お筆が別れて歸るところ、
〽見送るたもと見かへる袖、お筆は別れいでゝゆく。
で、舞臺下手で、一廻りグルリとまはつて見物にうしろを見せて這入る姿、これがよろしうありました。見物をワツといはせました。紋十郎さんは人形のうしろ姿を見物に見せるのが得意でした。阿古屋でも夕ぎりでも、「新吉原」の宮城野でもあの大きな人形をうしろむかせて掛の模様を見物に見せられましたが、その形が誠によろしうありました。紋十郎さんは見物に正面を向き、人形はうしろ向きのまゝで、しづしづと奥へ歩んでゆく姿は、まるで人形がひとりで歩るいてゐるとしか見えませんでした。「忠臣藏」の茶屋場のお輕の出の、二階の柱にもたれて左手をふところ手して、右の手でのべ紙をあふいで風を入れてゐる姿のよろしかつたこと目に殘つてをります。お輕がはしごを下りるところ「このはしごは勝手が違うて、どうやらこれはあぶないもの。--エヽ、もうのぞかんすないなア。」のあたり實に色氣があつて何ともいへませんでした。私のおぼえてをりますのは明治二十九年の四月、文樂座に「忠臣藏」が出ました時で茶屋場の配役は、
人形
お輕、初代桐竹紋十郎さん
由良之助、初代吉田玉造さん
平右衞門、二代目吉田玉助さん
太夫
お輕、竹本攝津大掾さん(當時二代目竹本越路太夫)
由良之助、二代目竹本津太夫さん(法善寺の津太夫と呼ばる)
平右衞門、初代豐竹呂太夫さん(はらはら屋と呼ばる)
三味線、五代目豐澤廣助さん
でありました。實に日本一の「茶屋場」であつたのであります。この時は非常な大入でありまして、四月十一日初日で六月十四日まで打續けました。
親御の門十郎さんは、紋十郎さんを人形遣ひにはせぬつもりで、紋十郎さんの小さい時分から堅氣の商家へ丁稚奉公に出されたのでした。しかし、醬油屋、砂糖屋、下駄屋、藍玉屋などと、あちらこちら奉公先はかはりましたが、何處も長つゞきがしませんでした。蛙の子はやはり蛙になるまで落ちつかなかつたのでありませう。どうしても親御と同じ人形遣ひになりたいと云つてきかぬので、しまひには門十郎さんもその氣になられて、ある席で「朝顔日記」の大井川の深雪の足を遣はして見られましたが、まるで無能だつたので、たつた一度で足があがつてしまひました。紋十郎さんの十四五歳の時であつたさうです。
親御さんの亡くなられた後、文樂座へ這入られて親御さんの以前の名であつた桐竹龜松を名乘つてゐられましたが、ある時「先代萩」の床下の鐵之助を遣はれたところ、相變らずの無能であつたので、頭取の二代目吉田玉治さんに呼びつけられて、「お前は駄目だ。とてもものにならぬ。」と云はれて、とうとう文樂座もことわられることになりました。もともと自分の藝道未熟から起つたことですから誰を恨むこともなりませず、そのまゝ引退るよりありませんでしたが、紋十郎さんは、この時に心から發奮されたのでありました。紋十郎さんは江戸へ上つて一修業しようと決心されました。『死物狂ひに修業して、文樂座から「龜松さん、どうか這入つてくれ。」と賴みにくるやうにきつとなつて見せる。今に見ろ。』さう心に誓つて、紋十郎さんは江戸へと志されたのでありました。大阪を發足された時、紋十郎さんの懷には只の十六文しか無かつたさうです。
しかし、このことは紋十郎さんの藝道のためには幸運であつたと思ひます。本當の藝は、生きるか死ぬるかといふ處までまゐりませねば出來るものではありません。
江戸へ上つた紋十郎さんは、女形(をやま)遣ひの名人、西川伊三郎さんと云ふお方について一生懸命に修業をなされました。またその伊三郎さんの父陸奥大掾さん、道化遣ひの辰松六三さんなどにも敎へを享けられました。この間の紋十郎さんの修業の苦しみは眞(まこと)に血の出るやうな難行苦業でありました。この頃から紋十郎さんは女形専門の意志を固められたのであります。そして紋十郎さんの命懸けの修業はつひに紋十郎さんを、その昔の辰松八郎兵衞さん、文化の頃の二代目吉田辰五郎さん、嘉永の頃の二代目吉田辰造さんなどと一しよに指を折られる女形遣ひの名人にしたのであります。
紋十郎さんの江戸修業時代、浅草の芝居で、「山科閑居」の戸無瀬を師匠の西川伊三郎さん、紋十郎さんは力彌の足を遣うてゐられた時のことでありました。或る日紋十郎さんは師匠の前に手をつかへて、「こんなことを申上げては惡うございますが、いつまでも足ばかり遣うてゐてもはじまりません。大阪へ歸る土産に、お情けにどうか一度だけ頭を遣はせて戴きたうございます」と折入つて賴まれました。伊三郎さんも紋十郎さんの心を汲まれて、下女のおりんの役をくれられました。頭を遣はして貰ふには違ひませんが、下女のおりんでは何もすることのない端役なので紋十郎さんは内心がつかりせられましたが、それでも足を遣つてゐるよりは増しとあきらめて、せめてのことに何とか新しい遣ひ方をしてみたいものと一生懸命に工夫を凝らされました。苦心の末、やつと工夫がついたので、その場を語られる織太夫さんの賛同を得、また左手や足を遣ふ人にも賴んで、それを舞臺に上せることになりました。
紋十郎さんの新工夫は、
〽昔の奏者今のりん、ドーレ、
といふところで、下女のおりんは赤い襷をかけて、髪を鬢つけで突立てさせ、結ひかけた髪といふ思ひ入れで飛んで出ます。訪なうて來た戸無瀬と小浪の二人を見て吃驚して、先づ襷をはづし、髪をキリキリと巻き上げて簪で止め、その手を前垂れで拭いてそれを帶にはさみ、兩手をつかへて「どなた様」といふ思ひ入れをする、といふのでありました。これが大變に受けまして、紋十郎さんの龜松さんは一ぺんに見物に存在を認められるやうになつたのであります。
この新工夫が云ひ傳へられて、歌舞伎の方でも相當の役者が下女のりんを買つて出て、この紋十郎さんの型を演るやうになりました。人形の方は勿論、東西の歌舞伎に、今にこの型が傳はつております。人の一心といふものは恐しいものでございます。
紋十郎さんは天保十二年生れで、明治四十三年八月七十歳で亡くなられました。
私が文樂座へ這入つて間のない、まだ子供の時分のことでありました。その時分の文樂座の樂屋の便所は汚なう御座いました。皆が手洗ひの水を飛ばすので、いつでも駒下駄がビチヤビチヤに濡れてゐて、それに履き替へるのが氣持が惡くて弱りました。見てゐると上の方の人達は皆上草履のまゝで用をすましてゐられます。しかし私ども下つ端の者はそんなことは出來ません。氣持の惡いのを我慢して、正直に履き替へてをりました。
ある時私が便所へ行かうとしてゐましたら、うしろから呂太夫さん(初代)がおいでになつて私を追ひ越して、例のとほり、上草履のまゝサツサと用をすまして歸つてゆかれました。それを見てゐて私もつい「エヽ、やつてやれ。」といふ氣になつて上草履のまゝで用をして歸りかけてゐるところへ、運惡く紋十郎さんがおいでになりました。
「こらこら、草履を履き替へんといかんやないか。」
と仰しやいます。何も云はずに「へい。」と云つてゐればよいものを。
「呂太夫さんのお師匠はんかて履き替へはれしまへんぜ。」
と私は云つたものです。今から思へばずゐ分向う見ずであつたと思ひます。紋十郎さんはその時は默つておいでになりましたが、お部屋へ歸られると早速、あれは誰の弟子かといふことになり、
「あんな若い者で、俺(わし)に口答へする者は今までに文樂にゐやせなんだ。あんな者あすから文樂へ寄越すな。」といはれましたさうで、たちまちその翌日から私は文樂座出勤を差止められました。
紋十郎さんの門人で、その當時桐竹龜松さんと申されたお方が私を可愛がつてゐて下さいましたが、このお方が詫びを入れて下さつて、やうやく御勘氣がゆりました。
紋十郎さんはお氣むづかしいお方で、御自身は時には冗談を仰つしやることもありましたが、こちらから冗談は生涯申上げられぬお方でありました。
十三四歳の頃でした。ひどい雨降りの日の夕方、私は文樂座から久寶寺町の淸六師匠の家へ歸る途中、北の御堂さんの裏手を歩いてをりました。もう薄暗い刻限で、雨で人通りも途絶えてをりました。
その時分私は至つて柄の小さい方でした。大きな番傘をさして、はだしで、向うも見ずに道を急いでをりました。
恰度、明かずの門の前へ差かゝつた時、突然大聲で、「誰やツ。」
と怒鳴りつけられました。私は飛び上るほど吃驚しました。見ると誰だか目の前に立ちどまつてゐられます。私も思はず大聲で、
「文樂の鶴五郎といふ三味線彈きでおます。」と云ひますと、その人は、「あゝ吃驚した。」
といつて行き過ぎられました。
あとで聞いたら、その人は豐竹呂太夫さんの連中さんで、たしか上町のいづ駒さんといふお人で、その時私を「まめだ」かと思はれたのださうです。私はこの話を思ひ出すたびに、小さい私が大きな番傘をさしてゐる姿が浮んでくるのでございます。
(「まめだ」といふのは貉か狸かの化けたもので、大阪には古來から、
雨がショボショボ降る晩に
まめだが德利もつて酒買ひに
といふ童謡があります)
同じ時分のことでした。
法善寺の津太夫さん(二代目竹本津太夫--後に七代目綱太夫)といふお方は、大變にやかましいお方でありました。淨るりはなかなかの名人でしたがお聲の小さいお方でした。
文樂座の樂屋の三階は恰度見物席の眞上になりますので、そこで三味線の調子を合はしてゐますと、下へそれが聽こえるのでした。津太夫さんの出てゐられる時に、上で調子を合はしてゐると、お聲が小さいのでそれが邪魔になると見えて、すぐお叱言(こごと)が來るのでした。それで私たちも氣をつけてゐるのでしたが、それも無理な話で、そこよりほか調子を合はしたりする場所はないのですから、出番の前などには困るのでした。
ある時も、出番の前だつたので、うつかり津太夫さんの出てゐられるのを知らずに調子を合はしてゐますと、下から注意がありました。「しまつた。」と思ひましたがもう遲い。こんな時はきつとあとで叱られるのです。しばらくすると津太夫さんがあがつてこられる足音がしますので、私は部屋の偶(すみ)に積み上げてある三味線箱の陰へかくれました。津太夫さんは部屋へ這入つてこられるなり、
「誰や、こゝで三味線を彈いてゐたんは。」と仰つしやいましたが、誰もゐないので、
「もう何處や行きよつた。」と仰つしやつて、舌打をして出てゆかれました。
それはそのまゝすんだのですが、餘り津太夫さんのやかましいのが忌々しくて仕方がないので、惡戯友達の同志と相謀つて、津太夫さんに何か仕返しをすることに議決いたしました。相棒は豐澤龍助さんの門人で龍之助といふ惡戯者(わるさ)でした。
「戀飛脚大和往來」が出てゐまして、津太夫さんは「新町」を語つてゐられました。或晩、津太夫さんが舞臺へ出られるのを見計らつて、私と龍之助の二人はソツと舞臺の上に吊り渡した板の上に忍んでをりました。三階の奥が舞臺の上になつてゐました。板の上には次の「新口村」で降らす紙の雪で籠に入れて兩はしに一つづゝ置いてあります。舞臺ではやがて忠兵衞が思ひ切つて封印を切りました。
〽十二十三十、四十つまらぬ五十兩。
といふところで、私と龍之助は一せいにその籠をぶちあけて舞臺へ雪を降らしたのです。見物はワツと云はれます。「誰や。」「誰や。」と云つて道具方がドヤドヤあがつてきます。二人は素早く、もう一つ上の處へよぢ登つて息を殺してかくれてゐましたので、見つけられずにすみましたが、餘り騷ぎが大きくなつたので、怖くなつてきました。次の「新口村」で、道具方が雪を降らしにあがつてきて下りてゆくまで、ジツとかくれてゐて、それからソツと下りて裏口から、二人ともはだしのまゝで、御靈さんの境内をぬけて逃げて歸りました。
翌る日知らぬ顔して文樂座へゆきますと、昨夜の話でやかましいことでした。誰だかわからぬが、下駄箱に、下駄が二足殘つてゐたと云はれた時はドキンといたしました。幸にしまひまで露見せずにすみましたが、無茶苦茶なことをしたものであります。思ひ出すと冷汗が出ます。
明治二十四年の五月二十一日に蓋をあけた文樂座の切狂言は「國性爺合戰」で、獅々ケ城の段を初代竹本呂太夫さん、三味線は淸六師匠當時鶴太郎が勤められました。その時のことでありました。
淸六師匠が舞臺を勤めてゐられる最中に、三味線の皮が破れました。師匠は【床の】うしろの板をコンコンとたゝかれます。弟子はいつも別の三味線を用意して裏に控へてゐて、こんな時はすぐ取替へる役目をしなければならないのです。ところが生憎私はその時三階の部屋で、ちよつと横になつてゐるうちに、何しろ朝が早いものですから、ついウツカリと眠つて仕舞つてゐたのでした。師匠はいくらたゝいても應へがないので、自分で三階まで三味線を取りにあがつて、また舞臺を勤められました。役をすまして師匠が三階へあがつてこられたのも知らずに私はまだ眠つてをりました。たゞさへ疳癖の强い師匠、役のあひだ押さへ付けてゐた怒りが爆發して、いきなり私は蹴り飛ばされました。その拍子に私は、途中で一曲りしてゐる階子段(はしごだん)を一番下まで轉がり落ちて氣を失なひました。ヘタリ(大工)の、いさはんといふお人が私を部屋へ連れていつて介抱して下さいました。
家へ歸つて師匠がその話をされたので、お年寄り--前申した黑鶴さんのお母さん--が私の實家へ知らして下さつたので、母が迎ひにきてくれられました。父がぐずぐず云ふのを押へつけて、母が私を師匠の家まで送つてくれ、挨拶をしてくれられました。師匠も案じてゐられたところだつたので喜んで下さいました。あとでお年寄りから「そんな心懸けでは修業はできん。」と云ひ聞かされました。
大隅太夫さんは、藝道には實に御熱心なお方でした。全く「凝り固まり」でした。明治三十六年九月三十日初日の文樂座の切狂言は、「桂川連理柵」で帶屋を大隅太夫さん、三味線は淸六師匠でした。師匠はこの時三代目叶から三代目淸六になられたのであります。
この時の大隅さんの帶屋のよかつたことを忘れません。マクラのあひだの間拍子のうまいことゝいつたら、地合ひ(節)の長短、アウンの呼吸の具合など目も覺めるやうでありました。私はその時は鶴太郎になつておりましたが、それまでに、そのやうに足が早くて、口調がよくて、文句がよくわかつて、それでゐて情合のある帶屋を聽いたことがありませんでした。それで私は師匠に「これはほんまの帶屋の足どりですか。」ときゝましたら、師匠は「これが淸水町さん(豐澤團平)の彈かれた手や、お前もよう覺えておきなされ。」と云はれました。私は初日から打上げの日の十一月三日まで毎日聽かして戴きました。大隅さんは繁齋がよろしい、母おとせがよろしい。長右衞門、義兵衞、お半、長吉、みな申分ありませんでした。殊に奥になつてからの繁齋のよろしいことゝ、お半の可愛らしいこと無類でした。舞臺裏は樂屋の聽き手で一ぱいで、ちよつと遲いと場所がないくらひでした。私も一日も缺かさず、「えゝなア。」「えゝなア。」と思つて聽かして戴きました。
ところでこの三味線で師匠淸六の苦心は並大ていではありませんでした。はじめのマクラのところと、奥のお絹の這入るところの、
〽や、むんころり、合テツヽン、こける夫にあてがふ枕、ふとん打きせ女房は、合チン、
これがうまく彈けんといふので、毎日大隅さんと師匠は合はしてゐられました。
〽打きせ女房は。
の三味線、
ツツテチ、チヽチヽチテツテ、チヽテツツンツントン、合チン、
こゝのところを、大隅さんは毎日のやうに「田中(淸六の姓)けふもいかんぜ。」と云はれるので、毎日毎日殆ど千秋樂まで、二人でこゝを合はしてゐられました。
こゝは誠にむつかしい三味線でありまして、力一ぱい彈きますときつすぎていかず、力をぬけば音が小ひさくなつてまたいかず、そこが苦心のいるところで、私どもにもいまだにうまく彈けません。
師匠は自宅でゞも、マクラと、サワリと、お半の出と、この「ふとん打きせ女房は。」のところを毎日毎日一人で彈いて稽古してゐられました。
この時は見物にも大變な人氣でありましたが、私は大隅さんと師匠とお二人の火の出るやうなお稽古ぶりを、はたで見ておりまして全く頭が下がりました。
大隅さんは明治三十九年の六月興行かぎり文樂座を退座され、淸六師匠は文樂座にふみとゞまられたのでした。
大隅さんは本名を井上重吉さんと申上げ、大正二年七月三十日、六十歳で、臺灣巡業中にお亡くなりになりました。
大正十一年の一月十九日の朝でした。私は毎年一月に八幡の石淸水八幡さんへお參りする例になつておりまして、その日がお祭りのしまひの日でありましたので、早朝五時頃仕度をして家を出かけようとしてゐますと、鹽町の師匠の家から弟子の淸丸といふのが驅けつけてきて、「師匠の容態がむつかしいから、すぐ來てほしい。」といふのです。
師匠は前年の秋頃から肺尖を惡るくして床についてゐられましたが、御自身も私どもゝむつかしいやうなことは考へてゐなかつたのでした。
意外な報せに驚いて私はそのまゝ淸丸と一しよに驅け出しました。早朝で電車はまだ動いてゐず、その時分にはタクシーもありませんでしたので、老松町から鹽町まで驅けとほしました。
師匠の枕頭へ驅けついた時は、師匠はすでに縡切(ことぎ)れてゐられました。師匠のからだに觸つてみましたら、まだ體温が殘つてゐました。その場にはお醫者さん、師匠の御内儀さん、御子息の永太郎さん、芳之助さん(養嗣子)など皆さんおいでになりましたが、聞けば誰も死目に會はれなかつたといふことでした。師匠は前晩床の上に起きあがつて、機嫌よくお話をなさつて朝になつて、家人の知らぬ間に危篤になつてゐられたのだといふことでした。がつかりして氣がついたら私は下駄のまゝで座敷へあがり込んでゐました。
師匠は行年五十五歳でした。身を打込んだ藝道の勉强が師匠の命を縮めたと思ひます。惜しいことをいたしました。本名を田中福太郎さんと申上げます。
--筆者の問ひに答へて--
今の淸六さんが、德太郎さんから四代目淸六さんになられた當時、淸六の高弟であつて何故淸六を繼がないのかといふお尋ねを諸方からうけて困りました。
しかし、それはかういふわけであつたのです。淸六といふ名は、代々叶にはゆかりのない名であつたのですが、法善寺の二代目津太夫さんの御内儀さんが初代淸六さんの娘さんでありまして、そのお方が師匠を見込んで賴まれたので、師匠--當時叶--は三代目淸六を繼いだのであります。
淸六といふ名は立派な名であつたのですが、二代目淸六さんは東京にゐられて、申憎いことでありますが、淸六の名を小ひさくしてしまはれたのでした。それで津太夫さんの御内儀の、師匠へのお賴みは、「淸六といふ名をあんたに磨いて貰ひたい。そしてあんたに門人もあるが、この名はあんた一代でこちらへ返してほしい。こちらの孫娘に三味線彈きを貰ふて四代目を繼がしたいから--」といふのでありました。師匠はそれを承知して引受けられたのであります。
私はこの時、師匠から叶の名を戴いたのでありますが、未だ藝道未熟でありましたので、叶の名を辱しめるのを恐れて、しばらく私の心にまかして戴き、大正二年の文樂座初春興行に、前狂言「大功記」七ツ目の切、杉の森で、九代目竹本染太夫さんの三味線を勤めまして、四代目叶に改名いたしました。
師匠淸六は前申したやうな次第で、門人一同に何の御遺言もなくお亡くなりになりましたが、師匠が襲名の事情はかねて師匠から承つておりましたので、未亡人とも談合の上、淸六の名は法善寺の方へお返ししたのです。今の四代目淸六さんの御内儀さんは法善寺津太夫さんのお孫さんです。師匠は、約束どほり立派に淸六といふ名に磨きをかけられたのでありました。(完)
鶴澤叶聞書 文藝春秋 第十一巻七號 1933.7.1 pp 116-123
ある時、團平さんのところへお出入の三味線屋の桝東といふのが、三味線の張替へが出來たのを持つて參りますと、團平さんはそれを彈いてみられて、
「これア鳴り過ぎていかん。もう一ぺん張り替へてきてんか。」と仰しやるのです。桝東は今までに、何處へいつても「張りが足らん。」といふ叱言は聞いても、こんなことを云はれたことはないので、合點がゆかず、怪訝な顔をしてゐますと、團平さんは、
「わしの三味線を聽いてもらふのやつたらこれでえゝのやが、わしは太夫の三味線を彈くのやから、これでは三味線が鳴り過ぎて、とても太夫が語られへん。」
と仰しやるのでした。
明治三十七年二月、文樂座で三代目大隅太夫さんの「八陣守護城」が出た時のことでした。初日前のある日、私が何かの用事で玉造さんのお部屋へ參りますと、玉造さんは人形の頭を塗り替へておいでになりました。
「何の頭だんね。」
ときゝますと、
「正淸や。」
と仰しやいます。
正淸の頭は、私は攝津大掾さんの時のを覺えてをりますが、もつと肉色が濃くて、桃色であつた筈でしたが、その時のはひどく白くなつてゐますので、
「えらい白おまんねなア。」
と申しますと、
「うん、今度はこないしとかんと太夫がしんどい(苦しい)。」
と仰しやいました。
玉造さんは、太夫の聲柄や語り口が、その役の人形としつくり合はない時には、人形の頭を塗り替へられるのでありました。それから注意して見てをりますと、玉造さんの遣はれる人形の頭が、太夫によつて時々塗り替はつてゐることに私は氣がつきました。
文樂座の稽古は、初日の前々日タテ稽古(太夫、三味線だけ)前日總稽古(太夫、三味線、人形一しよ)といふ順序になつてゐますが、タテ稽古の前にも、太夫、三味線は、さうしないと太夫の聲が決まりませんので床で稽古いたします。そんな時、玉造さんはジツと太夫の語り口を聽いてゐられるのであります。
玉造さんはこの年に亡くなられました。
呂太夫さんは聲量の偉大なお方でありました。大音强聲で三段目など大物を語られるのを得意となされて、當時攝津大掾さん、法善寺の二代目津太夫さんに次いでの立物でありました。
御靈の文樂座は、見物席の兩横の上が高窓になつてをりましたが、三段目の始まる午過ぎ頃に私が出勤いたします時、御靈さんの南門から一丁南の瓦町までまゐりますと、「大おとし」の節のところなど呂太夫さんのお聲はそこまで聽こえました。「あゝもう三段目やな。」と思つて急いで歩るくのでした。
「八陣守護城」の舟の場の正淸の笑ひを、呂太夫さんは、ウーフ、アーハ、を百遍ぐらひ笑はれました。しまひのウハハハハハハ……なども遠方から聽こえました。
お得意は、伊賀越の五ツ目、竹中砦、熊谷陣屋、又助住家、ひらかな三段目、志渡寺、大安寺堤、信長記天下茶屋の段、世話物では橋本などでありました。
前にも申しましたが、その頃文樂座で出ればいつも大入で、七十五日も打つたことのある「忠臣藏」の茶屋場の掛合は、二代目越路太夫さん(攝津大掾)のお輕、二代目津太夫さんの由良之助、呂太夫さんの平右衞門といふのが極り役でありましたが、このお三人の聲柄が、それぞれの役に打つて付けてよく合ふてゐて、よろしかつたのが人氣を呼んだのでありました。
呂太夫さんはお素人から出られたお方で、その頃市中を「はらはらぐすり--」と云つて賣り歩るいてゐた藥屋の本家の主人で、お素人の時の淨るりの俳名を二代目呂篤さんと申されました。はじめ初代豐竹古靱太夫さんに入門され(明治七年)古靭さんの歿後五代目豐竹駒太夫さんの預り弟子となられました。(明治十一年)舞臺へ出られたのは明治七年頃、人呼んではらはら屋の呂太夫さんと申します。今でも天神橋の北詰を一丁ほど北へ這入つた東側に、はらはら藥屋は殘つてをります。
何にしても、稀らしくお聲の大きいお方でありました。本名を上西吉兵衞さんと申上げ、明治四十年に六十五歳でお亡くなりになりました。
それから、はらはら屋さんを普通には初代と申し慣らしてをりますが、古く享保十年頃豐竹越前小掾の門人に初代豐竹呂太夫がありますから、本當は二代目であります。
今日では太夫も三味線も、西流東流どちらの物でも演りますが、大昔は東と西と劃然と分れてをつたのであります。
西流の元祖は初代竹本義太夫、後の竹本筑後少掾であります。貞享二年乙丑二月一日、始めて道頓堀にて櫓を揚げて操芝居を興行す。狂言は「世繼曾我」作者近松門左衞門なり。--と古文書に見えてをります。これが竹本座の濫觴で、只今の浪花座の位置であつたと聞いてをります。筑後少掾の三味線を彈かれたのは竹澤權右衞門と申されたお方で、義太夫節三味線の元祖であります。西流の太夫では、筑後少掾のほか竹本播磨少掾(二世義太夫)、竹本政太夫、竹本錦太夫、竹本土佐太夫、竹本春太夫、竹本長門太夫、竹本佐内など、三味線では鶴澤三二(後に初代鶴澤友治郎)、鶴澤義助、竹澤彌七、竹澤兩助、大西藤藏、鶴澤文藏(兒島屋文藏)、鶴澤淸七などが聞こえてをります。
東流は豐竹若太夫と申すお方、後に豐竹上野少掾から豐竹越前少掾になられたお方からはじまつたのであります。はじめは竹本采女と申されて初代竹本義太夫の門人でありましたが、天性に一二三の音の揃ふた美音で、殊更三の聲が勝れて美しく、當時、マカンの音(三の高音)は古今に勝れたりと云はれ、市中大評判であつたといふことであります。
元祿十二年師匠義太夫の許しを得て一流を立てられ、聲さわやかな太夫を選んで、道頓堀の東に豐竹座--東の芝居--を創められたのであります。追々に新作物も上演し、聲華やかに節付けて語るので人氣を呼んで芝居も大いに繁昌いたしました。これを東流と申します。
東流の當時の太夫は、豐竹若太夫、後の越前少掾、豐竹河内太夫、豐竹阿蘇太夫、二世豐竹若太夫、豐竹駒太夫、豐竹鐘太夫、豐竹筑前少掾(前名此太夫)、二世豐竹此太夫、豐竹肥前少掾など、三味線は竹澤藤四郎--元竹本座の竹澤權右衞門の高弟、後に豐竹座に入り立三味線になられたのであります。--それから野澤喜八郎、鶴澤平五郎、野澤淸五郎、野澤文五郎などであります。
東流はさきにも申しましたやうに、華やかに節美しく語ります。西流は古風に、澁味のある語り口です。同じハリマ節でも河内路でも、東と西とは語り口が違ひます。三味線も彈きやうが違ひます。尤もハリマ節と云ひ、河内と云ひましても色々ありまして、こまかいことはお話では申されませんが、たとへば「双蝶々曲輪日記」の「引窓」これは通例のハリマ節で、二世竹本政太夫場ですが、(話者三味線を取り上げて彈き語りをする。)
〽おはやは始終物案じ、さしうつむいて居たりしが、--
この「さしうつむいてゐたりしが、」のところ早く、語るも彈くもスネルのです。これが西風のくせであります。
それから「先代萩」の「御殿」これは豐竹若太夫場ですが、これも通例のハリマ節です。(話者再び彈き語りする。)
〽おさなけれども天然に、大守の心備はりて、
こゝは彈くも語るも、ノンビリ大容な節付になつてをります。これが東風と承つてをります。こんな風に東と西と狂言も違ひ、舞臺、人形の美をつくして兩座が競爭いたしましたので、市中の贔負連も自然と東と西に別れまして、寶曆年間まで大變な人氣が續いてをつたといふことであります。
西流と東流の狂言の有名なものと、初演の太夫を少しだけ申し上げてみますと、西流--「嫗山姥三段目」「お初德兵衞曾根崎心中」「おふさ德兵衞重井筒」初代竹本義太夫。「國性爺三の切」「御所櫻三の切」「ひらかな盛衰記三段目」「心中宵庚申八百屋」二世竹本義太夫。「双蝶々曲輪日記橋本」「戀女房染分手綱十段目」「ひらかな盛衰記四段目」「安達原三段目」竹本大和掾。「伊賀越岡崎」「花上野志渡寺」「加賀見山長局」初代竹本住太夫。「忠臣藏四段目」「千本櫻二の切」「双蝶々引窓」「源平布引瀧三段目の切」「忠臣藏十段目天河屋」二世竹本政太夫。「二十四孝二の切」「妹脊山三段目」「お千代半兵衞八百屋」「伊賀越六ッ目の切」初代竹本染太夫。等々。東流--「和田合戰三段目市若腹切」初代豐竹若太夫。「一ノ谷三段目」「忠臣藏九段目」「菅原三段目切」「玉藻前三段目」「橋供養三の切」初代豐竹此太夫。「菅原四段目」「二十四孝三段目」「一ノ谷二の中組打」「岸ノ姫松三段目」豐竹島太夫。「妹脊門松質店」「戀飛脚新口村」「合邦辻下の巻」「お半長衞門帶屋」「白石噺吉原」二世豐竹此太夫。「太功記十段目」「鎌倉三代記八冊目」「蝶花形八ッ目」「日吉丸三段目」初代豐竹麓太夫。「二十四孝四段目」「忠臣講釋七ツ目」「近江源氏八ツ目」豐竹鐘太夫。等々であります。
今日でも西流のものは西風に語り、東流のものは東風に語るのであります。三味線も同様であります。
義太夫節の三味線は、三味線を彈くのではなくて、淨るりを彈くのでございます。彈くだけは彈かねばならず、彈き過ぎてはならないのでございます。そして何處までも太夫が主、三味線が從であることを忘れてはなりません、しじう太夫を表に立てゝ、三味線は裏へ廻らねばなりません。時に應じて三味線の音を殺したり、押へたりして彈かねばなりません。聲量の少い太夫の合三味線を勤める場合などには、一層の手ごころがいるのでございます。太夫を閑却して、腕にまかして三味線を彈きまくり、たゝきまくるといふことは本意ではありmせん。こゝが三味線彈きの辛らいところで、大抵の場合三味線彈きの苦心は認められることが少ないのであります。しかし何處までも三味線彈きは太夫のよい女房であることを努め、それを本懷としなければなりません。義太夫節以外の音曲では、常盤津の三味線が同じ手ごゝろであるやうに存じます。義太夫節の三味線で精一ぱい彈いてよいのは、景事--道行とか三番叟などを申しますが、その三味線だけであります。
「淨るりを彈く」といふことは、なかなかむつかしいことで、彈け、彈くな、でありまして、その彈かぬといふことがむづかしいのでございます。これは私が申上げるのではなく、若年の頃に淸六師匠や絃阿彌師匠などから、矢釜しく云ひ聞かされたことでございます。今もつて滿足に彈けませんのをお恥かしく存じます。
明和の頃、初代鶴澤友治郎の門人に、初代鶴澤市太郎さんといふお方がおいでになりました。盲人でありましたが、名人の聞え高く、また大變に勘の早いお方でありました。こんな話が傳つてをります。
その頃堀江の阿彌陀池裏門筋に、石村といふ三味線屋があつて、或る朝兄弟子の兒島屋文藏さんが、何かの用事でその店へ行つてゐられると、折柄表を市太郎さんが通りかゝるのでした。文藏さんは矢庭に、店先に有合はす三味線を追取つて、一の絲を一と撥ち、
トン--
と打たれました。
三味線の音で往來に立止つて眼の見えぬ市太郎さんは、店の方を振り向いて、ニツコリ笑ひながら、
「あツ、兄(にい)さん。お早う。」
と挨拶をされたといふことです。文藏さんも名人でありましたが、恐しい耳もあつたものであります。
市太郎さんは大阪土佐堀の生れ、後に伊勢の山田吹上に居住されましたが、明和の頃は道頓堀西の芝居に出勤してゐられます。人呼んで伊勢の市太郎さんと申します。
或ゐ時、伊勢の山田の市太郎さんのお宅へ、旅稼ぎの太夫三味線彈き二人がお伺ひにきて、
「私どもゝ、しじう旅あるきばかり致しますので、大ぶん淨るりが老い込みましてございます。」
と申しますと、市太郎さんは聞きもあへず、かう仰つしやつたさうです。--これは古く、さるお人が書き殘されたものゝ中にありますので原文のまゝ申上げます。
ハテナ。貴様いつおひ出たるや聞かざりし。コレよう聞けよ。當時日本に淨瑠璃語りと云ふは只六七人も有ふか。其譯はまづ中通りが二十人も有べし。其あとが下通り、いくら有やら限りなし。家業とする中に極道が何程有ふやらかず知らず、三味線も段々差別が有り、本道を彈く人が廣い世界に三四人もないくらゐぢや。あとはならず者の、かぢるか、もつか、にぎるか。モウモウ其下を見ればほうずがない。三味線鳴らしか、又かぢるか、中通りか下通りならばまだしも、渡世にしながら三味線にぎりが箒で掃く程有じや。アヽ氣の毒じや。もつとも三味線にも己れが師匠に敎へられしを一がいによいと心得、外の藝は耳に入らず、かたくなにおぼえし通りより彈かざるは是極道のずい一なり、佛藝といふて此道の大禁物なり。中々さやうの小いさき物ではなし。本道をよくわきまへ其上にては自力第一なり。ケレンも時によつては用ゆべし。本道を知らざる者は用ゆべからず。只この道の極意を早く修業したきものなり。中々本道を少しにてもおぼえし者ならではケレンをやつても人が用ひぬぞよ。貴様もせめてケレンのケの字はならず共、下通りにてもなりたくば、こちの内に二三年もゐて、わめいたり、にぎつたりして見よ。
とあります。なかなか意地の惡い、辛辣な言葉でありますが、この通りに違ひございません。此道を修業する者にとつては耳に痛い言葉でございます。
昨年の十月、文樂座に「新版歌祭文」の野崎村が出ました時は、掛合の三味線を私が勤めましたが、毎日舞臺を勤めてをりまして、お染の出の、
〽切ても切れぬ戀衣や。元の白地をなま中に、お染は思ひ久松が、跡をしたふて野崎村、つゝみ、合チンチン、チンチン、チンチン、チンチン、チンチン、チテツン、ツヽン、テレトン、づたひにやうやうと、梅を目あてに軒のつま。--
こゝの合の手のところへ參りますと、昔聽いた松葉屋の大師匠のこゝの三味線を思ひ出すのでした。攝津大掾さんがまだ越路太夫と申された頃で、五代目廣助さんが彈いておいでになりました。廣助さんが、
チンチン、チンチン、チンチン、--
とお彈きになりますと、それこそ、本當にそこへお染が、首をふり、振袖を振つて、堤づたひに小走りに走つて出てくるやうに聽こえました。それがまざまざ耳に殘つてゐますので、一生懸命に彈いてをりましても、自分ながら自分の彈く三味線が聽き劣りがいたしまして、毎日氣が惡くて氣が惡くて困りました。
廣助さんの三味線は、間とか、模様とか、さういふ技巧の水際立つて冴えた、駈け引きの鮮やかな、まことに妙味のある三味線でした。思はず惹き込まれるやうなところが澤山にありました。重ね撥など、手厚くて、きつぱりしてゐて、それは綺麗なものでありました。耳にも殘つてをりましても、とても私どもに眞似は出來ません。さうかと云つて大きいところはまた吃驚するほど大きいのでありました。私どもがこんなことを申すのは僭上の沙汰でございますが、團平さんの三味線は力倆(ちから)のあり餘つた三味線、廣助さんの三味線は技巧の洗練され切つた三味線、と申上げてよいかと存じます。
廣助さんの三味線のよろしかつたところを申上げれば澤山ございますが、特に印象の殘つてゐますのでは、「先代萩」の御殿の「子は孝行におもやせて、はごくみかへすうばたまの」のところ、
チゝチンチン、チリチチン合チチンチン、チレチンチチン、チンチンチンチレチンチンリン、やツ、チリチヽチンチンチン合チレチンチンチンチン、チンチンチリンチチレチレツン合テンチン。
こゝの間がよろしかつたこと、何ともいへませんでした。こゝは松葉屋さんの手付けでありました。語られる大掾さんの淨るりと、廣助さんの三味線との呼吸(いき)が、キッチリ合ふてゐたのでなほよろしかつたのですが、廣助さんは、大掾さんと御一しよに舞臺を勤めてゐられても、右のやうな妙處へ參りますと、「松葉屋はん、松葉屋はん。」「お師匠はん、お師匠はん。」と、お見物から三味線に聲がかゝりました。
いつでありましたか、「白石噺」の新吉原が出ました時でした。廣助さんの前彈きを聽きますと、ほかのお人は、もつと花やかに彈かれたやうに覺えてをりますのに、お師匠さんのは大變にゆつくりした間で、何處となく陰のこもつた調子に聽こえますので、どういふお心持でお彈きになるのかとお伺ひ申しましたら、「お前も知つてのとほり、吉原には兩側に掛あんどがある。これは入相時で、その掛あんどに一ように灯がはいる。日暮れの吉原の景--その心で彈いてゐる。それでこゝはむづかしいのや。お前もいまに年がいたらわかる。よく聽いておきなされ。」
と廣助さんは仰つしやいました。
それからお師匠さんがこの前彈きをお彈きになるのを、私は眼をつぶつて、ジツと聽いてをりますと、入相時の吉原の情景が見えてくるやうに思ひました。今日それを思ひ出しますと、お師匠さんの仰つしやつたことが、よくわかりますだけに、つくづくお師匠さんに及び難いことを感じるのでございます。
たいていの三味線彈きは、左が利くか、右が利くかでありますが、廣助さんは兩手が利きました。團平さんもさうであつたと承りますが、それで左でハジクところ、たとへば「太功記」十段目の操のクドキの内の「現在母御を手にかけて」の、て--のゆりのしまひの合チレチンチンチンのチレがさうですが、これが廣助さんは誠に綺麗でありました。現今私どもも彈いてをりますこの合の手は、廣助さんの彈かれた手なのでございます。
お話は盡きませんが、ともかく廣助さんは、團平さんにつゞく近世の名人でお有なされたと存じます。(つゞく)
鶴澤叶聞書 文藝春秋 第十一巻八號 1933.8.1 pp 60-67
ある時御靈文樂座から、廣助さんのお供をして歸つたことがありました。その途中のことでした。
廣助さんは、その頃博勞町の三休橋筋東へ這入つたところにお住ひでした。淸六師匠の宅は博勞町稻荷の西門を北へ入つたところにあつて、私はそこへ歸りますので、文樂座の歸りがけに、樂屋口で廣助さんにお目にかゝつたりいたしますと、「お前も歸るのやつたら、ついておいで。」
と仰つしやることが、よくありました。若年の私は、それを光榮に思つて、御一しよにお供して歸るのでありました。
その日も、文樂座を出て、ブラブラ座摩の前筋を南へ歩るいて參りました。何でもまだ寒い時で、二月頃だつたと覺えてゐます。恰度本町の少し手前まで參りますと、路上に葱が一本落ちてゐました。大方八百屋の車からでもズリ落ちたものでありませう。青々と新鮮な色をしてゐるのです。
廣助さんは、それを見つけられると、「これこれ鶴五郎、あれを拾ひ。」
と仰つしやるのです。 私は内心「えツ」と驚きました。その時私は十八九歳であつたと思ひますが、色氣のつきはじめで、おしやれの一つもしたい年頃でしたので、そんな極りの惡い、人通りのある中で、地べたに落ちてゐるものを拾ふなんて、思ひもよらぬことでした。私が逡巡してゐるのを見られると廣助さんは、
「あのまゝにしといたら、人や車が踏んですたつてしまふ。勿體ない。拾ふといで。」
と仰つしやいます。仕方がないので思ひ切つて、顔を赤くしながら私はその葱を拾ひました。そして、それを持つて廣助さんのお宅までお供しますと、廣助さんは、「それ、勝手へまはしとき。」
と仰つしやいますので、お臺所へ置いて歸りました。
あとで實家の父に、この話を致しますと、
「さうか。やつぱり廣助さんは偉いお人や。ものの冥加といふことをお前に敎へてゐやはるのやぜ。藝の上でも同じことや。廣助さんの藝には無駄がない。廣助さんがいつ三味線彈きやはつても、見物がワツと云はぬことあれへん。お前も見習ひや。」と父はしきりと感心して、私に云ひ聞かせるのでした。
その時分、文樂座で一番怖いお人は廣助さんと、表の渡邊さんとでした。このお二人に叱られることは、私どもの首にかゝはる問題なのでありました。しかし、よく叱られました。叱られた記憶なら、いくらでもございます。
こんなことがありました。ある時大雨で、閉場(はね)まで手傳ひに居殘る私ども若い弟子連の歸る時刻には、外へ出るにも出られないやうなひどい降りになりました。お師匠さん方は俥でお歸りになりますが、私ども若い者は勿論そんなわけには參りません。雨はだんだんひどくなつてきます。それで渡邊さんのお計らひで、その晩若い者一同文樂座で泊ることになりました。前にも申上げましたが、その頃文樂座は午前七時開幕、午後七時閉場(はね)といふことになりまして、三番叟の始まるのは午前六時半ごろ。私どもはそれまでに出勤しなければなりません。さういふわけで、一つは泊れといふことになつたのであります。
そのうちに渡邊さんも歸られます。座からは煮〆と酒が出ました。座に殘つたのは十八九から二十四五歳までの、三味線彈きと太夫の卵どもばかりが二十幾人。誰も怖い人がゐなくなつた氣安さから、だんだん調子に乘り出して、煮〆を肴に、飲めや唄への亂痴氣騷ぎをはじめました。平土間の枠をはづして陣取つてゐましたので、果ては舞臺へあがつてスタコラ踊り出すものもあるといふ始末でした。これがいけなかつたのです。翌朝このことが渡邊さんに聞こえて、渡邊さんが廣助さんにお話しになつたものですから、そのまゝでは濟みません。一同廣助さんの前へ呼びつけられて、
「お前ら、舞臺を何と心得てゐるのぢや。」
と叱りつけられ、即座に閉門を云ひ渡されました。お詫びが叶ふまで、五六日一同文樂座出勤を差止められたのであります。鶴澤三次郎さん(今の三造)鶴澤花勇さん(今の勇造)、豐澤龍之助さん(故人)など、その仲間だつたと覺えてゐます。
私どもの叱られた話はまだまだございますが、廣助さんに叱られたのは私ども若い者ばかりではありませんでした。淸六師匠にも、こんな話がございます。
日淸戰爭の凱旋祝ひで、市中は踊りが出て、「ヱライヤツチヤ、ヱライヤツチヤ、」と騷いでゐる最中のことでした。文樂座に「千本櫻」の道行が出でゐまして、師匠は二枚目を彈いてをられました。その時の太夫は豐竹綾太夫さん、三味線はシンが二代目鶴澤叶さん--北の新地のお師匠さんと申上げたお方、通名金照さん--二枚目が淸六師匠、三枚目が當時鶴澤大造、今の友治郎さんであります。師匠はまだ鶴太郎と申されました。その頃師匠には、南地九郎右衞門町の淀龜席の藝者で、龜龍といふ深間があつて、龜龍は頭のものから帶止めまで、師匠の紋の丸にちがひ鷹にするといふのぼせ方、師匠の方も並ひとゝほりではないといふ仲でした。私もその關係で、この龜龍(ひと)には可愛がつて貰ひました。
ある日、淸六師匠は文樂座を無斷缺勤されました。師匠の替りは大造さんが勤められました、ところが惡いことは出來ないもので、その晩廣助さんが街の賑はひを見に出られて、戎橋を南へ渡らうとなさると、向ふから淸六師匠が縮緬の長襦袢に、頰被りで、その龜龍さんを連れて、「ヱライヤツチヤ、ヱライヤツチヤ。」と踊つてくるのに、橋の上でバツタリ出會はれました。「これツ。」と廣助さんが仰つしやいます。吃驚した淸六師匠は「ヘヱ。」と云つたまゝ、跡をも見ずに一目散に逃げ出されました。そのために師匠は、翌日から閉門になられました。
師匠が缺勤された日には、大造さんは師匠の替りを勤められて、廣助さんから「お前は感心ぢや。」と褒めて貰はれたさうですが、四五日すると、その大造さんがまた默つて座へ顔を見せられません。せつかく褒めて貰つた大造さんも、これまた閉門でした。
三代目越路太夫さん(當時さの太夫)も、その頃閉門組のお仲間でありました。廣助さんの仰つしやることは鶴の一聲、誰も違背することは出來ませんでした。名前はあづかりますが、廣助さんがお叱りになつて「豐澤廣助御禮申すツ。」と仰つしやつたので、「ヘヱ。」といつたまゝ、その場にへたばつてしまつたお人がありました。廣助さんは、そのくらゐに權式がお有になつたのでございます。
これは少し後のことでしたが、この廣助さんに向ふて、一と理窟申上げた勇敢なのが一人ありました。鶴澤才六さんと申して、當時たしか二十二三才ぐらゐだつたと思ひますが、いたつて剽輕者で、人の顔を見ると「るりんかるりん、ピツピツピツ、」なんてなことを云つて、おひやらかしたりする面白い人でした。或る時も、若い連中が何かのお叱言で、廣助さんに呼びつけられて、恰度私がこの人のうしろに坐つてをりますと、才六さんは「へーい。」と云つて頭を下げながら、ソツと片方の足の爪さきを、うしろで頭を下げてゐる私の顔のところへ持つてくるのです。可笑しくても笑ふことは出來ず、その時は困りました。そんなことをして喜ぶ人でした。
或る時、廣助さんが、才六さんが役の時のほかちつとも座にゐないのを咎められて、
「ちつと芝居を手傳ふて、もつと聽いて勉强せないかんやないか。」
と仰つしやいますと、才六さんは、
「そんなことしてられまへんね。」
といひます。
「なんでや。」
「そんなことしてたら、こゝが養はれしまへんがな。」
才六さんはかう云つて、頤へ手をやつて、ぐいと上へ突きあげて見せました。連中の稽古をして生活費を稼がねば、やつてゆけぬといふ意味なのであります。これには廣助さんも、
「さやうか。」
と仰つしやつて苦笑されたゞけで、別にお叱りはなかつたさうです。才六さんは私どものゐるところへやつてきて、
「どや。わいは松葉屋のお師匠はんを一本參らしてきたぜ。」
と自慢しながら、その話をするのでした。私どもは皆「ヘヱー。」と云つて、その話には感心したものでありました。實際こんなことを廣助さんに申上げたのは、あとにもさきにも才六さんひとりでございませう。恐らく廣助さんは、才六さんの剽輕な、毒のない氣質を愛しておいでになつたのだらうと思ひます。その後は廣助さんも、このことには、皆にもあまりお叱言は仰つしやらなくなりました。才六さんは後年に朝鮮で亡くなりました。
しかし廣助さんは、お嚴格ななかにまた温いところがお有になりました。やかましく仰つしやる一方に、可愛がつても戴きました。私が鶴五郎から、四代目鶴太郎になりました時には、改名祝に廣助さんは五十錢包んで下さいました。私は長いあひだ、それを神棚へ供へておきました。
廣助さんは、幼名を豐澤豐之助と申され、京都のお生れで、陸奥茂太夫さんの御子息であります。天保十五年道頓堀若太夫芝居へ初めて出座されました。三代目豐澤廣助さんの門人で、三代目の沒後は四代目廣助さんの預り弟子となられました。嘉永のはじめ豐澤富助となられ、同七年淸水町濱文樂芝居で「出世太平記」を勤められ二代目豐澤猿糸となられました。明治元年より竹本咲太夫さんを彈いて文樂芝居へ出勤され、咲太夫さんの物故の後、同三年七月五代目豐澤廣助を襲名いたされました。
その後諸所に出勤されましたが、明治八年から松島文樂座へ出勤され、中頃しばらく休座されたのと、同十七年一月からこれもしばらく、いなり彦六座へ出勤されたことがありましたほかは、同年九月、文樂座が松島から御靈境内へ移轉して開場すると、同時に復歸されて以後、引つゞき晩年まで文樂座に出勤されたのであります。長らく攝津大掾さんをお彈きになつてゐられました。たしか法善寺の津太夫さんを彈かれたのが、しまひであつたと覺えてをります。
明治二年、廣助さん壮年の頃、堀江の芝居で竹澤彌七さんといふお人が大三味線を彈いて人氣をとりました。これを聞いて廣助さんは、何を小癪なとばかり、その向ふを張つて、二貫目もある釘貫で「阿古屋」の三曲を彈かれて、溜飲を下げてゐられましたが、そんなことをするのは邪道だとあつて、廣助さんは因講から除名せられなさいました。それが團平さんのお仲裁で、やうやう元どほりになられたのだと聞いてをります。
さきに申上げた文樂座の表の渡邊さんは、渡邊幸次郎さんと申上げて、文樂座の支配人でお有でした。大勘定はその頃は池上さんと申すお方でした。
渡邊さんは表に坐つておいでになつて、いつも、ジツと太夫や三味線の舞臺を聽いてゐられるのでした。そして私どもが舞臺を疎かにするやうなことがありますと、すぐ表へ呼ばれて、
「あんた今なに彈いてたんや。あんなこと彈くやうやつたら、あすから芝居へきて貰はれへん。」
と極めつけられます。渡邊さんは藝の方のことがお委しくて、仰つしやることに間違ひはないので、言葉を返すことは出來ません。
「えらいすんまへんでした。あすからシツカリ勉强しますさかい--」
「勉强しとくなはるのやつたら、それでよろしい。」
といふ風で、若い三味線彈きや太夫が表へ呼ばれるのは、たびたびのことでした。「表から呼んでゐやはる。」と聞くと、皆ヒヤリとしたものでありました。
しかし、いつでしたか、竹本綾太夫さんの「新吉原」で、鶴澤勝右衞門さん--後に六代目淸七さん。今の綱造さんの父--が彈いてゐられた時、ある日勝右衞門さんが休まれたので、私が替りを勤めました。その時渡邊さんは「けふは、よう出來た。」と褒めて下さつて御褒美を呉れられました。
昔は、文樂座の表にも、こんなお方がおゐでになりました。
三代目越路太夫さんが、さの太夫の頃--さの太夫さんは、もう立端場(立者の語り場の端場)や附物(切に附けられる語り物)を語られる立派な太夫になつてゐられましたが、毎日、お師匠さんの攝津大掾さんのお宅へ御機嫌伺ひにおいでになると、いろんな走り使ひを云ひつけられなさつたさうです、豆腐を買ひにまでゆかれたさうです。
ある時、渡邊さんが大掾さんのお宅へ行き合はしてゐられて、この體を見られて、
「お師匠はん。もうあれだけやめはらんと、賣ものゝ太夫に花がないやうになりまんがな。」
と云はれますと、
「いや、あれはまだ一人前の太夫になつてまへん。そんなことを云ふて貰ふと、あれの藝が行きどまります。どうかそんなこと云はんといとくれやす。」
と大掾さんは仰つしやつたさうです。お師匠さんには、それだけのお考へがあつてのことであつたのであります。
團平さんは、御用事のない時は朝早く、大序の始まらぬさきから芝居へおいでになつて、子供たちの大序を彈くのをお聽きになりました。そして違ふたところがあると、「あすこは違ふ。かう彈くのんや。」と親切にお敎へになりました。時には、いくら仰つしやつても、むつかしくて、とても子供には彈かれぬことまで、熱心に云ふてお聞かせになりますので、或る時も、傍らにゐた少し年のいつた者が、
「お師匠はん。そんなこと子供に云ふて聞かしやはつても、わかりまんやろ。」
と申しますと、
「いやいや、さうやない。今はわからいでも、子供の時に聞いたことは忘れへん。あいつらが年がいつたら、ホンにさうやつたなアと思ひ出して呉れる。」
と團平さんは仰つしやつたといふことであります。
「おぼえられたか。」
「あかん。君は?」
「おぼえられへん。」
「なんせ、こゝやと思ふてると見物がワアと云ふよつて、あとの節がわからんようになるねやがな。」
「そんなこと云ふたかて、しやうあれへん。」
「チヨツ、あかん。」
舞臺では攝津大掾さんが、「中將姫」の雪責めの段を語つておいでになります。三味線は五代目廣助さんでした。舞臺裏で、先代南部太夫さんと私は、大掾さんの節を覺えるため、朱を入れながら毎日こんな會話をくり返すのでした。
〽ヤレヤレ心なの下部やな。きのふまでも今朝までも、痛はりかしづく身なりしに、淺間しや今日はまた、我を責むるか悲しやと、--
この「きのふまでも今朝までも」の大掾さんの節まはしが、なかなか覺えられません。たゞでさへお師匠さんの節は、こまかくて覺え憎いのに、こゝへくると、毎日きまつて見物がワアと云ふので、お師匠さんのお聲がよく聽きとれません。しまひに南部さんは、大掾さんの淨るりを喝采する見物衆を憎むのでありました。
舞臺裏は、私たち二人ばかりでなく、聽き手で一杯でした。少し遲くゆくと坐る場所がありませんでした。
「もう場所あれへんぜ。」
「そない云はんと、どこぞへ入れてヱな。」
さう云つて賴んで割込まして貰ふといふ有様でした。舞臺裏のこんな盛況は、今の文樂座では、あまり見受けられぬ風景でございます。
淨るりは音聲だけのものではございません。聲量に乏しくても「情」を語るといふ修業がございます。二代目竹本義太夫さんはこの情語りの名人であつたと承ります。
二代目義太夫さんは、初代義太夫さんの門人でありましたが、師匠義太夫さんが「お前のやうに小音では、とても太夫を勤めることは覺束ない。」と申されたので、仕方なく師匠のもとを離れて若太夫芝居へ入座され、小音であつて人を惹きつけるには情を語るに若かずと發心して、工夫を凝らされたのでありました。後年に師匠義太夫さんが、その淨るりを聽かれて、痛く感心なされ、西の芝居へ呼び戾して二代目義太夫の名跡をお讓りになつたのだといふことであります。
二代目義太夫さんは、幼名若竹政太夫、晩年に竹本播磨少掾になられ、本名を中紅屋(ちゆうもみ)長四郎と申されました。播磨少掾の門人、順四軒といふお人の聞書に、次のやうに書遺されてございます。
播翁師つねづね申されけるは、我長四郎の昔、小音なるゆゑ芝居はつとまるまじと筑後翁(初代義太夫)申されけるとき、つらつらおもふに音聲の大小は人の生れつき也、音曲の事は世話のたとへにも聲なふて人をよぶと云ふ事あり、生れえたる調子をはづれ語れば脾胃をそこなひ、調子律に叶はず應ぜざれば人感ぜず、音聲は師匠よりはるかにおとりしは生れ付きなればぜひもなし、音は銘々の音あり、音をもつて人情の喜怒哀樂眞實に語らば小昔なりとも人の感心せぬ事あるまじ、工夫して語りしと申されしが、成ほど人感心したりと見えて播翁師の出なされると手習子供の無言をまもる如くしづまりきゝ入けるゆへ芝居の外までも聞こえしなり。
順四軒と申されるお人は、お素人で、順慶町四丁目に住んでゐられたのがお名前の由來であるさうです。(つゞく)
情を語ると申しますのは、役々の性格を語りわけ、喜怒哀樂の情を眞實に【その役のこゝろになりきつて】語るといふことでありますが、近世で、私の存じてをりますのでは、五代目の竹本彌太夫さん--この間亡くなられた彌太夫さんの、もう一つ前の木谷の彌太夫さん--がこの情語りの名人でありました。お聲は惡聲と申上げねばなりませんでしたが、情のよろしかつたこと何ともいへませんでした。それはうまいものでありました。
中年から惡聲になられて、情を語るといふことに辛苦して御修業なされたのだと承りますが、澁い、寂びた、まことにうま味のある淨るりでした。それに三枚目のチヤリがまた實に輕妙で、よろしうございました。
私がはじめてお會ひした頃は、彦六座の閉座以後舞臺を引退されて、お素人の連中さんのお稽古をしておいでになりました。彌太夫さんは御裕福でしたが、お稽古は懇望されて老後の樂しみになさつておいでになるのでした。その頃【私】は北の新地の紅雀(こじやく)さん(平鹿樓先代の主人伊藤淸助氏)に御贔屓になつて彈かして戴いてをりましたので、紅雀さんのお供をして、よく彌太夫さんの初會(はつくわい)(連中の年はじめの會)や、納會(年末の會)に出ました。その當時、紅雀さんは彌太夫さんの連中さんでした。紅雀さんのほか、高麗(こま)五さん、北の新地の一聲さん、天滿の三木(ぼく)さん、うつぼの一俵さん、後に二代目の閑多になられ麟鳳さん、一秀軒さん、北の長池の雷鬼さん、千倉さん、壽鶴さん、十三さん、松壽さん、かつらさん、かなめさん、一寳さん、それから三木さんの息子さんの魚勢さんなど、當時大阪のお素人でも名だたるお人がお稽古に見えてをりました。
彌太夫さんは、堀江にお住ひでしたが、お稽古場は【北船場の】淀屋小路を魚の棚へ出るまでの南側常吉八郎兵衞さんと申すお宅になつてゐて、そこへ御出張なさつておいでゞでした。常吉さんは淨るりの俳名を楚雀さんと申し上げました。
私が彌太夫さんの連中さんの會へ出るやうになつたのは、明治三十一年頃からで、私の二十歳ぐらゐの時でした。--明治三十二年に私は二代目鶴澤鶴五郎から、四代目鶴太郎になりました--その頃は堺卯樓とか、備一樓とか、一流の料亭が、お素人の淨るり會に座敷を貸したものであります。
彌太夫さんの連中さんの一寳さんと申すお方は、その頃御靈さんの東門の前にあつた

といふ足袋屋さんの御主人で、本名を山田利兵衞さんと申されました。彌太夫さんの會でちよいちよいお會ひするうちに、「鶴太郎はん。ちつとわしも彈いてくれへんか。」といふやうなことから、その後私は一寳さんに御贔屓になり、一寳さんを彈いてよく順會(月並會)へ出るやうになりました。
一寳さんは大の彌太夫さん崇拜で、呼吸(いき)の使ひ方から、聲の出し方まで、彌太夫さんソックリに演られるので、會に出られると、なかなか人氣がありました。當時、天滿に彌生(やしやう)軒といふお素人の立者がゐられて、「壼坂」と「大文字屋」が十八番でしたが、殊に「壼坂」は有名でした。ーそれは本家の三代大隅太夫さんを凌ぐ位に人氣がありました。私もたびたび、彈かして戴きましたが、澤市が「おゝ、お里か。」と云ふと、もうそれだけでスッカリ盲目になつてゐました。「ほんにこりや眼があいた。」と云はれると、それこそ本當に眼があいたやうにきこえました。實際澤市だけは玄人もおよぱぬ老巧なものでありました。ある時も彌生軒さんの本が、新しい綺麗な本でしたので、「サラだんな。」と私がきゝましたら「鶴やん。これで六冊目や。」と仰つしやつたことがありました。彌生軒さんは、所望されて方々で、何べんとなく「壼坂」を語られるので、ちつとも本は見ずに、眼をつぶつて語られるのですが、そんなに本が傷むのでした。--その彌生軒さんが、出合ひの會で「ドツサリ」を語られ、一寳さんが「モタレ」で「伊賀越」の岡崎を出されると、それが見物の喝采をスツカリさらつてしまふので、彌生軒さんの出し物が、お得意の「壺坂」や「大文字屋」などでない時は、あとへ出て語りにくいと云つて、顔の下の一寳さんの「岡崎」をいつも怖がつてゐられました。一寳さんの「岡崎」は、彌太夫さんがミツチリお仕込みになつたゞけに、實際立派なものでありました。
一寳さんの三味線を彈くやうになつてから一寳さんは彌太夫さんに習はれたものをよくお演りになりますし、私は文樂座の方でしたから彌太夫さんの風と違ふところがあつて、時々合はぬことがありますので、それを勉强するため、彌太夫さんのお稽古を聽かして戴きに、私は常吉さんのお宅へあがるやうになりました。
初會や納會ではお顔を合はしてゐましたが彌太夫さんのお稽古を聽かして戴いたのはこれがはじめてゞした。
彌太夫さんは當時、六十一二の御年配で、小柄でしたが、品格のある、ものしづかなお方でありました。
【はじめて彌太夫さんのお稽古を聽きに常吉さんへ伺つた時のことです。】
常吉さんのお宅は、しもた家で、廣い、靜かなお家でした。
私がまゐりました時は、五六人連中さんがきてゐられて、なんでもその翌晩に會があるので、皆さんが一段づゝ、彌太夫さんにさらへて貰つてゐられるところでした。
恰度、「大文字屋」のお稽古がはじまつたところへ行合はせましたので、マクラのオクリから聽きました。彌太夫さんは危なつかしい三味線を彈きながら、連中さんの淨るりを直すために、御自分でそこを語つて聞かしておいでになりました。彌太夫さんの「大文字屋」は、私がそれまでに聽き馴れたものとは、よほど風が違ひます。が、何といふうまい淨るりでせう。私は吃驚いたしました。そして、いきなり彌太夫さんの淨るりに惹き入れられてしまつたのであります。
彌太夫さんの「大文字屋」は、マクラの「ハルブシ」の音の出端からして、聲づかひが違ひます。
〽すでに日もくれ飯焚が、灯す勝手の八方に、十方うしなふ氣はくらやみ。--
この「すでに」の「す」は普通は上から出るのを、彌太夫さんは、「す--ウ」と下から忍んで出て、上へもつてこられます。
〽心にもないわんざんを、いふも榮三が算盤の、桁をはづれて門口の、大戸おろせど落付かぬ、胸の算用とつ置つ、--
この「胸の算用とつおいつ」の間がまた違ひます。大戸をおろしに行きかへり、胸の算用に栄三は心も空といふ思ひ入れで語られます。
〽思案の中戸に人音して、萬屋の手代忠兵衞、上り口に手をつかへ、
で、忠兵衞の口上のキツパリと氣持を替へた輕さ。引かへてまた、舅助右衞門の思ひ遣りから離緣(さら)れて歸る妹お松の、シツトリと沈んだ憂ひの思ひ入れと、まだおぼこな、初々しい若嫁ぶり……
〽--いふうち門へ提灯の、かげも心もかきくもる、お松といへど色かはる、顔は辛苦におも痩せて、しき居も高き兄の内、供のでつちやこしもとも、氣の毒さうにしよぼ/\と、--
この「氣の毒さうに」の前、こしもとも……とちよつと間をおいて、供の者のお松への同情を强く利かすなど、寸分のスキもありません。
榮三の詞がまたよろしい。榮三は町人ながら柔術(やはら)の心得もある人、それで町人の氣分のうちにも何處か强いところがあつて、サラサラした調子--夫助六の難儀を救ふため、お松に新町へ身賣りをすゝめるくだりの「世間の口よりこの榮三が胸が、どうも濟みにくい」この詞が何とも云へぬほどよろしうございました。
母親がよろしい。助右衞門がよろしい。殊に助右衞門は、輕い詞のうちにも、大家の御隱居さんといふだけの品格がチヤンと具はつてをります。彌太夫さんは、榮三、お松、母親、助右衞門、とキツパリ語り分けて聞かされます。
それから奥の「題號(だいご)」のところ、こゝは御存じのとほり傳九郎と權八の兩人が、内そとに諜し合して、お松を盗み出し「くはへて退いて腹存分樂しんだ胴がらは約束の通り京へ賣り云々」といふ惡計から、助右衞門を送つていつた榮三の留守を見はからひ、格子先へ忍んできた傳九郎が、首尾はいかにと權八へ合圖に題號をとなへるところですが、その輕妙なこと、彌太夫さんの「題號」は神品と申すほかございませんでした。とてもその通りにはやれませんが、ちよつと、かういふ呼吸でした。人形は、傳九郎は頰被りして、彌造をきめこんでゐますが……
(話者、傳九郎のこゝろで、彌造をこしらへ、少し首をすくめて「題號」を語る。こゝは三味線のないところ。
〽妙法蓮華經、申すも愚や祖師日蓮大菩薩、龍の口にては太刀の下に直り給ひ、又或る時は、佐渡が島に流され給ひ、難行苦行なされしも彼の一物をせしめん爲の御誓願なり。なむ妙。--
このあひだ、始終あとさきに氣を配ることなし。
「彼の一物をせしめん」のところでは、「せしめん」の「ん」を「んンンンン……」と引きながら、その間に合はして、のびあがつたり、かゞんだりして内の様子を透し見また振り向いてうしろを窺ふこなしをします。
〽りんはなけれどさえわたる、法華の題號相圖と見え、内よりくゞりそつと明け、
「傳九郎きたか。」
「權八、首尾は。」「まぶぢや、まぶぢや。」(よいといふ意味)
これは、いかにもあたりを憚るヒソヒソ聲でした)
とまアいつたやうな風で、こんな私の語るやうなのではなく、全く息もつけさせぬほどうまいものでした。今でも耳に殘つてゐます。私はたゞ夢中で聽いてをりました。彌太夫さんは憂ひが利いてチヤリがまた無類です。私はそんな「大文字屋」を、それまで聽いたことがありませんでした。全く頭が下りました。そして私は、それ以來スツカリ彌太夫さん崇拜になつてしまつたのであります。
「大文字屋」のあとに、たしか「引窓」と「岩井風呂」と「新口村」のお稽古があつたと覺えてをりますが、あとのお稽古も聽かして戴いて、私はいよいよ彌太夫さんに敬服したのでありました。
その内、連中さんは皆お歸りになつて、私は彌太夫さんと二人きりになりました。私には「大文字屋」の感激がまだ消えません。
「お師匠はん。えらい失禮なことを申上げまつけど、お師匠はんの大文字屋は誰方はんの型でんね。こんな大文字屋、わては始めてだす。」とお尋ねしますと、
「これは師匠長門はんの型や。」
と仰つしやいました。なるほどよろしいも道理、中古の名人三世竹本長門太夫さんの型であつたのでした。若年の團平さんを登用して御自分の合三味線になさつたのも、河堀口(こぼれぐち)の大師匠と申上げたこの長門太夫さんでありました。私は今日になつて、彌太夫さんの偉さを、さらにまた長門さんの偉さを、一層しみじみと感じるのでございます。少し後のことでありましたが、彌太夫さんにお願ひ申上げて、「大文字屋」の五行本を拜借して、朱章を寫さして戴きましたが、その御本の表紙裏に左のやうな書き入れがしてありました。
此本章附ハ安政三年丙辰五月五日ヨリ初日、
大阪西横堀文樂芝居ニテ、
師匠三世竹本長門太夫
三世鶴澤淸七
相勤メラレ其節大當リセシナリ
是寫也五世竹本彌太夫
寫させて戴いた本は、今も大切に保存いたしてをります。
それからは、私は繁々とお稽古場へよせてもらふやうになり、いろいろのお稽古を聽いて、勉强さして戴きました。聽かして戴いたものは澤山にございますが、覺えましたのは「大文字屋」「伊賀越岡崎」「沼津」「彌作鎌腹」「赤垣出立」「双蝶々橋本」「沓掛村八藏内」「双蝶々引窓」「紙治茶屋」「道明寺」「岩井風呂」「どんぶりこ」「肉附面」などで、私も連中さんにお稽古いたします時は、及ばぬながらも、以上のものは彌太夫さんの風をお傳へしてゐるのでございます。
彌太夫さんの語り物の一つ一つについて、よろしかつたところを申上げれば、いくらでもお話はございますが、彌太夫さんは情を語るといふことでは、わけて申上げれば世話物と、時代物でも世話がゝつたものにかけては近世稀なる名人でお有になつたのでございます。
「大文字屋」の題號の前のところ、
〽四方に人音かすかなる、折を見合す格子先。合、妙法蓮華經--
こゝの合の手は、普通それこそ百人が百人まで、
チリリン、リン、リン、リン、リン、リン、リーン、シヤン、シヤン。
と彈いてゐます。りんの音を利かしてゐるのです。
ところが彌太夫さんは、一で、
ジヤジヤン、ジヤン
とだけ彈かれます、そして、「鶴やん。こゝはこない彈くのがほんまやぜ」
と仰つしやるのでした。
私は吃驚いたしました。何故なら、そのことは私もかねて五代目野澤吉兵衞さんから敎へて戴いてをりました。こゝは本當の行者ではなく、傳九郎が偽行者になつてゐるので、本文にも「りんはなけれどさえわたる」とあるのだから、チリリンリン……はよくないと懇々云ひ聞かされてをりました。その時吉兵衞さんが見せて下さつた松屋淸七さんの朱入の御本にも、ジヤジヤン、ジヤンと朱がはいつてをりました。しかし普通には大抵さうは彈いてをりませんのに、彌太夫さんは太夫さんでゐられるのに、そこまで三味線のことも心得ておいでになることを知つたからであります。偉いものだと思ひました。
その後さるお方が祕藏してゐられた西宮の初代鶴澤勝七さんの御本を頂戴して、私は所藏してをりますが、それにも同じ朱入がしてあります。
名人と申上げるほどのお方は皆、理前の合はぬことは彈きも語りもなさらぬものと感心いたしてをります。
その頃の彌太夫さんの連中さんが、彌太夫さんを尊敬してゐられたことは非常なもので一にも二にも、お師匠さん絶對主義でありました。
ある時、會で、麟鳳さん--後に二代閑多さん--の「赤垣」德利酒を彈きましたが、すんでから麟鳳さんが、
「鶴やん。玄關前(げんくわんさき)のとこは、もつとバタバタツと彈いて貰はんと合へへんぜ。」
と仰つしやいます。
〽--その醉ざめの水ならねど、この降る雪の面白味、下戸は何と見るで有ふ。や、こいつは酒呑でなきやわかるまいハハハハい。とひとりごとしてひよろひよろ、直(すぐ)なしの字の道さへも、くの字に歩む、合、玄關さき。
この玄關さきのところを仰つしやるのです。ここは私は彌太夫さんの御本から、三味線の朱も寫さして戴いてをりまして、
ツントンツン、テツツン、トツントン、ツツントン、ツトン、トン、トン、トン、トン、トン、
と彈いてをりますので、それより彈きやうがないのです。ところが、いくらさう申上げても麟鳳さんは聞き入れてくれられません。
「いゝや。お師匠はんは、もつとバタバタツと彈きやはる。そない彈いて貰はんと合へへん。」
「そない云やはつたかて、これより彈きやうあれしまへんねやがなア。」
その日は押問答でをはりましたが、翌る日お稽古場へ參りまして、彌太夫さんの前で、麟鳳さんと二人でそこを合はして聽いて戴きました。彌太夫さんはそれをお聽きになつて、
「鶴やんの彈くとほりでえゝのや。わしは手が廻れへんさかい、そない彈かれまへんのやがな。そのとほりに彈けいふたかて、そりや無理や。ハハハハハハツ。」
とお笑ひになつたので、やうやく麟鳳さんも納得されました。彌太夫さんは、手がお廻りにならぬところを、無理に間だけ付けて三味線をお彈きになるのを、麟鳳さんはその方がよいのだと思ひ込んでゐられたのでありました。今は故人になりましたが、その頃やはり麟鳳さんを彈かして貰つてゐた野澤吉松さんも、時々これには弱つてゐました。
それほどに連中さんの彌太夫さん崇拜熱は高かつたのであります。
これは彌太夫さんの藝と御人格の力によることではありますが、連中さんのお師匠さんに對するお心持も、まことに床しく感じられるのでございます。
しかし、その彌太夫さんもまた、お師匠さんの三代目竹本長門太夫さん--天保十四年國名を名乘ることを禁ぜられてからは長登太夫さんと、申上げる--を非常に崇拜しておいでになつたのであります。
彌太夫さんが、まだ師匠長門太夫さんの白湯汲みをしながら、お師匠さんの淨るりを聽いて本に朱を入れてゐられた御修業中のことでありました。ある時、長門さんが意氣込みのハズミで、痰拭きの裂を、床からポンと下へ投げられました。下にゐられた彌太夫さんは、それをソツと懷に入れて家へ持つて歸られ、その痰拭きをお祭りして、それからは毎日それを禮拜して、「どうか師匠ほどの名人にして下され」と祈られたといふことであります。
彌太夫さんが亡くなられたあとで、皮文庫の中に、汚れた、手拭ひのやうな古裂が大切に藏はれてあるのが發見されましたが、誰ひとり、その古木綿の裂の素性を知つてゐる者はありませんでした。後年彌太夫さんの日記によつて、それが長門太夫さんの痰拭きであつたことが、はじめて解つたのでありました。
彌太夫さんの御親父は、道具屋、髪結、湯屋などの株を持つてゐられたお人で、大の淨るり好きであつたところから、十歳にも足らぬ彌太夫さんに淨るりを仕込まれたのでした。そしてそれは嚴格を極めたものであつたさうです。」
十一歳の時、三代目長門太夫さんの門人になられたのでありますが、覺えが惡いと云つて御親父が彌太夫さんを風呂場へつれていつて、逆さまに湯槽の中へ頭を突込んだりされました。はたにゐる浴客が見るに見かねて仲裁する、そんなことは一度や二度ではなかつたさうです。
彌夫夫さんもこれは忘れられなかつたと見えて、日記にこのことを書いてゐられるさうです。また十五歳の時の日記には、
しんの闇見えも恥をもいとはずして
稽古場二階にひとり泣くらす
と歌を書いてゐられます。
しかし辛苦の效は空しからず、子供太夫の竹本小熊太夫は長門太夫さんの祕藏弟子でありました。十五歳の時、師匠と一しよに江戸に上り、彼地で竹本長子太夫となられたのであります。
彌太夫さんは、さきに申しましたやうに子供太夫の時分の名を竹本小熊太夫と云はれて嘉永年間から道頓堀竹田の芝居へ出勤されました。嘉永四年師匠三世竹本長門太夫さんと一しよに江戸に上られ、同五年歸阪されましたが、この江戸滯在中に竹本長子太夫と改名されました。
安政元年師匠長門太夫さんは文樂軒芝居の座附きとなられたので、長子太夫の彌太夫さんは諸所に出勤いたされました。元治元年三世長門太夫さんの歿後、四世竹本彌太夫さんの預り弟子となられたのでありましたが、明治元年四世彌太夫さんの亡くなられた後、その名跡を相續して五世竹本彌太夫となられたのであります。
明治四年より稻荷社内文樂軒芝居の座附きとなられ、松島時代から御靈時代初期の明治十九年まで文樂座に出勤いたされました。
その後引退休養してゐられた彌太夫さんは、明治二十七年に再興した第二次いなり彦六座に迎へられて、櫓下として入座なされました。しかし幾干もなく座主花里さんの失脚から、いなり座は經營困難に陥り、一時は彌太夫さん、大隅さん、團平さんのお三人が無報酬で出勤せられて、一座の維持に努められたこともあつたさうです。その後、團平さんの死につゞいて稻荷座の閉座--堀江明樂座での再起--明樂座から堀江座へ--この間に多少の消長はありましたが、文樂座に對抗して、後見役として稻荷座一派を率ゐ、彌太夫さんは具に經營の辛酸を嘗められたのであります。舞臺は稻荷座以後お勤めになりませんでした。
彌太夫さんは本名を木谷傳次郎さんと申上げ、今の木谷蓬吟さんの御親父であります。明治三十九年に七十歳でお亡くなりになりました。堀江にお住ひでしたので「堀江の大師匠」と申上げてをりました。
お得意の語り物は、私の聽かして戴いたのでは「菅原、道明寺」「菅原、佐太村」「義經腰越狀」「五斗」「伊賀越、沼津」「同、岡崎」「同、北國屋」「同、政右衞門屋敷」「同、新關所の段」「楠昔噺どんぶりこ」「忠臣藏四段目」「忠臣藏六つ目」「大晏寺堤」「勢州阿漕浦、平治住家」「二代鑑、秋津島内」「吃又」「花川戸」「双蝶々、橋本」「双蝶々、引窓」「大文字屋」「天王寺村、兵助内」「お染久松、めし椀」「帶屋」「新靱、八百屋」「岩井風呂」「赤垣源藏出立」「彌作鎌腹」「城木屋」「紙治茶屋」「戀女房、沓掛村」などでありました。
それからチヤリがよろしかつたことは前にも申上げましたが、彌太夫さん自作の滑稽淨るりが十二三種もございます。
お話の序に稻荷座一派のその後の成行きを申上げますと、明樂座を閉座した時から大隅太夫さんは文樂座へ入座されたので、堀江座は、頭梁を失つた若手の連中が背水の陣を布いて、孤城に立籠つたかたちだつたのであります。一座は竹本春子太夫さん、竹本伊達太夫さん(今の土佐太夫)、竹本長子太夫さん、竹本雛太夫さん、豐竹此太夫さん、豐竹新靱太夫さん、三味線は豐澤龍助さん、豐澤仙左衞門さん(後に三代目團平)、豐澤小團二さん、豐澤新左衞門さん、豐澤猿二郎さん(今の仙糸)、人形は吉田兵吉さん、吉田玉松さん、吉田簑助さん(今の文五郎)、吉田玉治さんといふ顔ぶれでした。一座の團結と奮闘とは大變に人氣を呼んで、文樂座以上といふ評判を取つたほどでありました。奮闘六年明治四十五年には有志の發起によつて、佐野屋橋南詰に【新築】創設された近松座に移り、文樂座から復歸した大隅太夫さんを迎へて華々しく開場したのでありました。これが只今の文樂座の建物の前身であります。その後大正三年まで興行をつゞけましたが、大隅太夫さんの臺灣客死、土佐太夫さんの文樂座入り、その他色々のことから遂に閉座の止むなきに至つたのであります。
只今の文樂座が引移るまで、長い間ビルデイングになつてゐて「何々事務所」「何々商會」の標札が入口に眼白押に並んで、昔を偲ぶ者に寂しい戚慨を起させてゐたのは御存知のとほりでございます。
只今の文樂も結構でございますが、以前御靈さんにありました時分には、床(ゆか)へあがりますと、いつもこんなことが思はれるのでありました。--御承知のとほり御靈文樂座には兩棧敷に二本づゝ太い柱が立つてをりました。それから後には天井を張りましたが、以前は天井がなくて、棟木や梁(うつばり)が下から見上げられました。床にあがりますと、この柱や梁が氣になるのでした。この柱や梁は昔から偉いお師匠さんがたの、立派な淨るりや三味線を浸み込むほど聽いてゐる。私の三味線を聽いて「あんなこと彈いてゐる」と冷笑してはゐないだらうかと思ふと氣がひけました。そして自づと緊張するのでした【。】誰が知らいでもこの柱や梁が知つてゐる。さう思つて一生懸命に床を勤めるのでありました。
私が覺えてからでも、三味線では松葉屋の大師匠(五代目廣助)、金照の大師匠(二代目叶)、二代目鶴澤勝七さん、五代目野澤吉兵衞さん、豐澤花助さん(後に勇造から文藏)、野澤勝鳳さん、鶴澤勝右衞門さん(後に六代目淸七)、鶴澤才治さん、名庭絃阿彌さん(六代目廣助)、豐澤小團二さん、私の師匠鶴澤淸六さんなどの大師匠がたがおいでになりました。特別に出勤なさつたのでは竹本播磨太夫さんを彈かれて、京都の五代目鶴澤友治郎さん、(通名建仁寺町)もお見えになつてをります。太夫さんでは攝津大掾さん、法善寺の津太夫さん、はらはら屋の呂太夫さん、大隅太夫さん、豐竹綾太夫さん、先代竹本相生太夫さん、竹本長尾太夫さん、九代目竹本染太夫さん、竹本むら太夫さん、竹本路太夫さん、六代目豐竹時太夫さん、竹本七五三太夫さん、三代目越路太夫さんなど、人形は初代吉田玉造さん、初代桐竹紋十郎さん、吉田玉助さん、吉田玉治さん、吉田金之助さん(後に多恵藏)、吉田玉五郎さん、桐竹龜松さんなどがおいでになりました。私の入座以前には五代目竹本彌太夫さん盲人の四代目竹本住太夫さんなどもおいでになりました。ほかにもまだまだおいでになつてをります。これだけのお師匠さんがたの心血が、あの御靈文樂座の「土」にそゝがれてゐるのであります。ですからあすこの「土」が、自然と、藝道の尊厳とでも申しますか、さういふものを感じさせるのだと思ひます。床に出る時の心の構へに何か別なものがございました。
舞臺を大切に勤める心には、今とても少しも變りはございませんが、御靈文樂座を囘顧いたしますと、あすこの「土」の貴さを考へずにはゐられないのでございます。
柱や梁を怖れる心持は、御靈文樂座では仕舞まで私はなくすることができませんでした。
九代目竹本染太夫さんの合三味線を勤めてゐた時のことでございました。大正二年二月十六日初日で文樂座は前狂言「義經千本櫻」大序より吉野山まで「渡海屋」は今の津太夫さん「鮨屋」は三代目越路太夫さん「川連法眼館」は染太夫さん、切狂言「鷓山古跡松」豐成館、中は竹本南部太夫さん、切は攝津大掾さんでありました。
恰度初日のことでした。「川連法眼館」で私は染太夫さんと一しよに床へ出ました。やがて前彈きがすんで染太夫さんはマクラを語り出されます。
〽園原や、はゝきゞならで有と見し、人の身の上いぶかしく、靜は君の仰せをうけ、
こゝで三味線は一の糸をトーンと彈いて受けるところです。ところが染太夫さんは一、二の音の開いた、朗々としたよいお聲でした。染太夫さんの淨るりは始終聽き馴れてゐるわけなのですが、この「靜は君の仰せをうけ」がまた何とも云へずよろしいのです。今更のやうに「あゝ、えゝ聲やなア。」と思つて聽き入つてをりました。
すると染太夫さんが小聲で、
「おい、彈きんかいな。」
と仰つしやるのです。私は染太夫さんのお聲にウツカリと聽き惚れて、「ウケ」を彈くのを忘れてゐたのでした。ハツと氣がついて慌てゝ、
トーン。
と彈いたのでありました。
樂屋へ這入つてから染太夫さんは、
「叶はん、けふはどないしたんや。」
とお尋ねになりましたので、
「えらい失禮しました。お師匠はんの、靜は君の仰せをうけのとこがあんまりよろしおましたので、お師匠はんのお聲に聽きとれてウツカリしてましてん。」
と申しますと、
「さうか。ハハハハハ」
とお笑ひになりました。
しかし、それからも毎日御一しよに舞臺へ出てゐて、そこのところを、いつも感心して聽いてをりました。いく度聽いてもよろしうございました。
それから奥の狐の忠信の詞。
〽今日國より歸つたる、誠の忠信に御不審かゝり、難儀となる故よんどころなく、身の上を申し上げる、始めはそれなる初音の皷、桓武天皇の御宇、内裏に雨乞ありし時、此大和の國に、千年功經る牝狐牡狐、二疋の狐をかり出し、その狐の生皮をもつて、こしらへたるその皷、雨の神をいさめの神樂、日に向ふて是を打てば、皷はもとより波の音、狐は陰のけだもの故、水を起してふる雨に、民百姓は悦びの、聲を初めてあげしより、初音の皷と名付け給ふ。其つゞみは私が親、私めは、其つゞみの子でござります。
これは人間でなく狐の詞ですから、狐の口調、狐の癖があつて、詞の長短がむつかしいのであります。染太夫さんはそれを誠にあざやかに語られました。
また奥の、
〽願ひ叶ふが嬉しさに、年月なれし妻狐、仲にもうけし我が子狐、不愍さ餘つて幾たびか、引かるゝ心を胴慾に、あら野に捨てて出でながら、あゝ餓ゑはせぬか、凍えはせぬか、もし獵人に取られはせぬか、我親をしたふほど、我子も丁どこのやうに我れをしたふかと、案じすごしがせらるゝは切つても切れぬ輪廻のきづな、愛じやくのくさりにつなぎとめられて、--
このあひだの憂ひのよく利いてゐましたこと、私は三味線を彈いてゐて、毎日のやうに舞臺で泣かされました。
今思へば偉い太夫さんであつたと、染太夫さんのことを憶ひ出すのでございます。
染太夫さんのこの四段目は四代目竹本住太夫さんの型と承りました。
染太夫さんは盲人の四代目住太夫さんの門人でしたが、住太夫さんの歿後は五代目彌太夫さんの門人になられました。登勢太夫から谷太夫になられ、そのあとで九代目染太夫となられたのであります。
攝津大掾さんのあとを襲ふて、三代目越路太夫さんが櫓下になられましたが、本當は顔から申せば染太夫さんがさきになられるのが順當であつたのでした。攝津大掾さんの御威勢と云ひ、當時花形であつた三代目越路太夫さんの御盛名から云へば座元の方針としても、それは致し方のなかつたことではありましたが、染太夫さんには御心中樂しまぬものがお有りになつたのであります。しかし大掾さんへの御遠慮から何事も仰つしやらずにおいでになつたやうに思はれます。
三代目越路太夫さんが、まだ櫓下になつてゐられなかつた頃のことでありますが、明治三十七年の十一月二十三日初日で御靈文樂座は前狂言が「加賀見山」切狂言は「心中天網島」でありました。「鶴ヶ岡草履打の段」は尾上、三代目越路太夫さん、岩藤、染太夫さん、善六、源子太夫さん(今の源太夫)の掛合でありました。初日前の皆の豫想は、今度は恐らく染太夫さんは越路太夫さんにクワレしまはれるだらうといふことに一致してをりました。當時油の乘り出した一騎當千の越路さんのことですから、これは無理からぬ豫想でありました。ところが蓋を開けて見るとそれがスツカリ逆でありました。藝の位といふものは何と申しても爭へぬもので、越路さんはまだそれだけお若かつたのであります。越路さんにはまた染太夫さんの眞似られぬところがありましたが、藝の重味では染太夫さんにその頃は一歩を讓られねばなりませんのでした。今にこの話は殘つてゐるのであります。後年の越路太夫さんが名櫓下でお有になつたことは異論のないところですが、たゞ私は、御在世中に染太夫さんが一度は櫓下になつておいでになつたら、定めて御本懷でお有だつたらうにと窃かに思ふのでございます。
晩年中風症を惱まれて舞臺を引退され、ずつと住吉に引籠つて御養生なさつておいでゞした。私も折々お見舞に參りましたが、或る時何かの話から、
「わしも紋下になれたのやが、--」
と、つと御感慨を洩らされたことがありました。何氣なく仰つしやつた風でしたが、いまだに私の心に殘つてをります。過ぎ去つたことを色々申上げましたのも、その當時の染太夫さんの御心境をお察し申上げる心からでございます。
舞臺を引退されたのは大正二年四月で、同五年二月十七日、六十四歳でお亡くなりになりました。讃岐の御出生で、本名を秋山瀧藏さんと申上げました。
私は大正二年一月、染太夫さんの「太功記」の杉の森を彈きまして、四代目鶴澤鶴太郎改め四代目鶴澤叶になつたのでございますから、染太夫さんは特に忘れられぬお方でございます。
初代古靱太夫さんが、座頭になつておいでになつた御靈さんの表門の土田の小屋で、一座の大工の棟梁梶德の兇手に殪れられたことは餘りに有名なお話でございます。委しいいきさつは私は存じませんが、古老の方々から承つた話から想像いたしますと、古靭さんの豪放に過ぎたお氣質と、梶德の狹量な一本氣が生んだ悲劇のやうに思はれます。梶德も事件後すぐに自殺したといふことであります。
しかし、古靱太夫さんは鬼才と申上げますか、全く名人でお有になつたといふことです。當時古靱太夫さん、織太夫さん(後に六代目綱太夫)、越路太夫さん(攝津大掾)のお三人が斯界の覇を爭はれる位置においでになつたさうですが、古靱太夫さんはそのうちでも尤なるものでお有になつたさうです。
明治三年十一月、いなり社内、文樂軒芝居に「加賀見山」が出ました時、七つ目のお初と尾上を越路さん(攝津大掾)と古靱さんが役を毎日交替して掛合で勤められました。古靱さんには喘息といふ太夫にとつては最も苦痛な持病がお有になり、聲量も有り餘るといふ方ではなく、越路さんは天下の美音でありましたにかゝはらず、この時は尾上になられても、お初になられても、どうしても越路さんは古靱さんに寄りつけなかつたといふことです。藝の位がそれだけ違ふたのでございませう。しかしその裏には越路さんの血の出るやうな御修業の苦心がお有になつたのでした。--後年に攝津大掾さんから折にふれて御修業中のお話を私はいろいろと承はりましたが、いつでしたかその時のお話が出まして、「偉いもんやつた。」と古靱さんのことを仰つしやつておいでになりました。
古靱さんは幼名を豆太夫と申され、初代豐竹靱太夫さんの門人となられて靱小太夫と名乘られました。師匠と一しよに東京にゆかれ、靱太夫さんが東京で客死されたのち明治三年に歸阪されて、古靱太夫と名乘られました。師匠靱太夫さんの歿後は竹本咲太夫さんの門人となられ、咲太夫さんが亡くなられた後は湊太夫さんの門人になられました。
明治三年の七月から、いなり、文樂軒芝居へ入座されましたが、その地位は當時賣出しの越路さん(攝津大掾)より上でありました。花形でお有になつた越路さんの上になられるほどですから、古靱さんのお顔のおよろしかつたことが窺はれると存じます。座元の政策も與かつて、古靱さんと越路さんは自然藝の上の競爭者となられる立場に立たれました。それがまた市中の人氣を呼んだのでありました。
鶴澤兵吉さん--竹本山城掾をお彈きになつたお方--からも古靱さんの偉かつたお話はよく承りましたが、明治四年の九月、いなり文樂座に古靱さんの「三勝半七、酒屋」が出ました時の市中の評判はすばらしいものであつたさうです。今でも殘つてゐる話ですが、古靱さんの、
〽今頃は半七さん。どこにどうしてござらうぞ。
の節の長かつたこと、大變なものだつたさうで「京へいつてかへるほどある。」と云はれたくらゐださうです。それがまた惹き入れられるほどよろしかつたので、長いといふ感じが、聽いてゐて少しもしなかつたさうであります。
古靱さんと越路さんのお二人は、こんな風に轡をならべて、いなり文樂座の兩花形になつておいでになつたのでありますが、前申しましたやうに古靱さんは豪放な御性質、越路さんは地位は古靱さんより下でも、もともと人氣がお有りになり、天性美音のところへ、倦まずたゆまず御勉强なさるといふ風でしたから、藝も進まれますし、人氣も一層華々しくなつてまゐります。遂には座元も越路さんを古靱さんより優遇するといふやうなことになりました。そんなことが原因になつたのか或ひはほかに事情がお有になつたのか、古靱さんは明治六年の四月興行かぎり稻荷文樂【軒】芝居を退座されたのであります。
御靈境内の土田の小屋に櫓を上げられたのは明治十年二月、凶變のあつたのは翌十一年の二月、狂言は「蘆屋道滿大内鑑」で古靱さんが「狐子別れ」を語つておいでになつた、その千秋樂の夜のことだつたといふことです。大掾さんよりは九つお年上でありましたが、行年今を盛りの五十二歳。まことに惜しいことであつたと存じます。本名を木村彌七さんと申上げます。
今日では淨るりの語り口もいくぶん違ふてきてをります。昔は一體に節の足が長うございました。そして息のつゞくかぎりは途中で節を切りませんでした。その頃にはまた、ずゐぶんと息の長い太夫さんがおいでになりました。なかでも攝津大掾さんは特に息が長うございました。「鎌倉三代記」八冊目の、時姫の詞から地合にかゝるところの、
〽どうやらつんと心がすまぬ短い夏のひと夜さに、
これだけの節が一息でした。それがらくらくとしたものでした。聽いてゐて驚かされました。こんな例は大掾さんには、他にいくらもございました。
(話のあとで、話者は三味線を取りあげて右の節を語ります。
〽どうやらつんとこゝろがア--アヽすまア--アヽヽぬみぢイかアヽヽヽヽアい……話者の息はこゝで切れ、一息ではあとのなアヽヽつウヽのオヽひとオヽよオさアヽに。
が殘ります。「あきまへん。息がつゞきまへん。」と話者は云ひます。義太夫を嗜まれる読者は試みてみたまへば、攝津大掾の異常な息の長さを痛感されるでありませう。(完)
以降『文樂聞書』による p275- (初出未確認)
初代鶴澤文藏さんが古今の三味線の名人でお有りになつたことはしばしば申し上げましたが、文藏さんの三味線の調子の合はせ方は、いつも一の絲のサワリがつまつてゐるのに、二の絲三の絲の音がひと一倍冴えてゐたと申します。御存じのとほり三味線は一の絲のサワリがなければ二、三の絲の音が冴えるものではございません。それが文藏さんはさうでなかつたといふことで、二、三の絲の音の冴えは特別であつたと申します。これは當時文藏さんの三味線を聽く人が皆不思議としたところであつたさうです。それから文藏さんの調子は普通より二がちよつと高かつたさうですが、それが正當の本調子であると承つてをります。--三味線の調子については、またあらためてお話いたします。--文藏さんが芝居へ出られると、文藏さんの三味線を聽きに町中の師匠たち法師たちが芝居へ詰めかけたものださうで、法師たちは眼をくるくるさせて文藏さんの絃の音を喜んださうです。文藏さんの三味線は音が大きくて、品があつて、綺麗だつたといふことです。そして生粹の西流の三味線であつたと申します。當時には初代鶴澤寛治さん、或ひは初代鶴澤市太郎さんなどの名手がおいでになりましたが、人形の吉田文三郎さんと、三味線の文藏さんが名實ともに當時の日本一でお有りになつたことは古文書によりましても明らかに窺はれます。
また文藏さんは節付の名人でお有りになりまして、立派な節付を遺しておいでになります。團平さんの節付を研究いたしますと、文藏さんの節付を學んでゐられるところが餘程あるやうに思はれます。名人、名人を識ると申しますか、さすがに團平さんのお偉いところであると存じます。
文藏さんのお手付けで有名なのは「お初德兵衞、曾根崎心中」の敎興寺の段でございませう。これは近松巢林子が世話淨瑠璃の作りはじめの作で、元祿十六年の五月竹本座に上演して未曾有の大當りをとつた狂言と承ります。此狂言は大阪内本町の醬油屋、平野屋忠右衞門方の手代德兵衞が、堂島北仲町、天滿屋の店付き女郎お初と深くいひ交して主人の妻の姪と夫婦になるのを嫌うたのと、油屋の九平次といふ者に欺かれたのを悔んで、曾根崎天神の森で心中したのを仕組んだものであります。天神の森はこの時以來、今もつてお初天神と申します。竹本座初演の時は女形人形遣ひの名人辰松八郎兵衞さんが、このお初を遣つて大人氣であつたと申します。がたゞ今傳はつてをりますのは、安永七年九月、北の新地で上演いたしました時に、近松半二、近松善平の合作で改作しました「往古曾根崎村の噂」上下でありまして、文藏さんのお手付けなされたのもこの改作でございます。原作の「曾根崎心中」の朱は、いまだに私も見たことがございません。「曾根崎村の噂」の初演の太夫は「敎興寺の段」中、竹本是太夫さん、切、竹本染太夫さんでありましたが、何といつてもその當時は三味線の文藏さんと人形の文三郎さんのお二人に御勢力がお有りになつたので、太夫さんは一段下についてゐられたやうです。染太夫さんの語り場のマクラのところ、
〽行迷ふ水の出ばなの一とさかり、すいのしまひはかう果てにやならぬふたりが大阪を、跡に見なしてとぼとぼと、戀の初旅内のまゝ、夕ベは野邊に夜を明かす、あだしが原の道のしも、一と足づつに消えて行く、夢の夢こそはかなけれ。--
こゝは節付手付ともに誠に立派で、いつも感心いたしてをりますが、それだけにまたとてもむつかしくて彈くに彈けぬところがございます。「夕ベは野邊に夜を明かす、あだしが原の道のしも」のところなどは名人團平さんでさへ撥がおろせぬと仰つしやつたさうですから、私どもに彈きにくいのはあたりまへでありますが、どうしても撥が强うなりまして困ります。といつて力をぬきますればまた模様が彈けませぬ。ほとほと撥をおろしかねるのでございます。
私は「敎興寺」は先年亡くなられた竹澤權右衞門さんに敎へて戴きました。權右衞門さんは世話物彈きの名手でお有りなされましたが、その撥の輕いこと、サラサラと誠に綺麗にお彈きなされました。私が彈きますとどうもコチコチして輕くまゐりません。もつと撥を輕く使へと、いつも權右衞門さんからいはれてをりました。恰度そのころ私の連中さんだつた松本蘭鳳さんといふお方--このお方はお素人でしたが、六世竹本染太夫さん、二世鶴澤叶さん。五世鶴澤淸七さん、豐澤小團二さんなどのお歷々の師匠方についてお稽古を積まれ、淨るりの譜章の委しいことは玄人も及ばぬほどで、本も皆御自分で書かれて御自分で朱を入れられました。叶の流れを汲んでゐる緣故から私は鶴五郎の時代から御贔屓にして戴いてをりました。--に「敎興寺」の語りをお稽古なされるやうにお願ひして、蘭鳳さんと同道して權右衞門さんのお宅へ通ひました。私ひとりで三味線だけの稽古をしてゐるのではとても覺えられなかつたからであります。そのやうにして隨分と苦勞いたしましたが、その當時の私には「敎興寺」の三味線といふものがまるで解らなかつたのでした。今日になつてやつといくらか解つてまゐりましたが、依然として撥がおろせません。この「敎興寺」の三味線がサラサラと彈けましたなら世話物は何でも彈けます。「敎興寺」は世話物の大關と申してよろしいのであります。
名人の手付けを彈きまするには、またそれだけの名手がいるのでございます。
團平さんがまだ丑之助さんと申されたころ、ある時伊勢の方へ旅に出られたついでに、初代市太郎さんのお宅へ御挨拶にまゐられました。折あしく市太郎さんは御不在。そこで留守居の人に、お師匠さんの知り邊の者であることを話され、「お目にかゝれぬは殘念でございますが、それではどうかお師匠さんのお三味線なりと拜見させて戴きたい」とお賴みになつて、丑之助さんは市太郎さんの三味線を見せて貰つて歸られました。
あとで市太郎さんが歸宅され、その話をお聞きになつて三味線を取り出して御覧になると、三味線は駒をかけないまゝで、チヤンと調子が合はしてありました。
「丑やな」
と仰つしやつたさうです。
團平さんのお若いころの逸話として傳はつてをります。
御存じのとほり只今の文樂座の兩立物、津太夫さん、古靱太夫さん、お二人とも三代目津太夫さんの門人でゐられます。津太夫さんは後に七代目竹本綱太夫を名乘られました。通名を法善寺さんと申し上げます。南地法善寺境内にお住まひになつて御留守宅は茶店を出してゐられました。
まことに御圓滿なお方で、長らく因講の會長をなさつておいでになつて、斯界の雑多な事件を處理なされましたが、曾て津太夫さんの御處置に不服が出たことはなく、皆心服してをりました。當時副會長は攝津大掾さんでありました。
津太夫さんは優さ形で上品な御風采のお方でした。お柔和な一面にまたなかなか奇才に富んでゐられて、瓢逸なところがお有りになりました。大のおしやれで、お召物なども凝つたものを着てゐられました。夏など、當時流行つた違つた柄を染め分けにした帷子などの上に、いつも折目のくづれぬ薄ものゝ羽織を召してゐられました。お頭もあまり多からぬ髪をいつも綺麗に分けてゐられました。樂屋では「お公卿さん」と緯名してをりました。
お叱言はお口矢釜しく仰つしやる方でしたが、仰つしやる時だけで、あとすぐお忘れになるといふ風なお氣質でした。ある時もしきりとお弟子さんにお叱言を仰つしやつてゐられましたが、しばらくしてそのお弟子さんの姿が見えないので「あいつ、もうどこや行きよつた」といつて舌打をされます。豈計らんや、そのお弟子さんは、おいひ付けでうしろへ廻つてお師匠さんの肩を揉んでゐるのでありました。「お師匠はん、こゝにをりまつせ」「あゝ、さうやつたか」といつたやうな、いたつて罪のないところがお有りになりました。
津太夫さんは小音でありましたが、攝津大掾さんの艶物に對して世話物語りとして世に聞えてをりました。時代物でもなんでもよく語りこなされましたが、お得意は世話物にありました。小音で、口元をモグモグさせるやうにして語られるのでありますが、さすがにそれだけ力量のある淨るりだけに、語り込んでこられるとお聲もよくとほります。よく聽えるのであります。いつでしたか、出し物がなんであつたか忘れましたが、津太夫さんがマクラを語つてゐられますと、見物席から、
「もつと、大きい聲でやつてんか」
といふ聲がかゝりました。ずゐぶんと無遠慮な彌次もあつたもので、聞いてゐて私どもゝヒヤリといたしました。津太夫さんは耳にもかけず、さあらぬ體で相變らず同じ調子で語つてゐられます。だんだん語り込んでゆかれるにつれて、見物はだんだん津太夫さんの淨るりに惹き入れられてきます。果ては場内シーンとして、あちらこちらから感動したすゝり泣きの聲が聞えてくるのでありました。こんな光景を私は覺えてゐます。藝の力といふものを、その時私はしみじみ感じさせられたのであります。
津太夫さんは憂ひがまことによく利きました。殊に子供の出てくる語り物がお得意で、見物はわけなくすぐに泣かされるのでした。子供の聲はなんといふことなしにいぢらしく聞えました「鰻谷」など樂屋の者までつり込まれて泣かされたものであります。
また輕いところは、まことに輕妙で、それがまたよろしうございました。「堀川」の猿廻しの段の、
〽おこすのぢやがな。おこすのぢやがな。けさ稽古したんぢやないかい。えゝなんさらつそい。おれが顔までかきやがるか。とつとも。さりとはさりとは--
のところ、これは昔からあつた型ではありますが、津太夫さんがいつもこゝで大あたりをとられてから、たゞ今のやうにこゝのところがあて場になつたのでございます。こゝのよろしかつたこと、津太夫さんは、全く無類でございました。
お得意のうちでも「大江山、松太夫内」「天王寺村、兵助内」「紙治、茶屋」「沼津里」「湊町」「橋本」「守宮酒」「夏祭、團七内」「妹脊山、杉酒屋」「白石噺、吉原」「戀女房、沓掛村」「お俊傳兵衞、堀川」「忠臣講釋、喜内住家」「忠臣藏、四段目」「お妻八郎兵衞、鰻谷」「おはん長右衞門帶屋」など殊によろしかつたことを覺えてをります。ともかくお聲は小音でも、情のよろしいことなんともいへぬところがございました。上品であつて色氣がお有りになりましたので、八重垣姫とか雛鳥とかお三輪とか、またお染とかさうしたものがなかなかよろしうございました。毎度申し上げます明治二十四年三月、文樂座に「忠臣藏」の通しが出ました時の、大評判だつた「茶屋場」の掛合は攝津大掾さん(當時二世越路太夫)のお輕、はらはら屋の呂太夫さんの平右衞門、津太夫さんの由良之助でありましたが、津太夫さんの由良之助は氣品と貫祿の備はつたまことに立派な由良之助でございました。攝津大掾さんのお輕との例の、「由良さんか」「おゝお輕か、そもじはそこに何してぞ」「わたしやお前にもりつぶされ、あんまりつらさにゑひざまし、風に吹かれてゐるわいな」の文句の掛合ひのところなどのよろしさは、全く絶品と申すほかはございませんでした。
津太夫さんに一度こんなお縮尻がありました。ある時、津太夫さん十八番の「日吉丸」の「ほとけさままで無理いうて」といふ文句のところを「ほとけさままで髪ゆうて」と仰つしやつたものですから、見物はドツと大笑ひをいたしましたが、その時の津太夫さんが、一向平氣でケロリとしてあとを語りつゞけてゐられた度胸には感心いたしました。
餘談になりますがこんな縮尻はほかの太夫さんにもまゝあることで「新口村」の、「京の六條珠數屋町」を「京の三條--」といつてしまつたので「--また三條、合せて六條珠數屋町」といひ替へたといふ苦しい機轉を利かした話や「加賀見山」の奥庭の掛合で、岩藤を勤めてゐる太夫さんが「ナニ岩藤どのは死なれたか」といつたもので、見物がドツとくるのを、おつ冠せるやうに「--いやそれはわたしの名。ナニ尾上どのは死なれたか」とやつてのけ、スッカリ見物の笑ひを押へつけてしまつたといふ大胆不敵な例もあります。津太夫さんはいひ直しなどなさらず、しまひまでシラをきつてゐられました。
津太夫さんは御本名を櫻井源助さんと申し上げましたが、そのころ大阪で、惡いことやへまなことがあると「源助やな」といふ言葉を使ふことが流行つてゐました。それで津太夫さんをお呼びするのに、お口の惡い大隅太夫さんなどは面白がつて殊更仰山さうに「源助はん、源助はん」と仰つしやるので、これには津太夫さんも閉口しておいでになりました。
津太夫さんは京都のお生れで、安政三年に竹本山城掾さん--近世のチヤリ語りの名人--の門に入られ、幼名を緑太夫と申され、元治元年に三代目竹本津太夫になられ、文樂座へ入座されたのは明治九年十月でありました。明治四十三年に七代目竹本綱太夫をお繼ぎになり、同四十五年七月二十三日、七十四歳でお亡くなりになりました。御趣味としては歌舞伎見物が何よりお好きであつたと聞いてをります。
「凝り固まり」といはれただけに三代大隅さんは藝一方のお方でありました。藝道以外のことは何事も捨てゝ返り見られぬといふ風でした。失禮な申し上げやうですが、大隅さんのなさることが時には思慮に缺け、時には放埒と見えたのも、所詮はさうした童心的な無頓着からで、大隅さんの關心はたゞ一途に藝道だけにあつたのでした。
東京の杉山茂丸翁からお聞きした話ですが、杉山さんはかねて大隅さんを大變に御贔屓になさつておいでになつたのですが、ある時、一時ではありましたが大隅さんと絶緣されたことがありました。
その事情は杉山さんに承りますとかうなのです。杉山さんは、大隅さんが単獨で文樂座へ入座された時も、取殘された堀江座組に同情されて、一應は大隅さんを責められたのでしたが、入座されたあとのことではあり、濟んだことは致し方ないとして、文樂座へ這入つた上からは、二代越路さん(攝津大掾)のあとを繼いで紋下になる覺悟がなくてはならんと励まされたのでした。また二代越路さんに向つても、越路さんが預かつてゐられた師匠春太夫さんの名跡をゆくゆくは大隅に讓つてやつてほしいと杉山さんは賴み込まれました。--二代越路さんと大隅さんは同門であります。--杉山さんは、どうかして大隅さんに御靈文樂座でひと花咲かしてやりたいと思はれたのでありました。ところが僅か一年足らずで、堀江座の方の春子太夫さんや伊達太夫さん(今の土佐太夫)などと一しよに北海道へ巡業にゆかれることになり、それを機會に大隅さんはまたフイと文樂座を退座してしまはれました。力瘤をいれてゐられた杉山さんの期待はみんごと外れたばかりでなく、色々と越路さんに賴みこんであつた杉山さんの面目は丸潰れとなりました。もともと大隅さんの性格はよく御存じの杉山さんも、この時ばかりは肚に据ゑかねられて、「もう二度とあんな者はあひてにしない」といふことになり、絶緣となつたのでありました。
その後は大隅さんが幾度お訪ねしても絶對に杉山さんは會はれません。大隅さんは玄關からスゴスゴ引返さねばならなかつたのでした。
この時の大隅さんの北海道巡業はさんざんの失敗であつたさうですが、その後に東京の明治座でその一座が興行したことがありました。杉山さんは依然として大隅さんに會はれません。それでも大隅さんは、もしや杉山さんが默つて聽きにこられないかと思つて、弟子たちにいひ付けてそれとなく注意さしてゐられたさうです。杉山さんももとより好きな道、毎日新聞でその日その日の番組を見ておいでになつたのですが、或る日、その日の大隅さんの語り物が「布引四段目」と出てゐました。これは住太夫風の純西流の物、大隅なら嘸かしうまく語るであらう。さう思はれると杉山さんも聽きたくて仕方がありません。たうとうその晩コツソリと明治座へ出かけてゆかれました。雨の降る冬の夜で、杉山さんは乘つてゆかれた自動車を久松署の門前に待たしておいて、外套を頭からスツポリと被つて明治座の木戸を這入られました。平場を見渡すと、客の頭かずは僅か六七十人、雨降りのせゐかまことに少い入りです。杉山さんは二階棧敷から、見付からぬやうに外套を被つたまゝ寝轉んで聽いておいでになりました。
やがて大隅さんは舞臺へ出られ「布引」の四段目を語られます。三味線は豐澤仙左衞門さん(源吉--仙左衞門--後に三代團平)でした。早くも杉山さんの見えてゐることが注進されたか、大隅さんはこゝぞとばかり一生懸命。その晩の出來榮えは格別によろしいのでした。
〽きのふまで秋の雲井の御住居も、今日はさびしき冬枯れて--
その音づかひのよさ。マクラから早や杉山さんは大隅さんの淨るりに惹き入れられてしまはれるのでありました。つゞいて例の三人上戸のところ、小櫻が平治に責められるところ、琵琶になつての平家節のところなど、ことごとくが無類の出來であるのです。ジツと聽いてゐられた杉山さんはつくづく感じ入られて「これほどの藝を持つてゐるといふのは、さすがに偉いものだ」と思はれたさうです。大隅さんの舞臺がすんだので、杉山さんは小屋を出られ、待たしてあつた自動車に乘らうとされると、雨のなかを大隅さんは土下を取つただけの着付のまゝでマントを引被り、息せき驅けつけてきて「旦那ツ」とひと言いふなり杉山さんにつづいて自動車に飛び乘つて、バタンと扉をしめてしまふのです。杉山さんは今夜の淨るりに感心して氣持が和らいでゐられたところだつたので、大隅さんの不意打ちを怒る氣にもなれず「こいつには勝てぬ」と思はれると自然笑顔になられないわけにはゆきません。自動車はそのま、旗亭へ廻されました。--そんなことからまたもともとどほりお出入りが叶ふことになられたのださうです。
「それからまた大隅が宅ヘくるやうになつたので、時々俺が覺えてゐる淨るりの節に疑問があると尋ねるのだが、それが間違つてゐたりすると、一體誰がそんなことを敎へましたか、それは何太夫風だから、かうですと容赦なくピシピシいふ。早速こんどは俺が叱られる番になるのだ。あとで攝津大掾に訊いてみてもいつも大隅のいふとほりだつた。藝のことゝなると大隅は確かなものであつた」と杉山さんはつい先だつてもその話が出た時仰つしやつておいでになりました。
僭越なことを申し上げますが、大隅さんの藝に對する眞つ正直な心、それが杉山さんを動かしたのであると存じます。そしてそれが大隅さんの持つておいでになつた貴い寳であつたと存じます。
まだ團平さんが御在世で、大隅さんが稻荷座の紋下でお有りになつた頃は、御存じのとほり團平さんが大隅さんを彈いておいでになりましたが、御一しよに舞臺を勤めて床をおりてこられると、冬でも大隅さんは汗ビツシヨリ、それに團平さんは「寒い寒い」と仰つしやつて、お部屋へ這入られるとすぐ火鉢のそばへ寄つておいでになつたさうです。
あれほどに鍛錬を積まれた大隅さんが、汗みづくになつてウンウンぶつかつてゆかれても、まだ團平さんを圧することは出來なかつたのでございませう。
團平さんがお亡くなりになつたあとで、前にも申し上げましたやうに、私の師匠三代目淸六さんが大隅さんを彈かれることになりましたが、今度は大隅さんから「團平さんはこゝをかう彈かれたからそのとほり彈いてくれ」といふ御注文がたびたび出るのですが、それがどうしても師匠にはそのとほりには彈けなかつたさうです。師匠もあれほどの名手であり、團平さん御在世中には團平さんのところへも御稽古に通つてゐられて、殊にはげしい御稽古であつたと聞いてをりますが、それこれ思ひ合はせますれば團平さんの及び難いお偉さが感じられるのでございます。
淸六師匠も暫く文樂座を出て、大隅さんを彈いてゐられたこの時代に、右のやうに非常に苦しまれただけ、それだけ腕を磨かれたのでした。弟子として生意氣なことを申すやうですが、舞臺で偉いお師匠さんがたのツレ彈きをいたしてをりますと、そのお師匠さんの絲の音が、右の耳ヘビンビン響いて困るのです。五代目の吉兵衞さんなど殊にはげしうございました。淸六師匠が稻荷座の方へゆかれないさきには、それがまだそれほどには感じられませんでした。ところが大隅さんと御一しよにまた文樂座へ歸つ蒔てこられて最初の出し物が大隅さんの「壺坂」で師匠の三味線、私は文樂座に居殘つてをりましたので、久しぶりに師匠の三味線のツレ彈きをいたしましたが、師匠の三味線の音が私の耳にとてもひどくビンビン響くので、「偉いもんやな」と内心竊かに私は驚いたのであります。私の若年鶴太郎時代のことでございます。
私がまだ鶴一郎で、たしか十五歳だつたと覺えてゐます。今の古靱さんがつばめさんで、私より一つ年上ですから十六歳だつたわけです。
ある時、そのころ梅屋敷にあつた成駒屋さんの別邸へ一しよに遊びにいつたことがありました。お稻荷さんの祭事とか、何かさうしたお催しで招かれたのであらうと思ひますがお覺えてゐません。ほかにも大ぜいお客があつたやうでした。一日中遊び暮らして、さて晩になつてお客の前でつばめさんが淨るりを語り、私が三味線を彈くことになりました。語り物は「玉藻前三段目」でした。はじめのあひだは無事だつたのですが、奥の「双六」のところになつて、どうしたのか三味線の手を忘れてしまつて、どうしても思ひ出せません。昼間あまり有頂天に遊びほうけたので度忘れしたのでありませう。一生懸命に語つてゐたつばめさんは私が彈きやめたので、
「どないしたんや」と尋ねます。
「忘れたんや」といふと、
「忘れるといふことがあるか」
つばめさんはスツカリ憤つてしまひます。私は躍起になつて思ひ出さうとするのですが、まるで思ひ出せません。果ては悲しくなつてきて、たうとう三味線を前へ置いてシク/\泣き出してしまひました。「もうえエ、もうえエ」さういつて、聽いてゐられたお客さんたちがなだめて下さつて、淨るりはそこまででやめになりました。今考へると子供だつたと思ひます。古靱さんは覺えてゐられるかしら……。
それよりもまだ小さかつたころのことだつたと思ひます。
文樂座の舞臺で、ツレ彈きの豆くひ(ツレの末端の位置)に出てゐまして眠りこんでしまつたことがございました。御靈文樂座では掛合でツレ彈きが大ぜい出る時には、棧敷の横の通ひ路の方へ折り曲げて床を附け足しますので、豆くひは廊下の戸口に近い隅つこに坐るわけでありました。無暗と朝が早いので、自分の彈き場がすんで、ジツと薄暗い隅つこに坐つてゐるとつい眠たくなつてくるのでした。その時はたうとう眠り込んでしまつて、みんなが這入つてしまつたのも知らず、ひとり取殘されてゐたのでした。
「起きなはれや、もうすんましたぜ」
さういつて見物のお方がゆり起して下さいました。ハツと驚いて目を覺めました私は、ヒヨコリと御辭儀するなり、慌てゝ床内へ飛んで這入りました。「無理ない。小つちやいさかいなア」とその見物のお方が仰つしやつてゐられるのがきこえてゐました。私は、特別に柄が小さくて、三味線の方が大きく見えるくらゐだつたのでさう仰つしやつたのでせう。しかし私はそれどころではなく、叱られる心配で一杯でした。師匠の耳に這入ればそのまゝではすみません。が幸ひにその時は師匠の耳に入れないやうに計らつて戴いたので叱られずにすみました。
やはりその時分のことでした。豆くひに出てゐて、幕になつて這入らうとすると、
「あんた、これおあがり」といつて、私の前の床の上へ、鮨の皿に入れたのをチヨンと置いて下さつたお見物がありました。お年寄りの女のお方でした。やはり私があんまり小つちやいので可愛く思はれたのでありませう。面喰つた私がモジモジしてゐるのを見て、「かましまへんがな、おあがり」
と何べんもすゝめて下さるのでした。もとより舞臺でそんなものを戴くわけにはまゐりません。私は赤くなりながら御辭儀して樂屋へ這入りました。どこのお方か知る由もございませんが、昔はこんなお氣合ひのお見物がおいでになりました。
私が文樂座へ入座した頃には、私の生家はもうだいぶんに逼塞してゐたのでありますが、それから四、五年經つて私が十六、七歳になつた時分にはスツカリどん底に行き着いてしまひました。父は道具屋でしたが、それまで北堀江の御池橋のほとりに開いてゐたさゝやかな店も疊んでしまつて、そのころ新町の義太夫藝者で近作さん(初代)といふ人の家形が堀江の隆平橋の北詰にあつたそこの二階を借りて母と一しよに佗しく暮してをりました。父は自分の手に合ふものを扱つていくらかは稼ぐのでありますが、それだけではとても遣つてゆけませんので、どうでも私が働いて家計の足しをしなければならなくなりました。恰度私は少し事情があつて、それまで寄寓してゐた淸六師匠(當時鶴太郎)の家を出ることになりましたので、其の二階へ歸つて、そこではじめてお素人の連中さんをとつて札稽古をいたしました。--札稽古といふのは、さきに何枚か札を買つておいて貰つてその札を持つて稽古にきてもらふ。そして一枚ぶんなり二枚ぶんなりのお稽古をするのを申すのであります。--私が札稽古をいたしましたのは、あとにもさきにもこの時だけであります。しかしさうやつて一生懸命稼いでも、まだ若輩のことではあり、それに文樂座の出勤、樂屋の用事の手傳ひ、師匠の御用などに手づかへぬやうにしなければならず、私自身も修業盛りの年ごろですから自分の稽古も疎かに出來ませんので、思ふやうには働けず、いくらの稼ぎにもなりません。親子三人の暮しはなかなからくではありませんでした。そのころ父は安物のニツケルの目覺まし時計を扱つたりしてゐましたが、なんでも元價一個五六十錢のもので、それを十錢か二十錢口錢を取つて賣つてゐるやうでした。私はそのころから時計が好きで、その目覺まし時計を一個だけ手許に殘しておきたいものだと思つてをりました。ある時父に、
「それ一つ殘しといて貰へまへんか」と申しますと、
「殘しといてやりたいけど、そないすると手許の都合が惡いねん。氣の毒やけど辛抱し……」と父はいひ憎さうに申されました。お笑ひになるかも存じませんが、なんといつてもまだ若年のことですから、父にさういはれると我が身のうへが恨めしいやうな氣持がして涙がこぼれてくるのでした。それからも時々その安物の目覺ましを、横眼で睨みつけては「なに、いまにもつといゝ時計が買へるやうになつてやる」と思つたりするのでした。お恥かしいことですが、それほど窮迫してをつたのであります。文樂座からはまだ給料を戴いてをりませんでした。
文樂座は入座すると最初は見習ひ、それから「大序」、これは太夫も三味線彈きも同じであります。ミス内で太夫は一人づつ交替で語り、三味線も一人づつ彈きます。私が大序にゐました時分には、三味線彈きは大ぜいだつたので三組にわかれて、組は毎日交替でありました。但し大序のしんと二枚目は交替しません。大序にも二枚目、三枚目と順位があつて、最後に大序のしんになるのです。大序のしんになつてはじめて座元から給料が出るので、それまでは無給であります。大序には少くても六、七年はゐなければなりません。もつと長くゐる人もあります。黑鶴さんでとほつてゐた二代目の鶴澤鶴太郎さんのやうなお方でさへ、七年おいでになつたと聞いてをります。私も大序に恰度七年をりました。大序をぬけると「序中」になり、それから「序切」の口、中、切といふ順序で、「序切」の切は三段目、四段目の「立端場」になるのです。こゝまで漕ぎつければもう一人前で、樂屋の風呂へ這入ることを許されます。私はそのころ大序の無給時代であつたのでした。
私は生活が苦しいにつけても、なんでも一生懸命に修業して偉くならなければならないと思ひました。--その時分には私はまだまだ知らない物が多かつたので、連中さんがお習へのために合はせに見えたりすると、本を出されるまでは不安でした。知つてゐる物だと竊にホツとするのでした。生活の糧のためにも稽古は忽せに出來なかつたのであります。--しかし淸六師匠のお宅へ伺つても、なにしろ師匠は當時花形でお有りになつただけに公私ともにずゐぶんとお忙しくてしよつちうお稽古をして戴くといふわけにはゆきませんでした。それに師匠は、「修業は自分でするものだ」とつねづね仰つしやつてゐられました。私はいくらか小錢が出來ると、本屋を漁つて三味線の朱の入れてある古い五行本を探しました。倖なことにその時分にはさうして探してゐると、思ひがけなく故人の朱や名ある師匠がたの朱の這入つた本が手に入ることがございました。私はさうして買ひ聚めた本を手賴りに、その時分はおほかた獨り稽古をしてをりました。その時聚めた本は今でも殘してをりますが、今日になりますと、またと手に入れがたいものもそのなかにございます。私が義太夫に關した古書を聚める癖もそんなことからはじまつたのでございます。
私の第二の苦難時代は三十七歳の歳に大病で入院した時でありました。醫者には手を放されますし、家には餘分の貯へとてはなし、命旦夕に迫るといふに、病院に寝てゐて節季の心配をしなければならぬといふ有様でした。この時はさる御贔屓の御庇護によりまして、費用の心配もなく、幸ひに命を取止めることが出來ました。今以て御贔屓にして戴いてをりますが、このお方は全く私の命の恩人でございます。
長々と身の上話に渉りまして恐れ入りますが、過ぎ去つたことを色々考へますと、今日人並みに暮らさせて戴くのも、偏にこれ藝道のお蔭、淸六師匠ならびに敎へを享けた師匠がたのお蔭と存じてをります。また苦しい生活のなかからも忽せにせられなかつた兩親(ふたおや)の御薫陶の恩も淺からぬのでございます。
敎へて戴いた師匠がたのなかでも、五代目の野澤吉兵衞さんには私の鶴五郎から鶴太郎時代、六代目豐澤廣助さん(後に名庭絃阿彌)には叶になつてから、特に御敎授にあづかつてをります。私には忘れてならないお二方であるのでございます。
これも杉山さんから承つたお話。
ある時杉山さんが博多へ歸省してゐられると、恰度巡業で久留米へ行かれた三代越路さんが、それを聞いて杉山さんを訪ねられたことがありました。その時越路さんは杉山さんに、
「旦那にひとつお願ひがおます。實は只今師匠(攝津大掾)に志渡寺を稽古して貰うてますのやが、もう半年餘りにもなりますのんに、いつまで經つても源太左衞門の入りまでで、奥を稽古してくりやはりまへん。私も御覧のとほり頭も白うなつてますのんに情なうおます。旦那から師匠に奥を稽古してくりやはるやうに賴んで貰へまへんやろか」と賴まれました。
「よしよし、賴んでやらう」
杉山さんは氣輕に引受けられて東京への歸途大阪へ立寄られ、攝津大掾さんに會つてその話をなさいました。
ところが、思ひもよらず攝津大掾さんは大變な不機嫌なのです。
「あれがそんなことを旦那に申しましたか。なんといふことを申します。稽古がらく過ぎるからそんなことを申すやうになるのです。私どもの修業中といふものは、朝から晩まで師匠(五代目竹本春太夫)につききりで御用をいたしたものです。旅に出てゐる時など、毎晩師匠がおやすみになる前に師匠の按摩をいたしまして、自分の宿へ歸るのはたいてい十二時過ぎでありました。按摩をするにも師匠はあのとほりの大兵でしたから、坐つてゐては肩を揉むことができません。いつも中腰になつて揉んでをりました。そのやうにしてをりまして、さていつ一度お稽古をして戴くといふことはありません。ある時も、こんど大阪へ歸つたら正月に伊賀八を出す。その時お前に相合傘(伊賀八の中)を語らすからシッカリ稽古しておけと仰つしやる。有難く思ひまして新左衞門さん(先代。當時の合三味線)に習つて一生懸命稽古をして、それが出來たので師匠の前で語つて聽いて貰ひました。私が語るのを聽かれて、師匠は立つて濡れ手拭を取つてこられ、「あとはそれでよいが、馬子のそゝりがいかぬ」といはれて師匠が自分で唄うて聽かして下されました。
〽いやかいの、いやかいの、いやなゝゝア--風にもなびかんせよヲ--
「いやなゝゝア--」で肩をゆすつて、持つてゐられた手拭ひを肩へひつかけられ、そして「風にもなびかんせよヲ--」と唄はれます。「この意氣でやらねばいかん」と仰つしやる。これだけが私の稽古でありました。それにくらべると、あれはどうです。身持もよろしくない。私のところへも朝遲くまゐりまして、それで毎日半段づつ稽古してやつてゐます。結構すぎるのです。それにまだそんなことを申すとは以てのほかです。ほかのことならあなたのことですからなんでも肯きますが、こればかりは肯かれません。奥を稽古しないのは源太左衞門がまだ住太夫風になつてをらんからです。自分の勉强の足らぬことも思はずに、そんなことを申してをるやうなら、これで三十七へん目ですが、今度といふ今度はいよいよ勘當いたします。あなたもどうかうつちやつておいて下さい」
大掾さんは杉山さんを睨みつけ一るやうにしてさう仰つしやつたさうです。
「濃い眉毛の下から俺を睨みつけるのぢや。その時の攝津大掾はちよつと怖かつたよ」と杉山さんは仰つしやいます。
杉山さんからあとでその話を聞かれて、三代越路さんは平身低頭してゐられたさうです。大掾さんはそれ以後フツツリと「志渡寺」のお稽古を打切られて、二度となされなかつたさうです。
温容そのものゝやうな攝津大掾さんも、事藝道に關するかぎりはこのやうに御嚴格でおありになつたのでございます。
まづ三味線から申しますと、間拍子と呼吸と足どり、この三つが兼ね備はるといふことが、義太夫三味線の極致であります。かう言葉で申すのは易いことでありますが、これは難中の難事でありまして、尋常一様で到り得る境地ではないのであります。未熟な私ごときは一生かゝつても、とてもその域には達しられさうもありません。名人團平さんの三味線には、立派にこの三つが揃つてをつたと承つてをります。つまりこの三つが揃へば三味線の名人であるのでございます。これは勿論語りの方にも當嵌るのでありますが、主として三味線についていはれるのであります。三味線は彈くところよりも、彈かぬところがむづかしいのであります。
つぎに「阿呍の呼吸」と申すことがございます。これは太夫が息を開けば、三味線がそれを押へ、太夫が息を押へれば三味線がそれを開く、それを申すのであります。たとへば「忠臣藏、九つ目」
〽[詞]これ小浪あれを聞きや、表に虚無僧の尺八、[合]チン、鶴の巢籠り鳥類さへ、--
「すごオヽもオヽヽリイヽヽ」と「リイヽヽ」を太夫は音を押へ込みますので、三味線は「あーッ」テテンと開くのです。その反對にたとへば「御所櫻」のマクラ。 〽その一人と呼ばれたる、武藏坊辨慶。 では「むさしイばうー」で三味線を開き、「べんけい--」と太夫が開いて張りますので、三味線は「むッ」ヂヤンヂヤンと一を押へて締めるのです。開くにも、押へるにも、太夫、三味線ともにそれまでは息をつめてゐなければなりません。三味線の掛け聲と同時に太夫は息をつぐのが本當なので、こゝらに太夫と三味線の呼吸の合ふといふ妙味があるのであります。本來淨るりの節付がそのやうに付けてありますので、「阿呍の呼吸」といふことが出來なければ、本當に淨るりが語れも彈かれもしてゐないのでありますが、これとてもなかなか修練のいることで、それを體得して堂に入るといふことは一朝一夕で出來ることではないのであります。 以上は技巧(わざ)についてのことでありますが、語るにも彈くにも、その心構へといふことがまた大切であります。語る方については古名人がたの敎訓も澤山遺つてをりますが、それはまたの折にゆづりまして、三味線について申しますと、以前にも申しました名人文藏さんの歌、
三味線は胸には彈きて手にひくなひけよひくなよ心すなほに
この一首のこゝろに、三味線を彈く心構へはつきるのであります。
それから私は、藝と申すものは、眞つ正直な心で勤めなければ出來るものでないことをいひ添へたいのであります。
三味線は心正しく彈くものぞ心にごれば音もにごるなり。
まことに稚拙な歌で、お笑ひ草でございますが、こゝろを汲んで戴ければ幸に存じます。
-自昭和七年至同八年文藝春秋・昭和九年週刊朝日-
舊著「藝と文学」が再版されるのを機會に「鶴澤叶聞書」だけを殘し、その後に書いた「團平の憶ひ出」を新たに加へ、本の題も「文樂聞書」と--智慧のない題ではあるが--改めることにした。さうすることによつて、内容に統一を與へたく思つたからでもある。
「團平の憶ひ出」
これはもつと長く續けて書くつもりでゐた。道八師も、それまでに他で斷片的に話したこととの重複を厭はずに、集大成的なものにしたいといふ意向であつた。私も、はずむ心を抑へかねて、神戸の道八師宅へ通ひつづけたのであつた。恰度、話が團平の行狀から藝談に立ち至らうとする間際に、計らずも師は神經痛で倒れた。そして病蓐にあること半歳、一時小康を傳へ聞いたが、遂に起たなかつた。結果は「團平の憶ひ出」もこれだけのものに終つた。--貰つた娘さん一人を相手の寂しい家庭であつたが、空襲で神戸が燒けてからの、その方の安否さへ私は知らずにゐる。師が所藏してゐた團平の遺品も、灰燼に歸したのでないかと思ふ。他日のためにと、丹念にそれらを撮つておいた写眞原版も、私の手許で燒失した。今となつては、とりつく島もないのである。
--道八師のもとへ繁々と通つてゐた頃、よくそこで、中堅の或る太夫が稽古を受けにくるのに出會つた。たまたま稽古が「壺坂」に及んだ時、師は「團平師匠の節付なさつたものですから」と、稽古の日時ををしへて、私にその稽古を聽くやうに慫慂された。--私の聽いたのは後半の「壼坂寺」の一部であつたが、傍で聽いてゐる私にもカンどころを敎へるといふ心遣ひもあつてか、細かい所にまで行渉つた叮嚀な稽古であつた。そして、それはかくあるべしと思はれる、佗しい味はひの「壼坂」であつた。しかし師の修練を積んだ技巧(わざ)のうまさは、その若い太夫に蹤いて行ける底のものではなかつた。たとへば山道で澤市が口三味線で唄ふ「憂きが情か」の唄にしても、師は口をふさいで唄へ、といふ。また唄の末節の「テチン、わが身の上は……」で泣くところも、口で泣かずに肚で泣け、といふ。これだけのことでも、その太夫には、ひととほりは、いはれたとほりやつてゐたが、聽いてゐる私にも納得がゆく程には、しまひまでやれなかつた。--途中で、師は三味線を膝に置いて、仰むき加減に少し首を突き出し、ふさいだ唇を尖らすやうにして、眼をつぶつて「憂きが情けか」を、はじめから唄つて聽かせるのであつたが、瞬間に容(すがた)そのものが、一箇の青白い盲人になりきるのを見て、私は慄然とした。その容(すがた)は今も印象に刻みついてゐる。泣くところも、師のは、忍ばんとして洩らす切ない鳴咽であつた。藝の技倆(ちから)の逕庭は一朝一夕で追付けるものでないことを、私は痛感せずにゐられなかつた。が、つけ加へておきたいのは、その太夫の謙虚な稽古振りである。私は好感を持つた。その後は、個人的にはなんの交渉もないその太夫の床(ゆか)を、私はそれとなく注意するやうになり、文樂座では、まだ上席の方ではないその太夫の、奮起と大成を望む氣持にも、いつか私はなつてゐるのである。
話は別であるが、序にもう一つ、ここへ書いておきたい道八師の言葉がある。
「これで、義太夫(われわれ)の方は難儀なしようばいでして、太夫も三味線もまるで金魚みたいにハツプ、ハツプと呼吸(いき)をするだけで、一段すむまでは、まともに呼吸(いき)ひとつすることもできんのでつさかいなア……」
巧まない、平易ないひ方で、これは太夫、三味線の床に於ける呼吸遣ひを、よく説明してゐると思ふ。讀者の義太夫節鑑賞の一助ともなれば幸である。
「鶴澤叶聞書」については別段にいふことはない。これを書いて、もう十四、五年になる。當時の私には義太夫節といふものの性格が、まだ充分に肚にたたき込まれてゐなかつた。話の受取り方に、手ごころの不慥かさがあつた。裏側へ手を廻して、突つ込んでものを訊くだけの用意は、もとより私になかつた。「鶴澤叶聞書」に、なほ讀者の興味を繋ぐものがあるとしたら、それは叶師が克明な性分から、諄いほどにも念を入れて話をしてくれたことに、功を歸せねばならないのである。
叶師は昭和十七年三月改名して、二代目鶴澤淸八を名乘つてゐる。兩三年前から四代目竹本大隅太夫の合三味線を勤めてゐる。
淸八師は昨年過つて兩手を挫いた。もう一度撥が持てるかが氣遣はれた。療養中、師は再三、他の三味線で舞臺へ出るやう大隅太夫に勸説したが、大隅は肯んじなかつた。然るに、その後にまた、不慮のことから師は一眼を失明した。重ねがさねの災厄であつたが、本年二月、文樂座再築落成の興行から、再び兩師揃つて床へ出てゐる。--淸八師は左手首にまだ繃帶を殘してゐるが、晴れた面持には憂悶のあとかたをとどめない。氣組に聊かの衰へも見せず、撥はさらに冴えまさつて聽かれる。--私は心から師の再起を悦ばずにゐられない。
私が、なにゝ牽かれて、飽きずにこのやうなものを書くかをいへば、たとへば團平をして、食膳に箸を措かしてまで技巧(わざ)の工夫に耽けらしたものは、藝といふものを、どこへ持つて行かせようとするのであるか。その深奥の藝境に宿るものは何なのであるか--朧氣にもそれに觸れたい氣持からにほかならぬのである。再版に際しても、また池田小菊さんの勞を煩はすこと多大であつた。謹んで謝意を述べる。
昭和二十一年四月十三日
著者
昭和二十一年五月十五日印刷
昭和二十一年五月十五日發行